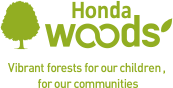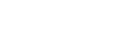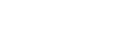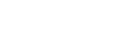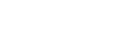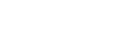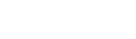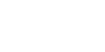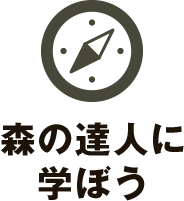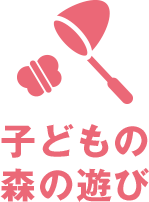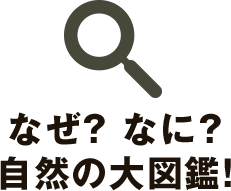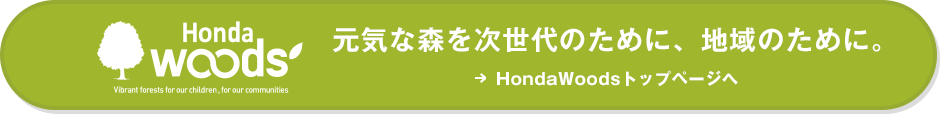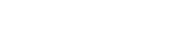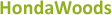
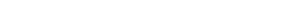
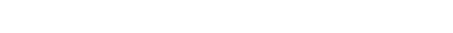
2024.09.26
海の生きものを観察する磯遊びのすすめ(後編)
タイドプールで魚を捕まえてみよう!


ハローウッズ キャスト
奥山 英治
こんにちは!日本野生生物研究所の奥山です。前回は海岸のタイドプールで生きもの観察する「磯遊び」をご紹介しましたが、今回はいよいよタイドプールでの魚の捕まえ方をご紹介します。動画をじっくり観て、自分でもぜひ挑戦してみましょう!
暑さが続く9月から10月にかけては「磯遊び」の絶好のシーズン
まずは前回のおさらいから。海に行くと、海水浴をするような砂浜とは別に、岩がごろごろしている「磯」と呼ばれる海岸があります。そこでは、潮が引いたあと岩のくぼみに海水が残り、小さなプールが出来上がっています。これを「タイドプール」と呼び、いろんな生きものが取り残されて海の生きもの観察に恰好の場所になっています。
このタイドプールで生きものを捕まえ、観察する遊びを「磯遊び」と言います。海水浴シーズンが終わった9月以降もまだまだ暑い日が続きそうなので、これからは「磯遊び」に絶好のシーズン。行く際の準備、持ち物、注意点などは前回ご紹介していますので、よく読んでから出発してください。
→ 海の生きものを観察する磯遊びのすすめ(前編)
タイドプールでの魚の捕まえ方をご紹介!
●その1:網で待ち伏せ
この記事の冒頭の動画で紹介している捕まえ方です。
磯にできたタイドプールを見て回っていたところ、元気に泳ぐ魚を発見しました!
イソスズメダイの幼魚です。この魚を捕まえようと、網を左右に2本持ってタイドプールの中に差し込みます。ここで注意したいのは、逃げ惑う魚を網で無理に追いかけようとせず、網を動かさないようにして魚のほうから網に入ってくるのを待つこと。
2本の網があれば、魚の前後をふさぐことができるので、自然と魚のほうからどちらかの網に寄ってくることになります。魚が網に入ったら素早く引き上げればOKです。
●その2:網に追い込み
さらに磯を探索していると、水路のような細長いタイドプールに数匹の魚を発見しました。そこで今度は、2本の網を使って挟み撃ちで捕まえることにしました。
1本の網は水路をふさぐように固定し、もう1本の網を水の中でバシャバシャさせて魚を追いたてて固定した網の方へ追い込みます。魚たちが固定した網に入ったら素早く引き上げればOKです。
このプールで採れたのはアゴハゼでした。アゴハゼは磯の海ではたくさん見つかります。捕まえる前に動きを観察してクセをつかんでおくとと捕まえやすいですよ。
タイドプールでの魚の捕まえ方をご紹介!
それでは、磯遊びに行ったときに見つけた生きものが何という生きものなのか分かるように、タイドプールで捕れる代表的な生きものたちをご紹介しておきましょう。

キヌバリ
黒とオレンジ色のゼブラ模様。石の下に隠れますが、普段は中層で浮くように暮らしています。

ナベカ
腹部から尾にかけて黄色く腹部から頭にかけて黒いゼブラ模様。普段岩の上などで行動しています。

クモハゼ
ずんぐりしたフォルムで岩の隙間や石の下など底で暮らしています。プール内の石や岩をひっくり返すと見つかります。

イソスジエビ
透明で黒いスジが数本あり、尾の先に丸くオレンジ色の紋があります。

ニホンクモヒトデ
触手が細く長く、昼間は砂に潜っています。少し大きな石などの下に隠れています。

バフンウニ
夜行性で昼間は隠れているので、大きな石などをひっくり返すと石に張り付いています。

ヒライソガニ
日中はあまり動きませんが、プールで石などをひっくり返すと慌てて砂に潜ります。

ホンヤドカリ
タイドプールの中で貝が動いているように見えますが、よく見るとヤドカリです。すごく小さいのも見つかります。

カゴカキダイ
黄色と黒のゼブラ模様の目立つ綺麗な魚。数匹で行動していることが多いです。

オヤビッチャ
面白い名前で覚えやすい魚です。縞模様が特徴ですが黒い筋は腹部途中で消えています。

メジナ
グレーで幼魚の間は群れて行動しています。目がブルーでとても綺麗。大きく成長すると釣りの対象魚として有名です。
●磯の危険な生きものたち
磯にいる生きものの中には、危険なものもいます。次に挙げる生きものを見つけたら注意してください。

ガンカゼ
ウニの仲間で細く長い棘には毒があり刺さるとヒリヒリします。棘が折れやすいので触らないように。

ハオコゼ
背ビレに毒を持ち刺さるとビリビリいつまでも痛くなります。見つけても捕まえないように。

岩に生えている海藻類
陸にさらけでている海藻類は歩くときに踏むと滑ります。海藻は陸では踏まないように行動しましょう。

岩につくカキ類
張り付いたカキ類の縁は薄く尖っていて手をついたりすると切れる事があるので要注意。
磯遊びで捕った生きものは飼育ケースなどに入れて観察しましょう。生きものたちのいろんな特徴が見えてきていっそう楽しめます。ただし、最後は海に戻してあげるのを忘れないように。
それでは皆さんもぜひ磯遊びを楽しんでください。

磯遊びで捕まえた生きものたち