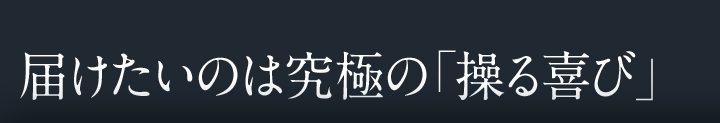「クラス最軽量・最コンパクトなバイクづくりによって、ワークスの走らせるRVF750を鈴鹿8耐で打ち負かす」。そんな野心的な試みからスタートし、ストリートスーパースポーツとしてここまで歩んできたCBR-RR。モデル毎にその達成手法は異なるものの、その根底にある「誰もが操ることを最大限に満喫できる」ものをつくり、お客様に操る喜びを満喫していただきたいという想いは決して変わることはなかった。
当時のスーパースポーツのトレンドであった、攻撃的なスタイリングから距離を置き、初代CBR900RRを思わせる、凝縮フォルムでデビューした9代目CBR1000RRは、「誰もが操ることを最大限に満喫できる」という目標を、初代と同じ達成手法によって実現させようと考えた、意欲的な一台である。最新のテクノロジーをもってかたちにした、「CBR-RRの原点」とは。
「クラス最軽量・最コンパクト」を再び
宮城:スペック表を見てみると、2004年モデルの整備重量が208kg。この2008年モデルは199kg。だいぶ軽くなりましたね。
福永:2004年の7代目モデルは、当時として考えられることを全てやったので、やり残したこと、というのはありませんでした。だけど、公道をメインのステージとし、かつレースまで全てをカバーするバイクづくりというのが、まったく初めてだったこともあって、各部の設計マージンをレース寄りに、かなりしっかりと取っていたんです。反省というわけではありませんが、2006年モデルでは、実際に市街地からレースまでを走った結果得られたものを踏まえて大幅にシェイプアップしました。さらにこの9代目モデルでは、これまでに培ってきた技術を全部投入して、もう一度クラス最軽量・最コンパクトを目指そうじゃないかと。そういうふうに考えたわけですね。
長谷川:RVF750を8耐で負かせるような“クラス最軽量・最コンパクト”という考え方をもう一度、今の技術でやってみようと。その時点でも、操る喜びを味わってもらうには我々のつくるCBR1000RRが一番だと自負していました。でも、それさえももう一度、「本当に正しいのか?」と一から見直し、どこまで軽く、コンパクトにできるのかということをやってみたかった。想いだけじゃなく、手法という意味でもまさしく“原点回帰”と言っていい開発だったと思いますね。
軽量・コンパクト・マス集中をピュアに表現する
機能部品がそのまま「エクステリア」となるバイクにおいて、走りとデザインは不可分の要素だ。最新技術によるクラス最軽量・最コンパクトというハードウェアの目標は、当然スタイリングにも新たなチャレンジを求めることになる。

宮城:今回のCBRは「原点回帰」だと。この2008年モデルのスタイリングは、それまでの4年間の路線から少し変わって、ちょっと初代を思わせますよね。ここにも「原点回帰」というのがあったように思うのですが。
岸:おっしゃるとおりですね。当時は、よりエッジを立てて、より鋭さを出して……という、言ってみれば周囲をどれだけ「威嚇」できるのか、がスーパースポーツのスタイリングの常套手段となり、各社ともそれが“ユニフォーム”状態になりつつあったと感じていました。しかし、次のCBR1000RRをつくるときに、その流れに乗ることだけが本当にこのバイクを買ってくださるお客様のためになるのかなと疑問を持ちました。
宮城:当時のスーパースポーツはどれもサーキットから帰ってきたばかりのような雰囲気を漂わせていましたよね。通常のライディングウェアよりはレーシングスーツが似合うような。
岸:そこで、トレンドを単純にフォローして、「鋭さ」で勝負するのではなく、CBR1000RRが持っている本来の機能と、「軽量・コンパクト・マス集中」というCBR-RRの本質に正面から向き合い、それをピュアに造形に表現していくことで、独自性やデザインの新しい価値を生み出したいと考えたわけです。最新のレースシーンからのフィードバックとか、新しい表現のトライなどを取り入れながらも。
宮城:2000年モデルの話でも伺いましたが、確かに2008年モデルは初代に近いスタイリングの考え方ですね。僕は2004年モデルの鋭さを感じさせるものも好きでしたけど、初代のデザインも好きですね。こう、丸くて、愛嬌があって。
岸:そうですね。スタイリッシュというよりは、どこか親しみやすさや温かみがあるエモーショナルなデザイン。僕はあの固く引き締まった形を“ゲンコツみたいなデザイン”だと思っていましたけど、DREAM CB750 FOURの時代から続く、Hondaらしい造形なのかなと。このモデルではそんな「Hondaらしい機能に忠実なデザイン」を意識して、各部をつくりこんでいきました。結果的にスタイリングの特徴となったカウルのアウトレットのデザインにしても、ラジエターのラインにぴったり寄り添うことによって、排風効率の最大化を果たして、カウルのコンパクト化に貢献出来るカタチを模索した結果です。「ハンドリングをより軽快にするために、重量物はできるだけ車体のセンターに追い込みたい」というエンジニアからの要望が当初よりあったので、「それなら顔も引けるところまで引いてデザインは何とかまとめるから、空気抵抗値とハンドリングのバランスはよろしく」という “機能をピュアに表現する”というチャレンジの一環でもありましたね。
長谷川:「できるだけ内側に追い込みたい」と言ったはずの僕らが、デザインスケッチを見て「うーん、これはちょっとやりすぎなんじゃないか」って唸るくらいのものも中にはありましたね(笑)
岸:Hondaにとって「スーパースポーツの祖」とも言うべきCB92の「神社仏閣」と言われたスタイリングを研究したり、カラーリングに、和を感じさせる朱と黒というコンビネーションを取り入れたり……。CBR-RRの、Hondaの、日本の原点というところまで想いをはせてかたちをつくることができたのは、我々にとっても、その後に繋がるひとつの良い経験だったと思います。