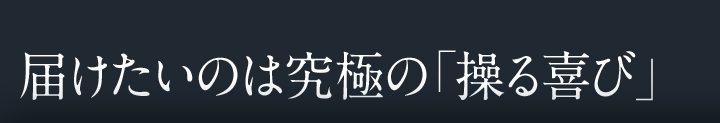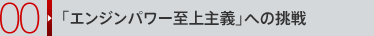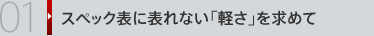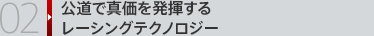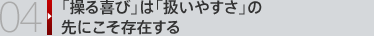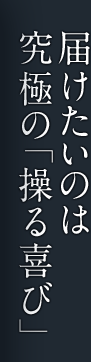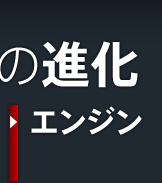当時のレースのレギュレーションに由来する750ccという限られた排気量の中で、あるいは「ライバルより少しでも大きく」と天井知らずに拡大していく排気量の中で、いかに高出力を絞り出すか。それこそがスーパースポーツにとっての定石だった時代があった。時は1990年代初頭。レースへのあこがれとともに、「フラッグシップ」を所有することへのあこがれが合致し、それを求めていた時代だったともいえる。そんな中、一台のバイクがHondaからデビューする。CBR900RR。
その心臓部は最高出力125馬力を発生させる893ccの直列4気筒エンジン。
レースのレギュレーションに合致する750ccでも、各メーカーの「フラッグシップ」と肩を並べる1000ccオーバーでもなく、誰よりもパワフルというわけでもない。ところが登場するなり、世界から驚きの声が上がる。これまでの常識では考えられないほどに軽く、驚くほどにコンパクトにつくられていたのだ──。
スタート地点は「打倒・RVF750」

元HRCワークスライダー 宮城 光(以下、宮城):「ずいぶんと思い切ったことをしたもんだな!」と思った当時のことは、よく覚えています。まず、こういった大排気量のフルカウルのスーパースポーツモデルといえば750ccのレーサーレプリカか、1000ccクラスのスポーツツアラーかという時代に、900ccというこれまであまりなじみのない排気量で登場したこと。そして、これまでの常識で考えれば本来1000ccクラスに匹敵するようなボリュームがあってしかるべきなのに、ホイールベースは600cc並みだし、フレームの隙間から向こう側が透けて見えるくらいあらゆるものがコンパクトにつくられていたし、カウリングもびっくりするくらい薄かった。全く新しいカテゴリーのバイクが登場した瞬間でしたね。
初代CBR900RR開発責任者 馬場忠雄(以下、馬場):まさに「軽くてコンパクトであること」こそが、このバイクの出発地点であり、存在意義でしたね。先行開発がスタートしたときの目標は、ずばり「鈴鹿8耐でHRCのワークスレーサー、RVF750に勝てるポテンシャルを持たせること」。
宮城:そう。もともとは750ccとして開発がスタートしたんですよね。しかし、「身内」であるRVF750をライバルとして設定し、それを負かすことを開発の目標に掲げるとは……すごいですね!
馬場:当時売られていたフルカウルのスポーツバイクは、誰もがバイクとの一体感を感じながら操ることができるかというと、そうじゃなかった。750ccクラスのレーサーレプリカも、1000ccクラスのフラッグシップスポーツも、年々パワフルに進化をしていっていたけれど、それに比例して車重も増えてしまっていたでしょう。もちろん、それを征服する楽しみというのもあったと思うけれど、そんな人はそう多くはなかった。
宮城:パワーもある。立派な排気量がある。これもライダーにとって、立派な価値ではある。しかし、走らせるときに体力も使うようになったし、扱うのも難しくなった……。確かに、これを乗りこなせるライダーは一握りですね。馬場さんとしては、その流れをなんとかして変えていきたかったわけですね。
馬場:そうですね。そのために目指したのが「クラス最軽量・最コンパクト」。他二輪メーカーの750ccはもちろんのこと、身内のRVFも凌駕できるようなものになれば、誰もが楽しめる、まったく新しいスポーツバイクができるんじゃないかと考えたわけ。それで、ずっと水面下で進めてきた軽量・コンパクトな直列4気筒の研究を活かした、新しいスーパースポーツの開発がスタートしたんです。そしてモデルをイメージするフレーズとして「操る事を最大限に満足させる」と定め各機能、性能を創り上げていった訳です。なお、このフレーズを英訳する際に適切なワードが無く、議論の末に「トータルコントロール」となったいきさつがあります。
既成の枠組みに捉われない、
全く新しいスポーツバイクの誕生
クラス最軽量・最コンパクトを実現させ、「鈴鹿8 耐」でHRCの走らせるワークス仕様のRVF750に勝てるだけのポテンシャルを持ち、かつ、誰もがバイクとの一体感を感じながら操ることのできるバイクをつくる──。そうした思いから始まった「CBR-RR」の先行検討段階だったが、やがて、その思いの根底の部分をさらに研ぎすましたコンセプトをかたちにするプロジェクトへと移り変わってゆく。

馬場:細かいところは省きますが、同じつくるならばわざわざHondaのラインアップの中で競合させるよりは、レーサーレプリカなら750ccだとか、フラッグシップスポーツならば1000ccだとか、そういったカテゴリーに縛られない、新しいコンセプトのものをつくろうということになったんです。幸い、多くの人に操る喜びを感じてもらうための750というパッケージングは、ディメンションから重心位置から、すべてできあがっている。それじゃあ、それをベースにしてどんなことをしたら、既成の枠組みを超えて、本当に操る喜びを感じてもらえるバイクができるのか?ということを考えていったわけです。
宮城:最初からあの900という数字があったわけではないと。しかし、750という枠組みを超えるにしても、上を見ればキリがないですよね?事実、そうやってパワフルに、同時に重くなっていったのが当時のスーパースポーツだったわけですから。
馬場:まず、ターゲットをドイツのアウトバーンに定めました。ライダーがフラッグシップモデルで求めている「速さ」はどのくらいなのだろう、ということを検討したわけですね。ご存知の通り、アウトバーンには速度無制限の区間があるわけですけど、相当の飛ばし屋さんならともかく、普通は時速160kmくらいがアベレージ。だったらそのスピードまで、当時の1000ccクラスと同じくらいのタイムで加速できるようにしましょう、と。これはパワーウエイトレシオで決まってくるので、そこから何馬力出せばいいのかということも、どのくらいの排気量があればいいのかということもわかります。あくまでも、750ccのパッケージングを維持した上でね。そうして導きだしたのが、893ccという排気量だった。
宮城:しかし、これは時代の流れとは正反対を向いていましたよね。「産みの苦しみ」は相当なものだったんじゃないかと予想できますが。
馬場:当時は「エンジンパワー至上主義」の時代でしたからね。エンジンパワー、ナンバーワン。最高速、ナンバーワン。排気量、ナンバーワン。そういうものが売りやすい。乗り味は数字じゃわかりませんから、説得にはずいぶん時間がかかりました。でも、日本にヨーロッパの現地法人のライダーを呼んで乗らせたら、この楽しさはすぐにわかってもらえた。それで、なんとか製品化にこぎつけることができたんです。ヨーロッパでは「900」という数字はあまり前面に出したくないということで、「FireBlade」という名前で売り出されることにはなったけれどね。