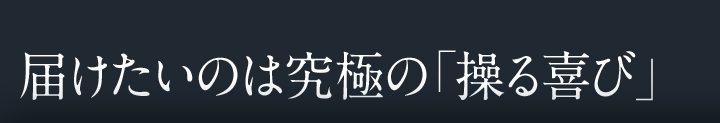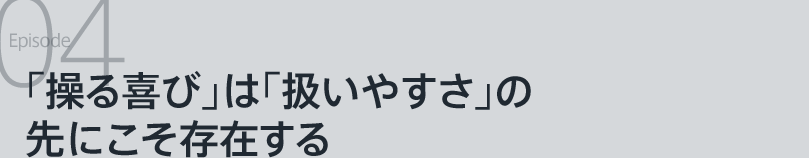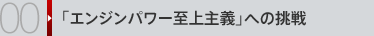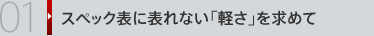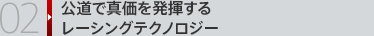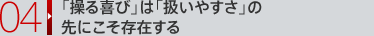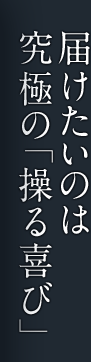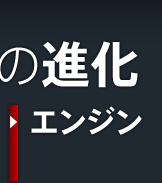最高出力や排気量が絶対要件だったスーパースポーツのあり方を変えた初代CBR900RR。公道で操ることを楽しむということを完成させた2000年のCBR900RR(CBR929RR)。それらの考え方を基に、ユニットプロリンクをはじめとした最新のレーシングテクノロジーを投入して完成させた2004年のCBR1000RR。「最軽量・最コンパクト」という初代CBR900RRでめざしたものを最新の技術でかたちにした2008年モデルのCBR1000RR……。そして初代誕生から20年となる2012年、12代目CBR1000RRがデビューした。時代は大きく変わり、様々なメーカーから、それぞれの解釈によるスーパースポーツが登場した。その中でパイオニアたる「CBR-RR」だけがライダーに提供できるものとは、何なのか。
いま、「CBR-RR」だけがライダーに提供できるもの
宮城:20年前にHondaのCBR900RRが切りひらいたこのジャンルは、今や日本国内の二輪4メーカーにとどまらず、海外のメーカーまで参入して花盛りとも言える状況にありますよね。雑誌の仕事で試乗をする機会も多くありますけど、それぞれのバイクに、それぞれの魅力があります。ライダーは、その中から好きなモデルを選んで乗れるわけです。ずっとCBR-RRというバイクに何かしらのかたちで関わってきた立場として、今、CBR-RRだけがライダーに提供できるものというのに興味があるのですが。
12代目CBR1000RR 開発責任者 石川譲(以下、石川):ひとことで言うなら、初代から20年にわたって培ってきた「扱いやすさ」なんですよね。技術はどんどん進化しているけれど、これは一朝一夕に実現できるものではありません。「扱いやすさ」という言葉は、額面通りに受け取れば「Hondaのバイクは誰でも乗れる」「Hondaのバイクは簡単すぎて面白くない」というようにも聞こえるかもしれませんが、扱いやすくなければ、そもそも楽しめないというのが我々の持論です。
宮城:フューエルマネジメントに手を入れてアクセルの開け始めのコントロール性を向上させたり、高回転域ではスロットル操作に対して過敏すぎない出力特性にしたり……本当に細かいところにまで手を入れていますよね。
石川:ドキドキしながら探るようにスロットルを開けていくんじゃなくて、右手とリアタイヤの間に何も存在しない……まさしく「直結」しているかのような感覚を味わってほしいんです。スペック表をどんなに眺めてもらっても、残念ながらその乗り味は伝わらないと思います。でも、エンジン、フレーム、サスペンション、空力……バイクがバイクとして成立するために必要な構成要素を徹底的に磨き上げることで、他のモデルでは味わえない楽しさを味わっていただけるということは、自信を持って言うことができます。

宮城:そうですね。減衰力の発生のさせ方を変えた、新しい構造のサスペンションもそうですし、空力を利用してリフトを抑えるという仕組みもそう。今回は2000年モデルで17インチになって以来ずっと続いていた3本スポークのデザインから大きく変わって、ホイールでも新しいことにチャレンジしていますよね。
吉井:ホイールも歴代モデルでずっとこだわってきた「どこまで乗り味を軽くできるか?」ということに繋がっています。支持する箇所を増やすことで、旋回中に生じるグリップの変化を極限まで抑えようというのがその意図ですね。
12代目CBR1000RR デザイナー 徳村大輔(以下、徳村):デザインチームも、以前からずっとホイールのデザインを変えたいということは言っていたんです。3本スポークは、メリットがあるからこそずっと使われてきました。でも、もっと素直に軽さを伝えられるデザイン表現をしないといけないと。5本、7本、9本と試す中で、見た目にも軽く、しかも乗ってみて軽快感があるというのが、今回の12本スポークホイールの造形だったんです。
宮城:なるほど。全体のスタイリングについては08モデルに対して、またシャープな印象が強くなったような気がしますが。
徳村:そうですね。しかし基本的には08モデルで表現した「軽量・コンパクト・マス集中」への徹底的なこだわりはそのままに、スポーツモーターサイクルとしてのダイナミックさをより素直に伝えられる造形を目指しました。先ほどのホイールのデザイン同様、軽いもの、速いものと言ったスーパースポーツとしての本質を、見る人が直感的に理解出来るデザインの要素を組み入れています。
電子制御の時代に見つめ直した
「バイクでスポーツすること」
Hondaには「レースは走る実験室」という言葉がある。レースのように、ものごとの進むスピードが早く、信頼性という面でも厳しい過酷な状況下で、ライダーの高い要求に応えられるほどの技術であれば、一般のライダーにとっても恩恵のあるものがそこから生まれてくる、という意味だ。事実、Hondaはレースの世界から様々なテクノロジーを市販車へとフィードバックさせてきた。

宮城:MotoGPで、Hondaは本当に素晴らしい電子制御式トラクションコントロールを完成させましたよね。これは、ASIMOで培われた姿勢制御技術までを投入して「どうしたらライダーの負担を軽減できるか」というところを徹底的に追求した、実にHondaらしいシステムだと思います。CBR1000RRの「扱いやすさ」を、これで実現しよう……という考え方は、ないものなのでしょうか。
吉井:もちろん、あれはライダーを主役に考えるというところに立脚した、すばらしいシステムだと思うし、将来的にCBR-RRというバイクにフィードバックされることがあれば、その考えは変わることはないでしょうね。絶対に。ただ、今このモデルで我々が提案したいこと、お客様に楽しんでいただきたい「スポーツ」の定義が何なのか、ということなんですよ。欧州仕様で170馬力以上あるようなパフォーマンスを持ちながら、自分とバイクが1対1で意志を通わせられて、なおかつ、きちんと操ることができる。これができるだけの扱いやすさ、余裕をつくるということに時間をかけたし、誰もが、それぞれのレベルでバイクを操ることを最大限に楽しめる。それが、我々が今回このモデルでこだわったことです。
宮城:スーパースポーツに乗ってみたい、でも自分にできるだろうか……と躊躇する人に対しては、ABSが大きく間口を広げましたよね。スロットルを開けていくという領域は緻密に仕上げていくことで、十分にコントローラブル、そしてビギナーからエキスパートまで、誰もが楽しめるものにできたと。電子デバイスの力を借りることなく、できるところまでやりきったということですね。
吉井:たとえば、CBR1000RRというバイクで一日走り回って、家に帰ってきたときに「今日はめいっぱい体を動かして、スポーツをして気持ちよかったな!」という気持ちだけを持ってもらえたら、僕らとしては本当に言うことはありません。そこに「エンジンがどうだった」とか「CBRがどうだった」みたいな感覚を、できるだけ入り込ませたくない。そう考えると、現時点ではバイクの基本構成を磨き上げることで実現させるのが一番いいというのが、我々の考えです。
福永:もちろん、トラクションコントロールなり、エンジンマッピングの変更なり、そういった電子デバイスがあったほうがいいという人はいると思います。使うとか、使わないとかに関わらず、そういうものを持っている、ということに価値があるかもしれません。でも、人とバイクの間に何も介在させずに操ることを最大限に楽しんでいただくということ……この楽しさは何にも代え難い。そのためにできることは文字通り全部、このモデルでやりきりました。20年間、時代の要請に応じて色々なアプローチを試みてきました。その中でも、バイクという乗り物の根幹にいちばん近いところにあるものを究極まで磨き上げて実現させた「いい汗をかけるスポーツ」。2012年モデルのCBR1000RRはひとつの完成形なんです。