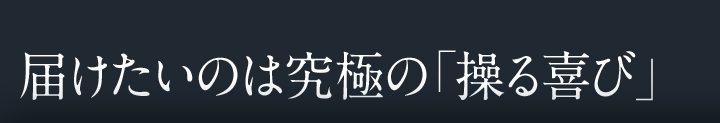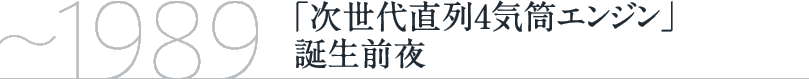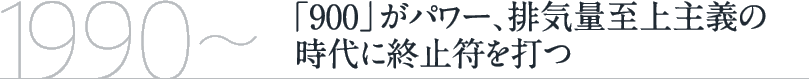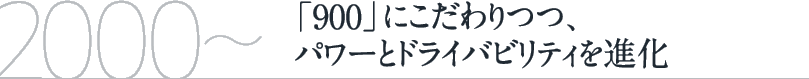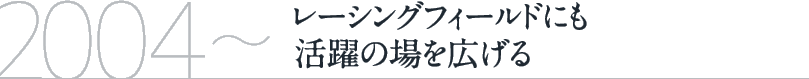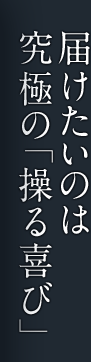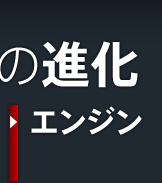1980年代後半。Hondaはレースシーンで活躍するV型4気筒エンジンを多様なモデルに展開していたが、同時に、これまで培ってきた技術を活かした、新たなエンジンの可能性を探っていた。その取り組みのひとつが、サイドカムチェーン方式を採用した、新世代のスーパースポーツ用・1000ccの直列4気筒エンジンの研究であった。カムシャフトを片側から駆動させるこの方式は、中央から駆動させる従来方式と比べて、発生する「ねじれ」の力が大きくなり、耐久性の面でクリアしなければならない点が多くある一方で、エンジンの全幅をコンパクトに抑えることが可能である。
大きく、堂々とはしているが、「自分の体の延長線にあるかのように自由に扱える」とは言い難かった、当時のリッタークラスのスポーツバイクにこれを搭載することで、車体設計の自由度が高く、トータルのパッケージとしての優れたパフォーマンスに寄与できる「直列4気筒」というエンジン形式の可能性を追求しようと考えたのである。
このエンジンの持つ可能性は、レースにおいても活きてくるのではないか。「V4エンジン全盛」とも言える今だからこそ、直列4気筒の可能性に注目したい……そう考えたのが、初代CBR900RRの開発責任者、馬場忠雄率いるチームであった。目標は高く「打倒V4」と定め、1000ccエンジンの基本設計を活かした、ボア×ストローク70mm×48.6mmの750cc・直列4気筒エンジンを試作。中回転域から高回転域までの優れたピックアップと加速特性を持つこのエンジンは、当時の750cc V型4気筒エンジンよりも軽量・コンパクトに仕上がっており、軽量で高剛性の車体と組み合わせることで、自由自在な走りを可能としていた。
その後、プロジェクトは、ヨーロッパ、アメリカに向けた新コンセプトのスーパースポーツの開発へと舵を切る。レースユースではないのだから、レギュレーションに則した750ccに固執することはない。大排気量エンジンならではの、太いトルクは欲しい。しかし、無闇に排気量を拡大したのでは、重く、大きくなっていた他のスーパースポーツと同じ轍を踏む……。そこで、開発陣は車体重量・車体寸法を先行検討段階にあった排気量750ccのCBR-RRと同等に抑えることを至上課題とした上で、どこまで排気量を拡大できるのかの検討を始めた。結果、多くのライダーが本当に必要としているのは160km/hまでの加速性能であることを探り当て、1000ccクラスのスーパースポーツと同等の0-1000m加速ができることを目標に設定。こうして導き出された893cc・124PSというスペックは、750ccエンジンの基本設計を踏襲しながら、ストロークを9.4mm延長することで実現させた。
数値として見れば“中途半端”だが、これまでのスーパースポーツにはない「操る喜び」を実現する「900」の登場によって、「カタログ上の排気量・エンジン出力がスーパースポーツとしての優劣を決める」時代は終わりを告げた。その後、ライバルが次々に1000ccのエンジンを搭載していく中、CBRは900ccエンジンにこだわり続けた。徒にハイパワーを求めるよりも、トータルのパッケージングで、ライダーに操る喜びを提供できるものを。この考え方は後にモデルチェンジする2000年モデル、2002年モデルのエンジンにも受け継がれていくこととなる。



初代CBR900RRの登場から8年。動力性能に優れた1000ccクラスのエンジンを搭載したライバルたちが登場してくる中で、Hondaはそれを凌駕する走りの楽しさを実現するため、さらなるハイパワー化に取り組んだ。しかしそこでも、開発陣は「900と呼べる排気量」にこだわった。単に名称に固執したわけではない。「レースのレギュレーションに囚われず、一般のライダーが公道で楽しめるバイクをめざす」「エンジン単体での安易な出力競争に走らない」。「900」という名称は、そんな「CBR-RRらしさ」を象徴するものだったからである。
では、その中でどこまで排気量を拡大することができるのか。ある意味で、これを決めるのは容易であった。意のままにコントロールできることを目的として、車体のディメンションが既に決まっていたためだ。エンジン全幅や全長を拡大できない以上、シリンダーのボアも自ずとそこから導き出される。ボア間肉厚を、当時の限界であった7mmまで詰めることで71mmから74mmまでボアを拡大。ここから929ccという排気量を得た。
この排気量からレースマシンのように最高出力だけを達成することは容易だが、公道において多用する低速域での扱い易さを犠牲にせず目標最高出力148PSを引き出せる見込みは非常に薄かった。そこで、低速域と高速域の出力向上を両立させる手法として様々なデバイスを検討する中で新開発したのがエキゾーストシステムとエアクリーナーに組み込まれた「H-VIX(ホンダ・バリアブル・インテーク/エキゾースト)」である。
これは、エキゾーストパイプの1番と2番、3番と4番を連結し、低回転域でのトルクを稼ぎやすい180度集合と、1番と4番、2番と3番を連結し、高回転域での出力を稼ぎやすい360度集合を、サーボモーターによって駆動される排気デバイスによって切り替えることで、高回転での痛快な走りと、低速での扱い易さを両立するという世界初のシステムである。3000回転までは180度集合、以降7000回転までは360度集合となり、それ以上では360度集合、かつ180度で連通される。また、この排気デバイスは超軽量チタニウムを採用し、軽量化を達成しながらレスポンス向上に寄与している。
この排気デバイスと、エアクリーナーに流入する空気の量を調節する吸気デバイスを協調制御することで、回転数に応じて常に最適な出力特性を実現。「900」という排気量の中で、高回転域での出力向上のみならず、公道で多用する低回転域でのドライバビリティ向上をも同時に達成することに成功した。
さらに、2年後にはそれまで7mmが限界とされていたボア間肉厚を6mmまで縮小し、ボアを74mmから75mmに拡大して排気量を954ccとしつつも、往復運動部重量を前モデル比4%の軽量化を実施。誰もが意のままに操ることのできるドライバビリティと、動力性能をさらに進化させた。
「最高速は290km/hまで出るけれど、やさしく走るのがCBRだ」。そんな言葉も、この5代目、6代目CBR900RR(CBR929RR, CBR954RR)のエンジン開発ではキーワードになっていた。そのドライバビリティの優秀性は、公道を舞台とし、世界でも最も過酷なレースの一つに数えられるマン島TTレースでCBR900RRを走らせたライダーやマーシャルたちの言葉に表れている。「マン島で、こんなに乗りやすいと思えたスーパースポーツは初めてだ」。

レギュレーションで、1000ccまでの4気筒エンジンが使用可能になったこともあり、ワールドスーパーバイク選手権を戦うレーシングマシンのベース車は従来のVTR1000 SP-1/SP-2からCBR1000RRへとスイッチすることとなった。エンジンは、ボアとシリンダーピッチはそのままに、ストロークを54mmから56.5mmへと延長したことで総排気量は998ccとなり、最高出力は172PSまで向上。先代モデル対比+24PSと、スペック上は華やかではあるが、「パワーが出ていればよい」という考えは、1992年に初代CBR900RRが生まれた時より、元来なかった。求めたのは、サーキットと公道、その双方で「結果」を残すことができるようにすること。つまり、懐の深い乗り味を実現する車体設計に貢献できるエンジンとすることである。
フレーム設計の自由度を向上させ、サーキットにおける戦闘力向上と、公道における軽快な走りを実現するユニットプロリンク採用に必要なスペースを稼ぎ出すための設計に着手。
クランクシャフト、メインシャフト、カウンターシャフトという3軸を三角形に配置しなおすことでクランクシャフトとスイングアームのピボットの距離を21.5mm短縮。スイングアームの全長を34mm延長させ、ハイパワーを安心して楽しめるディメンションをつくりあげた。
また、レースという極限状態で信頼されるエンジンにすることは、公道でも安心して長く楽しんでいただくことにもつながる。シリンダーブロックの剛性を高めるためにシリンダーボア上部とブロックのアウターウォール間にブリッジを一体成形したセミクローズドデッキシリンダーブロックを用いることで、冷却性能を損なうことなく、耐久性と信頼性の向上を実現。新設計のアルミ鍛造ピストンやナットレスコンロッドの採用と併せて、トータルでの完成度を高めた。
2008年にはボアを75mmから76mmへと拡大し、ストロークを56.5mmから55.1mmへとショートストローク化した999ccのエンジンへと進化。出力特性を大幅に向上させるとともに、新設計のエンジンケース、シリンダーの別体化や細部に至る材質の見直しによりエンジン単体で2.5kgもの軽量化も達成している。