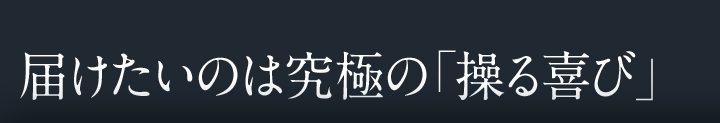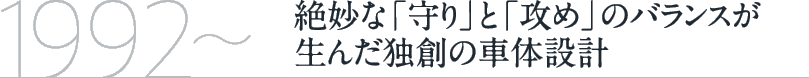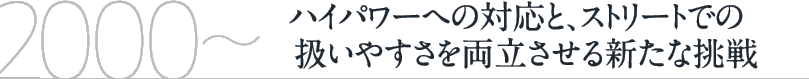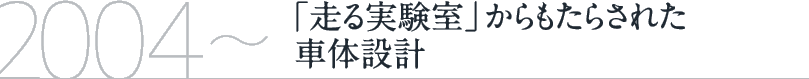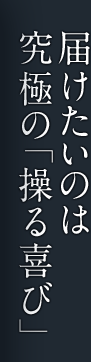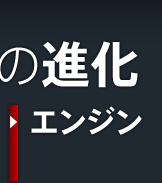世界の「スーパースポーツ」のあり方を変えた、エポックメイキングな一台である初代CBR900RRの車体は、「守り」の部分と「攻め」の部分とを絶妙に組み合わせてかたちづくられている。その判断基準は、「一体何がライダーの“操る喜び”のためにベストなのか。」というその一点に尽きる。
「守り」の部分の代表例は、開発陣の間で「ダブルアップサイドダウン」と呼ばれていたフロントフォーク。「ダブルアップサイドダウン」とは、「倒立の倒立」といった意味である。フロントまわりの剛性を向上させられる倒立フォークは、このバイクがデビューした1992年の時点でレーシングマシンでは多くの採用実績があり、市販車にも広まりつつあった。すでにさほど珍しいものではなかったが、なぜ倒立させたフロントフォークをもう一度倒立させようと考えたのか?その理由は、剛性という面では大きなメリットがあるものの、さまざまな路面状況が考えられる公道でのライディングを主な舞台として考えたときの作動性には、改善の余地があったところにある。そこで正立フォークの作動性と、倒立フォークの高剛性を両立させるため、倒立させたアウターチューブの外径にも迫るような45Φという極太のものを選択したというわけである。
ここに組み合わせられるホイールは、先行検討段階にあった、750cc CBR-RRのディメンションによる軽快なハンドリングを維持させながら、排気量アップでのハイパワー化によって抜けやすくなったフロント荷重を補い、さらにウィリー状態から接地したときのクッション性も確保するという考えに基づいた16インチホイール。タイヤの外径を確保しつつ、タイヤハイトを稼ぐにはどうするべきか……という考えに則って選択されたものだが、ここにはHondaのみならず、タイヤメーカーをも巻き込んだ「攻め」のエピソードが存在する。
なお、90年代初め迄の欧州ならびに北米でのマーケットに於ける日本車の「足まわり」のイメージは決して良いものではなく、純正装着のフロントフォークやタイヤなど「とりあえず付いている」といった認識も根強かった。しかし前述の通り開発陣が足まわりに込めた想いは熱く、フロントフォークはもちろん、CBR900RRにマッチした、ブリヂストン製の純正タイヤが最適であると確信していた。しかし当時の欧州ではブリヂストンのリプレイス用タイヤの供給体制は現在ほど整っていなかったため、CBR900RRと歩調を合わせ、販売力を強化していただいた。
排気量を拡大させながらもスーパースポーツとしてのディメンションを保つために、大きく湾曲させたツインスパーフレームもまた、部品メーカーの協力なくしては実現しえなかったものだ。時間をかけて製作する試作においては何とか曲げられたものの、大量生産となると更に困難を極めた。一時は量産が危ぶまれたものの、製作所の担当者が休日返上で各地を巡り、ようやくこの湾曲したフレームを加工できる部品メーカーの協力を得て、高品質な量産が可能になったのだ。
CBR900RRという全く新しいコンセプトのスーパースポーツは、社内外の多くの人々の情熱によって世界に提案することができた当時唯一無二のモーターサイクルだったのである。

さらなる「操る喜び」のためにハイパワー化したエンジンに合わせ、フレームも大幅な進化を遂げたのが、この2000年モデルである。ただし、その手法は従来のセオリーであった「高剛性化」によるものではない。むしろ、「従来の高剛性のみに頼らず、ハイパワーに対応」しようという、これまでと全く異なるアプローチによるものであった。
フレームの剛性を高めれば、確かに強大な駆動力を安定して受け止めることのできる車体にはなる。一方で、外乱に対しての挙動が過敏になったり、フレーム自体の重量が増加してしまったりといった、「公道でスポーツ走行を楽しむためのバイク」にとって、看過できない問題をはらむことにも繋がりかねない。そこで開発陣が白羽の矢を立てたのが、1996年にデビューしたVTR1000Fでも採用されていた「ピボットレスフレーム」であった。スイングアームをクランクケース後端に直接取り付けるこの車体構造は、駆動力や後輪から伝わる外乱を、メインのフレームではなく質量の大きなエンジンで受け止めることによって、「エンジンにフレームとしての役割の一部を担わせる」ことが可能である。フレーム本体の剛性を各部最適に調整しながら、かつ、重量増を伴うことなく、ハイパワーに対応させられるのである。
「フレームの一部」として取り込まれたエンジンは、シリンダーヘッド付近にエンジンハンガーを、そしてクランクケース後端にはスイングアームピボットを新たに取り付けられることになった。むろん、それは技術的には何ら難しいものではない。しかし、イメージの上ではがっしりとしていて、歪んだり、よじれたりしない「剛体」のようなエンジンも、シリンダーヘッド付近でフレームと締結されては、フレームから伝わる衝撃を無視することはできない。
微細な歪みによって、フリクションが増大しないか、ヘッドガスケットからの「吹き抜け」が起こらないか……など、エンジン性能、信頼性などの面でクリアしなくてはならないハードルは多かったが、ピストンをはじめとしたエンジンパーツの寸法を徹底的に管理し、これらの問題をクリア。見事、エンジンをフレームの一部として機能させ、ハイパワーと軽量化、公道において重要な軽快感ある乗り味を両立させることができた。
こうした取り組みに加え、各部の徹底的なブラッシュアップによって1998年モデルから比べてさらに10kg減。2年後にデビューした、2002年モデルでは、25cc排気量アップし、さらに2kgの軽量化を達成している。
こうした軽量化は、図面上だけで実現できるわけではない。部品メーカーや、浜松製作所の技術が不可欠である。溶接の順番をどのようにするか?できあがったパーツをどのような順番で組み付けるか?こうした違いによっても、重量は少しずつ異なり、完成車としての重量に影響してくるためである。
CBR-RRにおいては、「数値の上ではわずかに思えるこの軽量化も、スーパースポーツとしてのパフォーマンスや、操る喜びに確実に繋がる」という姿勢を一貫して貫き続けてきたことにより、製作所や部品メーカーからも全面的な協力を得られ、乾いた雑巾を絞るかのような努力の結果、軽量化が実現できた。
「ハイパワー化への対応と、公道における扱いやすさの両立」という、難しい課題に挑んだ2000年モデルのCBR900RR(CBR929RR)の車体設計。それは、「車体」のみならず、このバイクづくりに関わるあらゆる人々の創造性によって実現されたものなのである。



電子制御式ステアリングダンパー・HESD
四輪車、二輪車レースの頂点にそれぞれ位置するF1マシンとMotoGPマシン。その違いは何か。それは前者が間違いなく「クルマの頂点」ではありつつも、運転操作から運動特性まで一般の乗用車とは全く異なる存在であるのに対し、後者は基本的に市販の二輪車の延長線上にあるということだ。
公道からサーキットまでをカバーする7代目CBR1000RRを開発するにあたりMotoGPマシンのRC211Vを「手本」としたのは、世界最高峰のモータースポーツにおいてパフォーマンスを発揮している車体構造で実現されていたからである。
フレームは、CBR-RRの伝統と言えるツインチューブフレームで、革新的ではないものの、MotoGPマシンと同様、いかに重量物であるエンジンや路面からの外乱を受け止め、逃がすかという、理想的な「しなり」を求めて設計が行われた。コンピューターがいくら発達しても、これは計算だけで求められるものではない。試作をしてはテストコースで走り込みを行い、現場で「切り貼り」を繰り返し、ときには原型をとどめないようなフレームになって再び研究所に戻ってくる……。こうした地道な試行錯誤を経て、レースまでを見据えたハイパワーを確実に受け止める剛性と、公道における軽快なハンドリングを高次元で両立させる車体を具現化していった。
新しいリアサスペンションの構造であるユニットプロリンクをRC211Vからフィードバックするにあたり、ライダーに路面の状況やタイヤの動きなど、軽快に操り、走るために必要な情報だけを伝えることを目標に開発が進められた。路面からの外乱など、走る上では「ノイズ」でしかない情報を足まわりで吸収し、フレームに伝えないようにすることでフレーム剛性の設定自由度を拡め、誰もがより的確なライディングをできるようにしたのである。
このモデルから採用された電子制御式ステアリングダンパー「HESD」も同様に、ハンドリングをより安定し軽快な操作を行えるよう路面からの外乱や振動を低減するなど、不要な車両の挙動を抑え、どんな状況でもより安定したライディングを可能にすることを目的に開発。速度に応じた緻密な電子制御を行うことで、ハンドリングの軽快感を残したい低速時には、「装着していることを気づかせない」ほどの完成度まで高めた。
「レースは走る実験室」というHondaのモータースポーツ活動のポリシーをこれ以上ない形で反映させたのが、7代目CBR1000RRの車体設計なのである。