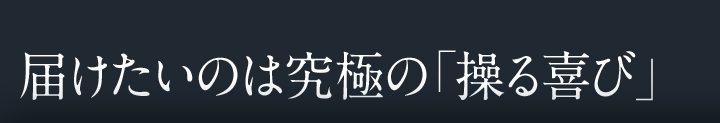ユーザーに育てられるバイク

こうして誕生したCBR900RRは、作り手の心配をよそに、多くのライダーから受け入れられ、多くのライダーがバイクでスポーツすることの楽しさを満喫した。その結果、バイクが排気量で決まるわけではないことを当たり前に認識してもらえるようになり、発売当初は「900」という数字を嫌ったヨーロッパ仕様車にも、改めて「CBR900RR」という名称を冠することになった。
元々CBR900RRは、「レーサーレプリカ」として誕生したわけではない。当時のTT-F1クラスやワールドスーパーバイクのレギュレーションには則していなかったし、「サーキット最速」のための造りこみがされているわけでもなかった。ところが、ふたをあけてみれば、「FireBlade」は、世界中のレースで次々に勝利を挙げていく。
宮城:RC30とは違う道を歩んだことにも象徴されるように、これは「レーサーレプリカ」ではないわけですよね?
馬場:そう。レーサーレプリカではない。
宮城:僕もアメリカで馬場さんもよくご存知のエリオンレーシングというチームでレースをしていたときに、このCBR900RRに乗りました。オープンクラスと呼ばれるクラスのマシンですね。これがすばらしく速かった。デイトナのバンクで、スーパーバイクのワークスマシンに乗るライダーを引き離すことができるくらいでした。各国のレースでも活躍していたように思いますが、これについてはどう思われますか?これでもなお、「レーサーレプリカ」ではないわけですよね?
馬場:そう。あくまでも、ライダーが公道で乗ってスポーツできるバイクです。それでも、「レースで活躍できた」というのなら、それはユーザーがチューナーまでを巻き込んで「CBR900RRを育ててくれた」から、でしょうね。我々がしたことは、使い方を限定するのではなく、ユーザーに任せることのできるクルマづくりだけ。ツーリングに使う人もいるでしょうし、ワインディングを楽しむ人もいるかもしれない。そうなれば、当然レースに使う人もいると。
宮城:ユーザーが「CBR900RRを育ててくれた」、いい言葉ですね。そういえばCBRが変えたことのひとつに「作り手の顔が見える」ということがあると思うんですよ。馬場さん自らがCBR-RRオーナーの前に出て行き、積極的にコミュニケーションを取っていましたよね。
馬場:そうですね。ユーザーが考える「操る喜び」が何なのかを、実際に会って確かめたかった。ヨーロッパやアメリカに出かけていって、どのメーカーのどのバイクのオーナーかということは問わず、あらゆるバイクユーザーを呼んで、ざっくばらんに話をした。そこで「ミスター馬場、俺のR1(ヤマハ)をもっと乗りやすくするにはどうしたらいいんだ」というような相談にもきちんと答えました。……まあ、「それならCBRに乗り換えた方がいいよ」という話は当然しましたが(笑)。そうしてユーザーが本当に求めているものを見極めようとしたんです。
CBR-RRのコンセプトは、
言葉を越えて世界へ伝わった
まるで、自分の手足であるかのように走らせられるスーパースポーツがある──。CBR900RRは、世界中のライダーが「スーパースポーツ」というジャンルに対して抱いていた「速いけれど扱いにくい」という認識を大きく変え、世界中の多くのライダーに対して、「操る喜び」を広げていくこととなった。

宮城:馬場さんがこのCBR900RRでやったことというのは、文字通りスーパースポーツのあり方を変えたことだと思います。このバイクに乗ったことで、新しいバイクの楽しみ方に出会ったお客様が多くいらっしゃると思うんですよ。
馬場:このバイクで実現したかったのは、あくまでも、自分で体を動かしてスポーツをしたときの「いい汗をかいたな!」という、あの感覚なんですよ。冷や汗をかいて、くたくたに疲れてしまうんじゃなくて、ツーリングから帰って、ライディングウェアを脱いで、シャワーを浴びて、ソファーに座ってお酒を飲みながら「ああ、今日は充実した一日だったな」って振り返ることができるような、心地よい疲労感を味わえるバイクをつくりたかった。それが、「操ることを最大限に満足させる」というコンセプトの背景にあるものなんですよね。
宮城:なるほどね。それまでのパワフルだけれど、重く大きなスーパースポーツでは決して味わえない感覚でしたね。
馬場:これは余談になりますが、英語で「冷や汗」って「コールドスウェット」っていうんです。文字通り、冷たい汗。大体、どこの国に行ってもこの言い回しで通じる。ところが、僕らがイメージしている「いい汗」って、英語でもドイツ語でもイタリア語でもフランス語でも、これをそのまま伝えられる言葉がない。でも、たぶん我々がユーザーの皆さんに味わっていただきたかったものは、そんな言葉での表現を越えてきちんと伝わったものと思っています。これがバイクでスポーツをして「いい汗をかく」っていう感覚なんだってことはね。