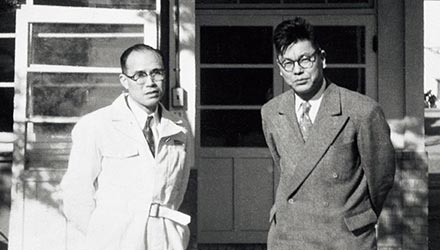耕うん機の成功で、欧州各国にパワープロダクツ事業の基盤を築く

フランスの畑と庭園はヨーロッパにおけるホンダパワープロダクツ事業発祥の地である
 コンパクトなサイズと取り扱いの良さで欧州各国で大ヒットとなったF25
コンパクトなサイズと取り扱いの良さで欧州各国で大ヒットとなったF25
欧州は二輪車の本場だが、耕うん機の本場も欧州である。ホンダは、1963年3月、パリ国際農機具サロンに耕うん機F190・F60を初出展する。狭い土地でも小回りの利く機動力、光沢があり耐久性の高いクロームメッキ仕上げの回転式ハンドル、夜間用のヘッドライト、優れたデザインが高く評価された。さらに通称「ナタヅメ」と呼ばれるナタの形をしたホンダ独自の回転刃は、南フランスの下枝の多いブドウ園、堅い岩盤の上にある農地を耕すのに最適だった。ホンダの耕うん機はたちまち話題となり、販売代理店の申し込みが殺到した。1964年にはホンダ・フランス(FH)を設立。現地での綿密な市場調査によって、郊外に畑を持つ市民が使えるF25・F28を1969年に投入した。クルマに積めるコンパクトサイズと取り扱いの良さで大ヒットとなり、ベルギー・旧西ドイツ・イギリス・オランダ・スペイン・フィンランドなど欧州各国に広がっていった。欧州における汎用エンジンの貢献を藤澤武夫(当時の副社長)はこう述べている。
「欧州で四輪車をスタートする足掛かりは二輪車ではない、農機具であったということを言いたい。農機具において地盤をとったということが、フランスにおいての日本というイメージを猛烈に起こした。(中略)二輪車も農機具関係、ジェネレーターというのをひっくるめて、あらゆるものが全部ユニークなもの。物真似でないからこそ値打ちがある。物真似でないから外国が高く評価しているという状態で、今、ホンダがあるということを申し上げられるわけであります」
この成功こそが欧州におけるホンダの礎となったのである。
欧米の芝刈機市場に着目し、ホンダの新領域を開拓する
1970年代半ば、世界のパワープロダクツ製品市場は年間約2,000万台で、そのうち芝刈機市場は約850万台を占めており、大きなポテンシャルのあるマーケットだった。1975年、H型エンジンに続くMEエンジン*5の研究が一段落した開発チームに芝刈機の開発命令が下される。当時の日本に芝生のある家庭は少ない。開発チームのメンバーは、芝のない国・日本のホンダが、芝のある国の芝刈機メーカーが林立する世界になぜ出ていくのかと戸惑いつつ、イギリス・旧西ドイツ・フランス・スイス・アメリカなど芝刈機市場の国へ飛んだ。
欧米各地を回ったメンバーはホンダブランドの力に驚かされた。農機具販売店へ行くと、ホンダが来たということでどこでも歓迎され、有益な調査を行うことができた。二輪車・四輪車で築いたホンダブランドを決して汚すわけにはいかない、10年、20年と、満足して使っていただく芝刈機をつくらなければと決意したのである。
他社製品との差別化を図るために、静音性・安全性・操作性にフォーカスした。そして、音が静かで圧倒的な始動性を誇るバーチカルエンジンを搭載し、世界で初めてのBBC(Blade Brake Clutch ハンドルを放すと3秒以内に刃の回転が自動停止する)機構の搭載に成功する。こうして1978年、ホンダ初の歩行型芝刈機HR-21が発売された。HR-21は欧米をはじめ海外市場で好調に売り上げを伸ばし、1985年には年間約33万台のビジネスに成長したのである。
- :さまざまな機械のベースとなる汎用エンジン製品

ホンダ初の歩行型芝刈機HR-21。欧米の芝刈機市場で高い評価を得た

パリ郊外のディーラー店頭にて芝刈機を展示(1987年)
暮らしを豊かに。ホンダらしいロボット芝刈機を実現したMiimo

ホンダらしいロボット芝刈機のカタチを追求したMiimo
欧州では休日に芝刈機で自宅の庭を手入れするライフスタイルが定着しているが、2000年代以降、便利なITツールに囲まれて育った若い世代の間では、面倒な芝刈りを自動化してその時間を有効に使いたいというニーズが高まってきた。
自動運転芝刈機(ロボティックモア)が2004年ごろから欧州市場で拡大していく。2009年ごろには主要芝刈機メーカーも参入し始め、このままではホンダ離れが進むのではないかという懸念が広がり、ロボティックモアの開発が始まった。
そして2013年、ホンダらしいロボット芝刈機のカタチを具現化したMiimo*6を発売する。開発メンバーは欧州でロボット芝刈機を使っている家庭を訪問し、ロボット芝刈機の新たな付加価値に気付く。ある家庭では芝刈機に名前まで付けて愛用していた。単なる機械ではなく、ペットのように家族の一員として扱われていた。
「帰国後、ホンダのロボット芝刈機のカタチを考える時、やはりあのご家庭で目にしたペットみたいな存在というとらえ方が強く残っていました。そこでフレンドリーで優雅なガーデンライフという世界感において、Miimoのデザインは、やすらぎや幸せ感を大切にしようと決めました」(当時 汎用R&Dセンター主任研究員 保坂潤)
生産はフランスのオルレアンにあるホンダ・フランス・マニュファクチュアリング(HFM)。自動制御技術を搭載した家庭用電気製品の生産は、ホンダの工場としては初めてであった。異なるサプライヤーからの電気・電子部品の調達、ラインでの組み立てなどHFMにとっても大きなチャレンジとなった。
ホンダのパワープロダクツの源流をたどれば、人々の暮らしに身近に役立つ製品を提供することが理念である。
「実際お客様の声を聞くと、いろいろと機能があるけれど置いてあった時にカワイイとか、ある息子さんは、高齢になったお父さんのためにMiimoを買ってあげたらお母さんも喜んだという話をされていました。製品のみならず、製品が使われているシーンや生活感を演出できるところまで踏み込んでデザインを考えることで、お客様だけでなくそのご家族までも幸せになっていただけるということもあるんだな、と改めて知る機会にもなりました」(保坂)
「人々の仕事や生活の場で役に立つ製品を提供したい」という考えのもと、使う人の幸せや愛着を生み出すプロダクツを開発・生産していくことが、ホンダらしいロボット芝刈機を誕生させた。
- :My Intelligent Mowerを表す造語

ホンダ・フランス・インダストリー(HFI)は1986年にパワープロダクツ製品の生産を開始。2008年にHFMとなる
BLとの提携を足掛かりに四輪車市場へ挑む
 欧州での四輪車の販売と生産拠点の足掛かりをつかむきっかけとなった英国BLとの技術提携
欧州での四輪車の販売と生産拠点の足掛かりをつかむきっかけとなった英国BLとの技術提携
1973年の第一次オイルショック・1978年の第二次オイルショックをきっかけに、GMを頂点とするビッグ3は、大型車から小型車への戦略転換に乗り出した。これが自動車業界再編の火付け役となって「世界自動車戦争」が幕を開けた。燃費の良い小型車を得意とする日本車メーカーにとって大きなチャンスでもあった。
1979年12月、ホンダはオースチンやローバーで名をはせた英国のブリティッシュ レイランド(以下、BL)と技術提携を結ぶ。当時のBLは経営が低迷し、国有化されていた。BL民営化を公約に掲げるサッチャー首相の代理として駐日英国大使が提携を持ちかけてきたのである。日本の自動車メーカーが次々と辞退する中、ホンダはこれをチャンスととらえた。日本車への規制が高まる欧州で、四輪車生産の第一歩を踏み出せるかもしれない。欧州は数多くの自動車メーカーが存在し、小型車市場も形成されている。欧州の厳しい規制の中で、BLと手を組むことで、販売と生産拠点の足掛かりをつかむチャンスだったのである。
提携2年後の1981年、ホンダの乗用車バラードをBLがトライアンフ・アクレイムとしてライセンス生産を開始し、欧州各国で販売されて成功を収める。弾みをつけたBLは、エグゼクティブカーの共同開発を持ちかける。ホンダも高級車の技術が学べることを期待して、1983年に契約が締結される。プロジェクト名は「XX」。開発から生産までホンダとBLが共同で行う、世界でも画期的な試みだった。また同年トライアンフ・アクレイムの後継車として、日本のバラードをベースにローバー200としてライセンス生産することにも合意した。
初の共同開発で双方の開発チームは何度も衝突を繰り返しながら、やがて「XX」はV6エンジンを投入したレジェンド(1985年発売)、ローバー800(1986年発売)として結実する。

レジェンド
欧州のクルマづくりを学び、自らの市場を開拓する
1985年6月、XXプロジェクトが佳境を迎えていたころ、次のプロジェクトの新規提携覚書が調印され、YYプロジェクトと命名された。1986年12月には共同開発契約書が調印され、YYプロジェクトが正式に動き出した。レジェンドの経験を踏まえ、より効率のいい開発体制とするため、デザイン部分はローバーの良さを生かし、開発全体はホンダが主導権を握ることとなり、和光研究所(以下、HGW)や栃木研究所(以下、HGT)、HREにオースチン・ローバー・グループの開発担当者が長期滞在しながら進めていった。
大衆車カテゴリーであるコンチェルトは、欧州市場が求める「走る・曲がる・止まる」の基本性能に加え、コストや生産性も重視される。また、レジェンド同様に部品の現地調達率を80%以上にすることも課題だった。オースチン・ローバー・グループから欧州の部品メーカーの情報を仕入れながら調達を進めたが、ホンダの仕様と品質に適合する部品をつくってもらう難しさは並大抵ではなかった。そして、開発スタートから4年後の1989年5月、ローバー200/400とローバー・グループ製コンチェルトは発表され、ローバー・グループのロングブリッジ工場にて生産された。ローバー214は『What Car?』誌の1990年度「カー・オブ・ザ・イヤー」を獲得するなど好調な販売を続け、以後数年間にわたって派生機種を生み出すことになる。
バラード/トライアンフ・アクレイムに始まり、レジェンド/ローバー800、バラード/ローバー200、コンチェルト/ローバー200・400と続いた成功は、四輪車事業の欧州進出における確かな一歩となったのである。

ローバー・グループとの2回目の共同開発車 コンチェルト(日本仕様)
ローバー・グループとの提携がホンダにもたらした意義
欧州市場におけるホンダとローバー・グループの提携は加速していく。1990年、ホンダはローバー・グループと資本提携を結ぶ。前年の1989年には、イギリス・ウィルトシャー州スウィンドンにあるホンダ・オブ・ザ・UKマニュファクチュアリング(以下、HUM)での四輪車工場建設についても合意に達し、HUMで初の完成車を生産するため、欧州仕様のアコード/ローバー600の共同開発がスタートした。1992年10月、HUM初となる完成車、アコードがラインオフする。
日本の自動車メーカーの欧州現地生産も進む中で、ホンダは確かな手応えを感じていたのだが、シビック5ドア/ローバー400の開発もほぼ終了に近づいた1994年初頭、ローバー・グループがBMWに買収されることになり、ホンダとの資本提携は突如として終幕を迎えた。
シビック5ドアは1994年10月、ローバー400は1995年3月に発売、HUMとローバー・グループそれぞれの工場で生産された。15年続いた提携関係だったが、それはホンダに3つの大きな意義をもたらしたといえる。「まず1つは、輸入規制のあるヨーロッパに小さなマーケットしか持っていなかったホンダが、ローバーでコンチェルトをつくってもらうことにより、販売量の拡大を図れたということです。2つ目は、ホンダがエンジンの生産工場をHUMでスタートさせ、ここで生産したエンジンをローバーに供給するという形で、四輪車の現地生産の足掛かりをつくったこと。3つ目には、12年間にもわたる各種の提携関係で、先輩方が払われた大きな努力が、ヨーロッパ社会で評価されています。これはヨーロッパの自動車産業にホンダが仲間入りをさせてもらったということで、非常に大きな意義がありました」(当時 HME・HUM社長 三宅章二郎)。

1992年 HUM初の完成車アコードがラインオフ
自らのクルマは自らの手で。四輪車工場HUM始動
ホンダの欧州四輪車生産拠点として、HUMは大きな役割を果たしてきた。1985年に設立され、オースチン・ローバー・グループ製のバラードのPDI(完成車検査センター)としてスタートし、1989年からはコンチェルト/ローバー200/400の共同開発を機にエンジン生産工場としての役割を担う。「いつか自らの手で完成車をつくりたい」という夢を抱き続けてきたHUMだが、自動車工場は年間20万台の生産規模がないと経営は成り立たないとされていた。
ホンダの技術は欧州で高く評価されていたにもかかわらず、厳しい輸入規制によりホンダのマーケットは限定的にならざるを得ない。そこでローバー・グループからの委託生産をすることで、2車種を生産し工場を採算ベースに乗せる計画を立て、1992年にホンダブランドの四輪完成車工場として欧州仕様のアコードを生産することにこぎ着けた。
その結果、販売網も増強され、輸入制限の厳しいフランス・イタリア・スペイン・ポルトガルなどでの販売も可能になった。ホンダは輸入会社ではなく、欧州に根を下ろしたメーカーとなったのである。
「(欧州に生産拠点を設けたのは)お客様に喜んでいただける質のいいホンダ車を提供することです。ホンダには『需要のあるところで生産する』という基本的な考え方があります。これは、できるだけお客様の近くで生産することにより、それぞれのマーケットニーズに合った仕様・品質の製品をつくり、買った方々に喜んでいただくことにつながります。ヨーロッパのお客様のご要望に応えるために、ヨーロッパの中に生産拠点を持ったわけです」(三宅)

1992年に四輪完成車工場として稼働し、ホンダの欧州における四輪車生産拠点となったHUM
1989年、ホンダの事業活動を統括する欧州本社として、HMEが設立され、1992年6月には、世界を日本・欧州・アジア大洋州・北米の4グループに編成し、自律的に事業活動を進めるホンダの「世界四極体制」が敷かれる。HME・HUMは欧州における中心となっていった。