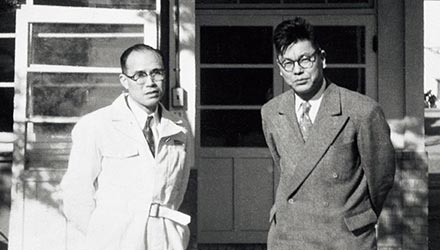即断即決、タイムリーな開発、タイムリーな上市を目指す
欧州の二輪車市場は、1980年代終わりから始まったEU(欧州連合)統合への期待感から好景気に突入し、1990年には年間販売台数が70万台を突破する活況を呈していた。しかし、1992年秋から翌1993年にかけての欧州の政治・通貨・経済危機によって、統合景気も意気消沈する。欧州全体が不況に陥ると、二輪車需要も縮小の一途をたどり始めた。同時に、モペッドの衰退とスクーターの台頭という変化も訪れていた。
だが、二輪車保有台数約2,100万台の欧州には、伝統ある二輪車文化と、多くの二輪車愛好家を抱える底堅い潜在需要がある。スクーターの台頭や免許制度改定などが要因となって需要減少も底を打ち、メーカーが開発競争に励んだことと相まって、需要は拡大に転じた。加えて、都市交通の過密化、フランス・イタリア・スペインなどの免許制度の改定(四輪免許取得者に125ccまでの二輪車乗用資格を付与)が追い風となった。
このころ、日本のメーカーは急激な円高に見舞われ、相対的な競争力低下に苦しんでいた。欧州メーカーが反撃に出て、新興アジア諸国のメーカー参入も相次ぐ。日本メーカーのお家芸ともいえる大型オートバイは欧州でのシェアが80%から70%に落ちていた。
欧州の市場環境を見据えて、ホンダは1996年、欧州二輪事業統括会社ホンダ・ヨーロッパ・モーターサイクル(以下、HEM)をイタリア・ローマに設立する。二輪車におけるNo.1の地位は揺るぎないが、欧州市場でのシェア縮小は憂慮すべき事態である。この状況を打破し、将来においても欧州市場で二輪車のリーディングカンパニーとしての地位を維持するために、イギリスにあるホンダ・モーター・ヨーロッパ(以下、HME)から二輪車部門を独立させた。ミッションは、即断即決、タイムリーな開発、タイムリーな上市を旨とし、欧州における二輪車のリーディングカンパニーとしての基盤を強固なものとすることである。
HEMは、HII・MHSAの二輪車生産と欧州10カ国での販売を統括し、ドイツにある研究開発拠点、ホンダ R&D ヨーロッパ(以下、HRE)からスクーターの開発機能を独立させたHREローマオフィスを併設し、そこにスクーターのSED(営業・生産・開発)機能を集結させた。
欧州の二輪車市場は、趣味性を追求した高付加価値を持つFUN領域と、日常生活の足として使われるコミューター領域に二分される。HEMでは1998年に大型FUN・Hornet(ホーネット)を欧州でデビューさせる。直列4気筒エンジンを搭載したロードスポーツ車の海外生産は日系メーカー初の挑戦である。年間2万5,000台を販売し、2001年の欧州No.1に輝く超人気モデルとなった。Hornet(ホーネット)を含む大型FUNモデル6機種は、1998年から生産を日本からHIIに移管し、欧州事業に大きく貢献した。

Hornet(ホーネット)(600cc 1998年モデル)
欧州二輪車販売台数No.1を実現した欧州プラットフォーム戦略
1996年の125cc免許の四輪車免許付帯化および50ccの改造規制強化を受けて、ホンダは125cc以上の登録スクーターのラインアップ充実を図る方向に舵を切った。翌年には、全モデル4ストローク化の方針を打ち出す。
短期間でラインアップ充実を図るために、新規エンジン・新規フレームを軸とした欧州プラットフォーム戦略が立てられた。年間に1モデルのハイペースで3モデルを一気に市場に投入していく計画だった。その実現のため、欧州の志向に合わせてホイールを12インチから16インチまで展開可能なフレームとエンジンを軸に、マフラー・エアクリーナー・スイングアームを共用する合理的なプラットフォームを採用した。ラインアップは、イタリアを中心にニーズの高い大型ホイールモデルSH125/150、新デザインを提案した@125/150、廉価スポーティーモデルDyla125/150となった。
第1弾となった2000年発売の@125/150は、渋滞するローマ市街で少しでも前に出ようとするスクーターの群れから着想を得て開発された。目標値もシンプルに、環境性能No.1のEURO 2(欧州二輪車の排出ガス規制)を先取り、燃費と走りの良さNo.1を掲げた。プラットフォームの軸となるコアエンジン・コアフレームの開発から始まり、リッター100馬力の高出力と低燃費性能を両立したエンジン、ローマの石畳を安定して走れる剛性の高いフレームが誕生した。デザインはHREミラノオフィスが担当し、300人を超える聞き取り調査を実施。デザインの本場が求めるクオリティを忠実に再現していくことに徹底的にこだわった。さらに90%という高い現地調達率を達成し、@125/150は欧州生産モデルとしてイタリアを中心に欧州の人々に広く受け入れられた。発売年の販売台数は、欧州で人気を誇っていたベスパET4を抜き、欧州全体で3位となった。
続く第2弾として2001年に上市したSH125/150は、イタリアで爆発的に売れ、イタリア国内で販売台数第1位を獲得する。コンセプトはローマへ通勤する人たちが乗りやすいベストサイズを追求すること。16インチのタイヤを履くハイホイールカテゴリーで、The Best Scooter for Centroを目指した。SH125/150はローマへ通勤する人たちに高い人気を呼んだ。とりわけ多くのユーザーに評価されたのは、まさにチームが目指したベストサイズと@125/150で開発した燃費の良いエンジン性能だった。

欧州プラットフォーム戦略のもと第1弾として開発された
@125

ローマへ通勤する人たちが乗りやすいベストサイズを追求したSH125
欧州のスクーターに新たな時代を切り拓いたSH300i
SH125/150はたちまち街中コミューターとして人気を博したが、一方で、250ccをはじめとする大型スクーターを好むユーザー層もあった。こうしたユーザーは郊外から高速道路を使って市街地に通勤する。大型スクーターは高速道路の走りは良いが、街中での渋滞や二輪車がびっしり並んだ路肩や駐車場ではそのサイズを持て余していた。
そこで、2007年に発売されたのが300ccで大型ホイールを擁するSH300iだった。開発チームは、SHシリーズの上級モデルとして、欧州の街並みに溶け込むエレガントなスタイリングと、石畳を華麗に走る上質な乗り味を兼ね備えたパッケージングが必要と考えた。これを技術課題に当てはめると、エンジンの大排気量化・発熱量抑制・小型化・冷却機能・車体剛性を、かつてないレベルで実現しなければならない。
エンジンは競技車用の機構を採用し、バランサーを廃止して小型軽量化するというチャレンジに挑み、排気量をアップさせて加速性能を高めた。車体は16インチの大型ホイールを装着し、広いフラットフロアを確保するためにフレームボディは大きなU字を描いた形状にして、各部品を収めた斬新なレイアウトとした。さらに走行時の安定性を生むために、U字部分に、トラス構造に着想を得た背骨を入れることでフレームの剛性を高めた。高出力化エンジンに熱はつきものだが、オイルパンにラジエーターから冷却水を通す構造、走行風導入ダクトとバッテリーボックスの二重構造化など、あらゆる手を尽くして対応した。
誕生したSH300iは販売早々大好評を博し、2007年にイタリアでクラスNo.1セールスに躍り出た。SH300iのあまりの独走ぶりに他社も追従し、市場に300cc・大型ホイールスクーターというカテゴリーを形成するほど影響力があった。新しい市場を開拓することは、時には確固たる既存技術を自己否定することから生まれてくる。それがユーザーの潜在的なニーズも掘り起こし、新しい時代を切り拓いていく。

欧州のスクーター市場に300㏄・大型ホイールスクーターというカテゴリーを生んだSH300i
ホンダのグローバルネットワークを活用したPCXの成功
「日常生活の足であるスクーターには、価格、燃費、使い勝手の良さなどが求められます。また、国によりタイヤサイズなどのニーズの違いにもきめ細かく対応していかなければなりません。その中で競争力を保つには、常に新しい提案をカタチにしていくことが必要です」(当時 欧州地域本部長 西前学)
ホンダのこうした考え方を具現化したのが、2010年に欧州で発売したPCXである。PCXは、タイ・ホンダ・マニュファクチュアリングTH*3で生産し、ベトナム・インドネシア・欧州各国・アメリカ・韓国・オーストラリア・ブラジル・日本などに輸出。その後、生産国をインドネシア〜ベトナム・ブラジル・中国にも拡大するというホンダのグローバルネットワークが活用された。ASEAN*4地域や南米向けには高付加価値の上級モデルとして新しい市場の開拓を目指し、欧州・アメリカ・日本などでは、環境性能・快適性・高品質とバランスのとれたお求めやすい価格の小型コミューターとして打ち出した。
エンジンは4ストロークの125cc。アイドリングストップシステムを採用し、燃費を向上させた。電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)やマフラーの触媒装置で、日・欧・米各国の排ガス規制にも適合する。先進的なデザインの車体に、燃費が良く環境性能に優れたエンジンを搭載し、お求めやすい価格を実現したことで多くのユーザーから支持された。
- :タイホンダマニュファクチュアリングカンパニー・リミテッド(Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.)
- :Association of South-East Asian Nations 東南アジア諸国連合

タイで生産しグローバルネットワークを活用して欧州にも投入されたPCX
欧州伝統の二輪車文化を受け継ぐFUNモデルをグローバルにリーディング

デザインをHRE-Iが担い、欧州大型FUNモデル市場へ新たなコンセプトで投入されたX-ADV
2010年代になると、大型FUNモデルの発信の場として、世界の二輪車メーカーがEICMA(ミラノショー)に出展するなど、大型FUNモデルの欧州発信がトレンドになってきた。
ホンダは以前より、欧州を大型FUN新機種のマーケティングの場として重要視してきた。その中で、新たなコンセプトで登場したのがX-ADVである。未舗装路走行を得意とするアドベンチャーモデルと、取り回しの良い車体サイズ、積載性の良いラゲッジボックスなどの使い勝手の良さで市街地走行を得意とするコミューターモデルを高次元で融合させることで、今までにないアドベンチャーモデルを提案した。
イタリア・ローマにある二輪車デザインを中心とした開発拠点ホンダR&Dヨーロッパ・イタリア(HRE-I)で、そのコンセプトを具体的なスタイリングデザインに落とし込んでいった。NCシリーズのプラットフォームを活用し、アドベンチャーとシティコミューターの要素を融合させた新しいカテゴリーともいうべきコンセプトモデルを提案。2016年のEICMAで初公開され、翌年2017年に上市されたX-ADVは欧州のお客様に支持され、発売以来、ホンダのラインアップの中で常に販売上位のベストセラーとなっている。
その後、X-ADVのスタイリングテイストは、ADV150/160・ADV350・NT1100など、ホンダモーターサイクルのアイデンティティーに影響を与えるきっかけとなった。
また、欧州をリードカントリーとして発表・発売しているAfrica Twinをはじめ、NT1100・Hornet(ホーネット)・Transalp(トランザルプ)なども、マーケットシェアを着実に拡大し、欧州におけるプレゼンスを向上させている。
高まる環境対応ニーズと、2009年のギリシャ財政危機問題に端を発した欧州の経済危機という苦境の中、次代のモデルはどうあるべきかの企画を進めてきた努力が、着実に実を結び、ホンダのグローバルリソース活用によって各国市場の変化にスピーディーに対応し、欧州における需要の拡大につながった。

Africa Twin