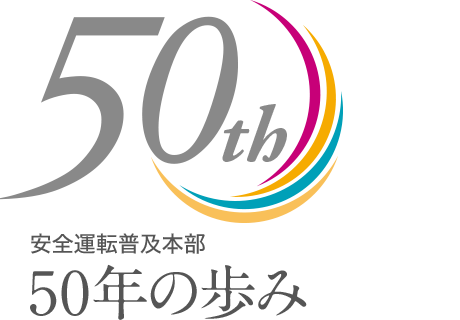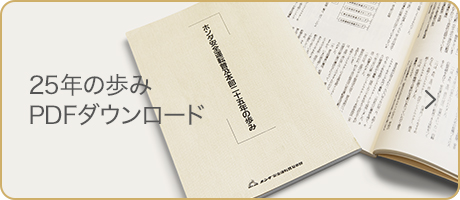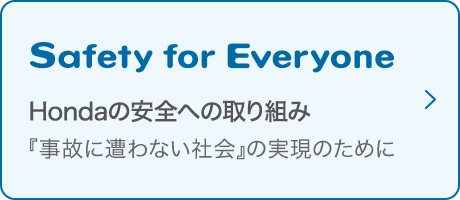Hondaの活動■印は国内活動
□印は海外活動
- 1962年 9月
- ■ 鈴鹿サーキット竣工
- 1963年 1月
- ■ ホンダ自動車教習所発足
- 1964年12月
- ■ 鈴鹿サーキットに安全運転講習所オープン
- 1966年 9月
- ■ 鈴鹿の安全運転講習所で全国の白バイ隊員に対する実技訓練スタート
- 1968年 4月
- ■ 白バイ高速乗務員の鈴鹿サーキット委託教養
- 1969年 6月
- ■ 警察庁主催「第1回全国白バイ安全運転競技大会」を鈴鹿サーキットで開催(第1回〜第24回大会まで毎年開催)
交通社会の動き●印は主な交通関係の法令制度など
○印は交通社会の動きなど
- 1962年 6月
- ● 大型自動車免許の取得(資格年齢21歳)
- 1965年 9月
- ● 安全運転管理者制度施行
- 1966年 4月
- ○ 交通違反取締りに覆面パトカー導入
- 1967年 4月
- ○ 指定自動車教習所で路上教習実施スタート
- 1968年 6月
- ● 交通反則金制度スタート
- 1968年10月
- ○ 全日本交通安全協会主催「第1回二輪車安全運転コンテスト(現、二輪車安全運転全国大会)」開催
安全運転普及本部関係の活動■印は国内活動
□印は海外活動
交通社会の動き●印は主な交通関係の法令制度など
○印は交通社会の動きなど
1970昭和45年
1971昭和46年
1972昭和47年
1973昭和48年
1974昭和49年
1975昭和50年
1976昭和51年
1977昭和52年
1978昭和53年
1979昭和54年
安全運転普及本部関係の活動■印は国内活動
□印は海外活動
交通社会の動き●印は主な交通関係の法令制度など
○印は交通社会の動きなど
1980昭和55年
1981昭和56年
1982昭和57年
1983昭和58年
1984昭和59年
1985昭和60年
1986昭和61年
1987昭和62年
1988昭和63年
1989昭和64年
平成元年
安全運転普及本部関係の活動■印は国内活動
□印は海外活動
交通社会の動き●印は主な交通関係の法令制度など
○印は交通社会の動きなど
1990平成2年
1991平成3年
1992平成4年
1993平成5年
1994平成6年
1995平成7年
1996平成8年
1997平成9年
1998平成10年
1999平成11年
安全運転普及本部関係の活動■印は国内活動
□印は海外活動
交通社会の動き●印は主な交通関係の法令制度など
○印は交通社会の動きなど
2000平成12年
2001平成13年
2002平成14年
2003平成15年
2004平成16年
2005平成17年
2006平成18年
2007平成19年
2008平成20年
2009平成21年
安全運転普及本部関係の活動■印は国内活動
□印は海外活動
交通社会の動き●印は主な交通関係の法令制度など
○印は交通社会の動きなど
2010平成22年
2011平成23年
2012平成24年
2013平成25年
2014平成26年
2015平成27年
2016平成28年
2017平成29年
2018平成30年
2019平成31年
令和元年
2020令和2年