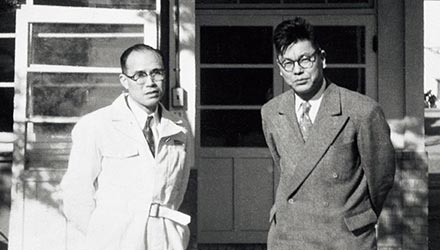クルマの普及がもたらした影
1960年代の半ば、日本はようやくモータリゼーションの時代を迎えつつあり、それに伴って排出ガスによる公害も出始めてきた。運輸省(後の国土交通省)は1966年7月、自動車の有害な排出ガスの基準を示し、同年9月以降の生産車(ガソリン自動車、ただし軽自動車は除く)については、一酸化炭素(CO)を3%以下にすることが義務付けられた。翌1967年8月には公害対策基本法が、1968年には大気汚染防止法が施行されるに至った。
1970年には東京都新宿区牛込柳町交差点付近の住民の血中鉛濃度が高い症例や東京都杉並区での光化学スモッグ被害が自動車公害問題として注目を浴びることとなる。
一方、米国では1963年、連邦政府が全米を対象とした大気清浄法を制定し、1965年には自動車汚染防止法が追加された。また、カリフォルニア州では大気資源局が、1966年から排出ガス規制を開始。さらに、連邦政府も1966年3月20日付の官報によって、大気汚染防止の規則を公示した。1970年、公害対策環境行政を強力に推進するため、保健・教育・厚生省(H・E・W省)で行われていた環境行政を、新設された米国環境保護局(以下、EPA、後に庁となる)に移管。時を同じくして、上院議員のエドモンド・S・マスキー氏が、従来の大気清浄法を大幅に修正した大気浄化法(通称、マスキー法)案を議会に提出した。同法案の内容は非常に厳しく、従来車に比べ、5年後の1975年型車から一酸化炭素(CO)・炭化水素(HC)はともに10分の1に、1976年型車から窒素酸化物(NOx)も10分の1にするというものであった。
GM・フォード・クライスラーといった米国のビッグスリーを筆頭に、世界中の自動車メーカーは「この規制内容を達成するのは不可能である」と主張したが、マスキー法は同1970年12月31日に発効した。
クルマが空気を汚しているのであれば
きれいにするのは技術屋
本田技術研究所では、1965年の夏、エンジン性能ブロックのリーダーを務めていた八木静夫が、将来の四輪車輸出を考え、米国における大気汚染の法規制の動向を探るため、同ブロック内に10人規模の大気汚染研究グループを発足させ、情報収集を開始。ホンダの大気汚染研究はひっそりと産声を上げた。
また、同年9月、技術調査室(当時)の伊藤薫平は、日・米両国の自動車排出ガスによる大気汚染とその規制、ならびに先行メーカーの当時の対応状況について調査を行い、報告会を開催。研究・設計グループを啓発した。この報告会をきっかけとし、伊達撛(当時、本田技術研究所取締役)、八木、中川和夫(当時、設計ブロック主任研究員)らは排出ガス対策研究を本格的に推進すべきであると合意し、機会を見ては大気汚染研究室発足の必要性を説いていた。
しかし、当時のホンダは、四輪業界への進出を果たしたばかりで、次なるクルマの開発が急がれていた。そのうえ、1964年1月にはF1TM 世界選手権への参戦を宣言しており、結果がすぐに出ない大気汚染の研究に、研究所の人員を割けるような状況ではなかった。
1966年6月、日本自動車工業会は、米国における自動車公害の現状視察を目的に調査団を組織し、渡米。メンバーの一員として、ホンダからは八木が参加した。調査は1カ月に及び、GM・フォード・クライスラーや関係官庁・大学などの関連研究所23カ所を訪問し、交通事故対策や排出ガスの研究状況をつぶさに調査した。この訪米調査をきっかけとし、伊達・八木・中川の3人が大気汚染研究の必要性を所長の杉浦英男に報告。「じゃあ、やろうよ」と、杉浦は即座に返答した。
早速、要員を集め、約30人で大気汚染対策研究室、通称AP(Air Pollution)研が発足した。
ゼロからの勉強、手探りでの研究がスタート
研究室は発足させたものの、エンジンの高回転・高出力化を追求してきた研究者にとって、排出ガス対策は初めての経験で、ゼロからのスタートとなった。AP研がまず始めたことは、当時、他社が研究していた排出ガス対策の検証と排出ガスに関する調査・研究を行うこと、そして研究所内への広報活動であった。
ガソリンエンジンやディーゼルエンジンの改善・改良はもとより、ロータリーエンジン・ガスタービンの代替エンジン、さらに酸化触媒(キャタライザー)や再燃焼(サーマルリアクター)などの後処理装置、アルコールや水素などの代替燃料と、さまざまな可能性を追求し調査・研究が行われた。
広報活動としては、AP研独自でAPニュースという広報誌を作成し、研究所、および関係する所外の部門へ配布。同誌には、国内や米国での排出ガス規制によって、自動車の設計・製造・整備など、各段階における仕事のやり方などが今後、いかに変わっていくかなどに関する情報が掲載されていた。
エンジン性能ブロックの設計者(当時)だった大谷淳示によれば、本田は研究所員に対し、「排出ガス対策で、今あるガソリンエンジンをなくすということは、大変なことだ。自動車会社の生産設備などを全部捨てなくてはならない。そのような対応ができるわけがない。既存エンジンへの規制だから、そのエンジンで達成可能な規制であるべきだ。だからこそ、既存のレシプロエンジンを改造しなきゃだめだ」と語り、既存エンジンでの対応を主張した。
AP研では、排出ガス対策は吸気と燃焼の制御を基本とし、それでも、なお排出される有害物質を後処理装置で処理しようと考えた。
当時の酸化触媒装置は、工場ばい煙などの固定施設に対応したシステムで、ペレット状の触媒を筒に入れたものであり、触媒としてはマスキー法を十分クリアできるレベルにはあった。しかし、自動車に装着した場合、振動で擦り減ったり、エンジンの燃焼具合では触媒装置そのものが焼失したりする状態で、耐久性に大きな問題があった。
また、再燃焼装置は、燃焼室で燃え切らなかった不完全燃焼物を、排気の途中で再燃焼させるもので、再燃焼を確実に行うためには、濃い混合気を供給する必要があり、燃費が悪くなった。
本田は、AP研のメンバーに、さまざまなアドバイスを行った。その中の主なものは、吸気の際に新機構のべーパーライザーによる燃料の蒸発促進や、燃料噴射装置による吸気効率のアップであった。
当時、技術的立場から指導にあたっていた東京大学の浅沼強教授は、毎月1・2回研究所を訪れていた。研究メンバーは同教授との意見交換を行う中で、有害物質であるCO・HC・NOxの発生量を同時に低減する方法としては、燃料を完全燃焼させる希薄燃焼しかないとの思いを強くしたが、当時の技術レベルでは到底クリアできるとは思えなかった。
「やらんで、何がわかるか」
本田にいつも言われていたこの言葉を実践すべく、AP研のメンバーたちは希薄燃焼の実現に向けた基礎研究(以下、R研究)を開始した。しかし、混合気の加熱・気筒内ガス流動の強化・点火エネルギーの増大・多点点火など、考えられるあらゆる方策をテストしたが、どれも良好な結果を得ることはできなかった。
同じことをしては追い付けない
他がやっていないことをやろう
試行錯誤が続く中、AP研の幹部は先発メーカーと同じ研究をしていては追い付くことが難しいと考え、他社がやっていない方法に挑戦することとした。その時、1つのアイデアが出た。
「従来のガソリンエンジンでは使われていない、副燃焼室付エンジンで希薄燃焼ができないか」
副燃焼室付エンジンは、ディーゼルエンジンの一部では実用化されていたものの、ガソリンエンジンでは粗悪燃料の利用や燃費の改善策として研究されるにとどまっていた。
大気汚染対策としての研究はどこも行っていないため、やってみる価値はある。N600のエンジンを使って改造設計を開始した。本田は設計室にたびたび顔を出し、図面を見ては次々と指示を出した。
「せっかく、図面をまとめようとしていたら、本田さんから指示が出て、また引き直さなければならなかった」と、改造設計を担当した大谷淳示は言う。試作エンジンの完成を待てない本田は、「うちにも、汎用エンジンで副室付エンジンがあるじゃないか。試作エンジンができるまでそれで研究したらどうか」と助言。汎用エンジンGD90での先行テストが開始されることとなる。
GD90はV型2気筒の479cc副燃焼室付ディーゼルエンジンで、実験用エンジンとしては手頃なものだった。まずは副燃焼室に点火プラグとガソリン噴射ノズルを取り付け、圧縮比を8から16まで調整できるように改造。このGD90を改造したエンジンテストは1969年12月から翌年2月まで行われた。テスト結果はおおむね良好。ガソリンエンジンでの希薄燃焼の可能性を示唆してくれた。
そして1970年1月には、待ちに待ったN600を改造した単気筒300ccエンジンが完成し、試作エンジンによるテストを開始。副燃焼室の最適な条件出しなど、希薄燃焼のR研究が行われた。
さらに排出ガス対策に不可欠な水冷エンジンでの研究も行われることになったが、ホンダにはテストに使える四輪車の水冷エンジンがない。とても水冷エンジンを自作する時間的余裕はないことから、日産自動車(株)(以下、日産自動車)の1600ccエンジンなどを使いテストが行われた。このテストでは他社のエンジンを使うことで、より汎用性のある研究データを収集できたという副次的効果も得られた。
また、研究体制の見直しも行われ、1970年12月にAP研は発展的に解消。第4研究室と第5研究室が設けられた。人員も常時、100人を超える体制とした。
ついにマスキー法クリアが目前に
CVCCエンジンを発表

 副燃焼室に点火プラグとガソリン噴射ノズルを設けた
副燃焼室に点火プラグとガソリン噴射ノズルを設けたCVCCエンジン燃焼室カットモデル
R研究が終了し、有害成分を減少させる可能性が見えたと知らせを聞いた本田は、低公害エンジンを公表すると宣言。研究途中での公表について本田は、
「君たちに聞いても、もうこれで完成したとはいつまでたっても言うはずがない。それを待っていたのでは会社がつぶれる」と、この段階での発表に踏み切った。ホンダ流に言う、「2階に上げてはしごを外す」やり方で、新エンジンの公表による従業員の士気高揚と、研究開発の進展を促したのだった。
また、発表する以上、新エンジンには名前が必要だ。研究所の応接室に伊達・八木・中川らが集まった。
「この時点では、めどが立ったとはいえ研究が進行中でしたから、当然、特許申請もまだ途中でした。そんな中での公表ということで、名前から構造の一部でも分かるようなことがあってはならないと思いましたし、燃料供給方式もまだ決まっていませんでしたので、ユニークでパンチの効いた名前にしようと考えました」(伊達)
そうして新エンジンの方式は、Compound(複合・複式)・Vortex(渦流)・Controlled Combustion(調速燃焼)の頭文字を取り、「CVCC・複合渦流調速燃焼」と命名された。
C(Compound)は、エンジン機構として、燃焼室が主燃焼室と副燃焼室の2つがあることから、複合・複式を表す。
V(Vortex)は、副燃焼室で燃焼した火炎がトーチノズルを通して主燃焼室に噴流となって噴出すると、主燃焼室内に渦流を起こし、エンジンの燃焼速度を速める作用をすることから、渦流を表す。
CC(Controlled Combustion)は、燃焼速度を適正コントロールすることから、調速燃焼を表す。
1971年2月12日、本田は東京・大手町の経団連会館で記者会見を行い、「1975年の排出ガス規制値を満足させるレシプロエンジン開発のめどが立ったので、1973年から商品化する」と発表。同時に従業員に向けても2月26日発行のホンダ社報臨時号で、CVCC技術によりマスキー法で定められた基準を達成できる見通しが立ったと発信した。
試作エンジン1号機は、企画開始から2カ月という短期間で完成した。その後、埼玉製作所(当時)の協力を得て100台が製作され、ベンチでの基本性能テスト後、日産自動車・サニーのフレームに搭載し、シャシーダイナモ上のテストに入った。
副燃焼室方式による希薄燃焼では、当初予測していた通り、CO・NOx・HCの減少は図られたが、HCについてはマスキー法1975年度規制値には及ばなかった。しかし、その後の排気系(マニホールド)の研究と、主・副燃焼室の組み合わせや燃料の供給方法で、排出ガスの保持熱により排気管内での酸化反応が起き、HCの低減を図ることが可能となった。これによりエンジニアたちは、酸化触媒装置を使用することなくマスキー法規制値をクリアできる目処を立てることができた。

CVCCエンジン燃焼プロセスイメージ図
自身が培ってきた技術力による達成
1972年10月11日、この日はホンダにとって記念すべき日となった。東京・赤坂プリンスホテルにおいてCVCCエンジンの全容を国内外のジャーナリストに発表。会場は、低公害エンジンを印象付けるためにブルーのパネルで飾られ、澄み切った青空が表現された。
この発表会には、社長の本田を始めとする各役員・開発担当者が出席し、CVCCエンジンについて、その開発過程やエンジン特性、燃焼理論を紹介した。
同エンジンの特長として挙げられたものは、
①従来のレシプロエンジン本体をそのまま使うことができるため、現在の生産設備が生かせる。
②エンジン内部できれいな燃焼をするため、触媒などによる排出ガス浄化装置は不要で、2次公害の恐れがない。
③シリンダーヘッドから上を交換するだけで済むので、他メーカーのエンジンにも応用でき、広く低公害化が図れる。
などであり、本田が開発当初から目指していたエンジンになったことを明らかにした。
「他社にも良い研究はありましたが、それを実現する技術がありませんでした。ホンダは、全部自分たちで考え、研究し、その技術を確立したのです」と、本田の教えである「自前技術の大切さ」を八木は語る。CVCC方式の原理に関する総合特許、ならびに周辺技術を含め、この時点で出願された特許は230件に及んだ。
公害対策技術は
多くの自動車メーカーで共有する
この発表は、国内外に大きな反響を呼んだ。米国EPAからは、早速、CVCC搭載車の提出要請があり、ミシガン州アンナーバーにあるEPAのエミッション・ラボに3台が送られた。3台のうち2台は1万5,000マイル走行車、もう1台は5万マイル耐久テスト完了車が持ち込まれた。立ち会いテストは1972年12月7日から14日まで行われ、1975年規制のマスキー法合格第1号となった。
また、テストでは、日産自動車のサニーにホンダのCVCCエンジンを搭載してデータを計測した。当時、ホンダにはCVCCエンジンを積める大きさの車体がなく、やむなく、テスト時から使っていた他社の車体での適合テストとなったのだ。
本田は、かねてから公害対策技術は公開する方針を表明しており、CVCC技術は他の自動車メーカーにも公開した。これに呼応して、トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)から問い合わせがあった。トヨタの技術者が研究所へ来所し、クルマの試乗、技術内容の説明などを受けた。トヨタはCVCC技術を評価し、同年12月13日、技術供与に関する調印が行われた。
「トヨタが最初というのは、CVCCにとっても、ホンダにとってもプラスが大きかった。トヨタに技術供与をしたと新聞に出たら、すぐに国内や米国メーカーからも引き合いがありましたからね」
と、技術供与に関する対外交渉の実務責任者(当時)であった吉澤幸一郎は言う。
その後、フォード・クライスラー・いすゞ自動車(株)の各メーカーにも技術供与されたが、この間、研究所には世界の主要自動車メーカーの技術者が続々と来訪した。
このクルマがだめだったら、四輪車市場からの撤退も考えなければならないという背水の陣で開発されたシビックが、1972年7月12日に国内で発売された。同車の市場評価は高く、1973年度『モーターファン』誌主催のカー・オブ・ザ・イヤーに輝いた。翌1973年12月13日には、4ドアのシビック CVCC(1500cc)が発売され、シビックの名前を国内市場で不動のものとした。
米国市場へのシビック CVCCエンジン搭載車は1975年モデルから輸出された。
輸出にあたっては、EPAからマスキー法1975年規制適合認定を受けなければならなかった。ホンダは1972年にCVCCエンジン単体でマスキー法の適合審査に合格していたが、シビック CVCCとしての審査は受けていなかったからである。
1974年11月、シビック CVCC 1975年モデルがEPAに持ち込まれた。
「テストが終わり、コンピューターが計算をして、その結果が出てくるまでは、大学の入試発表を待つような気分でした」
と、EPAプロジェクトで認定担当(当時)だった福井威夫は語る。
審査終了後、EPAの検査官は
「コングラチュレーションズ」
と、握手を求めてきた。福井は無事に認定が取れただけで喜んでいたが、EPAの検査官は燃費が1番であると伝えたのである。
「われわれはエミッションばかりに気を取られていて、燃費のことはまったく考えていなかった。しかし彼ら(EPA)にとっては、エミッションは当たり前で、将来を考えたら燃費だということだったんですね」(福井)
シビック CVCCは年を追うごとに燃費が向上し、1978年モデルまでの4年連続で、EPAで米国燃費1位認定を獲得。2000年に米国自動車技術者協会(SAE)の月刊誌『Automotive Engineering』誌が選出する20世紀優秀技術車(Best Engineered Car)の70年代優秀技術車に選ばれるなど、時代を超えて高く評価されていくこととなる。

CVCCエンジンを搭載したシビック
未来を担う子どもたちのために
 「CLEAN AGE CAR」と銘打たれたシビックCVCCキャンペーンポスター
「CLEAN AGE CAR」と銘打たれたシビックCVCCキャンペーンポスター
マン島TTレースへの出場宣言以来、高回転・高出力のエンジンを絶えず追求してきたホンダは、自分たちが乗り越えるべき課題として低公害エンジンの開発に挑戦。その道のりは平たんなものではなかったが、「マスキー法への対応は企業本位の問題ではなく、自動車産業の社会的責任上なすべき義務である」という強い想いがエンジニアを突き動かした。
ホンダはその後、規制や法律に合わせて製品を開発していくだけではなく、持てる技術によって積極的に環境負荷低減を追求していく。1991年には優れた走りを持ちながら低公害・低燃費を実現した希薄燃焼エンジンVTEC-Eを発表。1998年、米国とカナダで、排出ガスの中でも光化学スモッグの原因となるハイドロカーボンの量をそれまでの10%に規制する米国カリフォルニア州排出ガス規制ULEV(Ultra Low Emission Vehicle)の認定を取得したアコードとシビックを、さらに2000年には、カリフォルニア州の新・自動車排出ガス規制LEVIIの中で最も厳しいSULEV(Super Ultra Low Emission Vehicle)の基準を満たしたアコードを発売。量産のガソリン車で達成したのは、どちらも世界初だった。
さらにホンダは、2011年、グローバル環境スローガン「Blue Skies for Our Children(子どもたちに青空を)」を制定。CVCCエンジンの開発から始まった地球環境負荷低減への取り組みは、資材調達から製造・流通・廃棄といったすべての工程、さらには社会貢献活動など、企業責任・社会責任において地球環境負荷ゼロ達成に向けた挑戦を続けている。