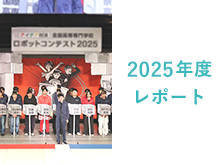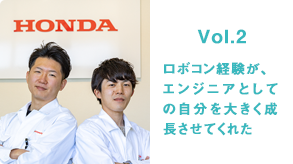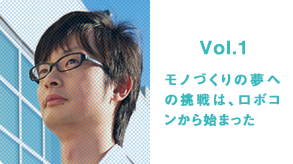- 高専ロボコンTOP
- 取材レポート
- Honda Engineer Voice
- アーカイブ

来場者数:4,069人
高専生(エキシビジョンチーム含む28チーム):278名
Honda従業員観戦(家族含む):327名※
※申込段階の数字で、当日キャンセル等は含んでいません。


全国の高専生が「アイデアと創造性」をキーワードにロボットを製作し、与えられた競技課題に挑んで、その成果を競い合う全国高等専門学校ロボットコンテスト(通称:高専ロボコン)。Hondaは次世代を担うエンジニアたちを応援したいという想いから、2002年より協賛を続けている。
11月17日に両国国技館で行われた全国大会には、地区予選を勝ち抜いた全26チームが集結。ロボコン史上、最も難易度が高いといわれるテーマの壁を、どのような独創的なアプローチで乗り越えるのか。技術力はもちろん、立ちはだかる壁に果敢に挑む高専生たちの姿は今大会の最大の見所。大会では、次世代のエンジニアたちが地区大会からさらにブラッシュアップさせたロボットで、最後の熱き戦いを繰り広げた。

今年の大会テーマは「ロボたちの帰還」。競技課題は、ロボットを狙った場所に着地させてオブジェクト(ボールとボックス)を回収し、ロボットを再びスタートエリアに帰還させるというもの。各チームはロボットの着地地点や届けたオブジェクトの数などで合計点を競い合うが、オブジェクトの回収方法やロボットを帰還させる方法は決められておらず、各チームのアイデアと戦略に委ねられている。例年以上に独創的なアイデアと巧妙な戦略、そして高い技術力が求められる難しいテーマだ。

今年の大会テーマが難しいといわれた
理由の一つが、“ロボットを
投げ上げて飛ばす”というルールだ。
飛ばされたロボットは着地の衝撃でダメージを
受け、うまく稼働しなくなったり、最悪の場合、
壊れるリスクを負うことになってしまう。
各チームが衝撃を減らすためのアイデアや工夫を
ロボットに施すなどの対策をしているが、
試合中は想定外の故障やトラブルがいくつも発生。
制限時間が迫るなか、故障の原因を見極め、
復旧に急ぐチームの姿を
会場中の観客が固唾をのんで見守った。





各チームが競い合い、緊張感ある闘いが繰り広げられる中、見事優勝を勝ち取ったのは、二回戦で敗れたものの、ワイルドカード※によって復活を果たした大阪公立大学工業高等専門学校の「銀火(ギンガ)」。100点を狙える精度の高い着地と素早くオブジェクトを回収する機動性で、決勝までにすでに2回のミッションコンプリート(時間内にすべての課題をクリアすること)を達成していた本校。決勝でもその技術力の高さはぶれることなく、40秒台でコンプリートし、昨年の優勝校としての強さを見せつけた。
※ワイルドカート:1回戦・2回戦で敗退したチームのうち、優れた戦いぶりが評価
された1チームが、審査員の選出により準々決勝に進出できる。




最も優れたアイデアを生み出したチームに贈られるロボコン大賞に選ばれたのは、香川高等専門学校(詫間キャンパス)の「KKO(カカオ)」。故障を恐れずに挑んだ、特徴的なドラム型のロボットの100点エリアへの着地と回収、橋を使ったスムーズなロボットの帰還は見事と審査員から高い評価を受けた。



高専ロボコンの各協賛企業が選ぶ特別賞のうち、
「Honda賞」を手にしたのは大分工業高等専門学校のチーム。製作したのは、ボールを届けるロボット「蒼玉(ソウギョク)」、ボックスを回収するロボット「紅玉(コウギョク)」、そしてそれら2台を投げ上げる「翠玉(スイギョク)」。エメラルド、サファイヤ、ルビーの宝石を模したという美しく、色鮮やかなロボット3台だ。
近距離からボールを一つずつ着実に射出するだけでなく、遠距離への射出にも果敢に挑戦するその勇姿は観客に強い印象を残した。

-

- 軽くて強度のある5.5ミリのテクセルボードを紐で組んだボディは、軽量で衝撃に強い構造。また、試合では見ることが叶わなかったが、紅玉は壁との距離をレーザーで測定し、飛距離が一定以上になると自動でロックを解除し、ボックスを届ける仕組みを備えている。
-

- 蒼玉が、回収したボールを翠玉の格納スペースへ!
ローラーでの射出で狙った場所に飛ばす技術力の高さは評価にもつながった。

大分工業高等専門学校
チームリーダー
平川晴己(ひらかわ はるき)さん
Honda賞を受賞し、自分たちの実力と努力を評価していただけたと感じ、嬉しかったです。実は、100点エリアを狙うだけのロボットをつくるアイデアもあったんです。ですが、着地から回収、帰還までミッションをしっかり遂行できる競技用ロボットをつくるということに最後までこだわりました。工作機械が壊れて練習が十分にできず、心が折れそうになることもありましたが、これまで先輩方がつないでくれた大会への道筋をこれ以上途切れさせないよう、チームで一丸となって頑張りました。
ロボコンを通じて学んだのは、チームの大切さです。1人ではできなくても、チームで協力することで1つのプロジェクトを成功させることができます。このロボコンでの経験を活かし、将来はエンジニアになって自分の好きなことをしつつ、人の役に立つロボットをつくれたらと思っています。

今回の競技では、勝ちを取りに行くなら、ロボットを投げ上げる際は平たく小さいものを柔らかく包んで投げる、また、回収役のロボットについては距離を飛ばす必要のない2台目以降のロボットとして投げるのが、故障のリスクを軽減できる安全で確実な方法です。ですが、大分高専は回収役のロボットを投げ上げて高得点を狙うリスクの高い方法を選びました。敢えて困難にチャレンジする姿勢、そして、軽量化による着地衝撃の緩和や、ロボットの剛性・強度の確保によりロボットの破損・変形の防止など、リスク対策をしっかり行なえていた点を評価しました。



Honda賞審査員
株式会社本田技術研究所 先進技術研究所
フロンティアロボティクス研究ドメイン統括
エグセクティブチーフエンジニア
吉池孝英さん
今年のロボコンは、ロボットを投げ上げるというかなり難易度の高いルールがありました。そのため、ロボットが壊れたり、動かなくなったりするのかなと心配していましたが、複数のチームがミッションコンプリートを果たしていて、そのレベルの高さには正直驚きました。また、ロボットがどうやって帰還するのかが今回のポイントでしたが、どのチームもそれぞれ独創的なアプローチを考えていました。そこが今年の大会ならではの面白さだと思いました。
学生たちは、2分30秒という限られた時間内で自分たちのやりたいことを実現するために、日頃からさまざまな準備を重ね、製作に取り組んでいます。ロボコンは、技術力を向上させるだけでなく、「うまくいかなかったときにどのように対応するか」を考えたり、さまざまな経験を積むことができる場だと思います。この先のエンジニア人生を考えた時、うまくいかない、壁にぶつかることもたくさんあるでしょう。ぜひこのロボコンで、そういったものを身に付けながら、新たな壁に向かってトライしていただきたいです。

全国の高専生たちがアイデア、技術、戦略を競い合い、
情熱を注いだ2024年の高専ロボコン。
ロボコンを通じて得た、課題をクリアする難しさや、
チームでつくり上げる喜び、
そしてものづくりの楽しさは、彼らの夢を
きっと後押ししてくれる糧になるはず。
これからも、ものづくりへの情熱を絶やさず、
自分の目指す未来へ向かってチャレンジしてほしい。
Hondaは夢を追い続ける未来の若きエンジニアたちを
応援しています。