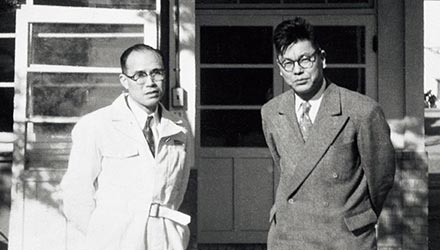勝率5割の裏側にある進化
 RC181
RC181
 NR500
NR500
 NS500
NS500
 NSR500
NSR500
 RC213V
RC213V
2023年は、ホンダがロードレース世界選手権、現在のMotoGPに参戦して65年目となるが、この間、最高峰クラスであるWGP500とMotoGP(2002年から2022年シーズン)で通算21回のライダーズチャンピオンを獲得しており、その活動は次の4つの時代に分けられる。
①4ストローク直列4気筒のRC181での参戦(1966年から1967年)
②4ストロークV型4気筒のNR500での参戦(1979年から1982年)
③2ストロークV型3気筒のNS500、同V型4気筒のNSR500での参戦(1982年から2001年・2002年MotoGP初年度のみ2スト・4スト混走)
④4ストロークV型5気筒のRC211V・990cc、同V型4気筒のRC212V・800ccとRC213V・1000ccでの参戦(2002年から2022年シーズン現在)。
この中でライダーズチャンピオンを獲得したのはNS500とNSR500の2ストローク時代とRC211V・RC212V・RC213Vの4ストローク時代であり、2022年シーズンの終了時点ではおのおの11回と10回のライダーズチャンピオンを獲得している。つまり、どちらの時代もほぼ勝率5割を達成していることになり、これは当時のライバルたちに比べると抜群の戦績だ。しかし、視点を変えれば、出場した半分のシーズンで負けたということになり、奇しくも、双方の時代とも4年連続の敗北の後の大躍進が存在する。
同じ4ストロークエンジンで比較すれば、エンジン回転数は1960年代半ばに125ccや50ccのエンジンで毎分2万回転を超え、4ストロークV型4気筒で長円ピストンを使ったNR500も最終的に2万回転を達成した。RC213Vは排気量がNR500の倍の1000ccとなり、その分だけフリクションも増大しているがおおよそ18,000回転付近まで回っている。いつの時代も高回転・高出力はレーシングエンジンの基本である。
 高回転を追求し、2ストロークによって高出力が容易となった
高回転を追求し、2ストロークによって高出力が容易となったNSR500エンジン
過去のレーシングマシンが、現代のような材料や加工技術がなく解析技術なども不十分であった時代に、超高回転を成し得たことは驚異的であるといってよいが、言い方を変えれば60年前にでも超高回転でエンジンを回すことは技術的に可能だったわけである。課題は時代ごとにエンジンに対して求められる条件が異なっているということにあり、それによって追求すべき技術的テーマも異なってくるということだ。
4ストローク直列4気筒エンジンの時代は高回転・高出力化を狙い、ただひたすら機械的な回転上昇を追求した。その経験を反映させながら、4ストロークV型4気筒のNR500時代は構造的にまったく異なる形式のエンジンで、やはり機械的に高回転化を追求した。
NS500・NSR500時代は、2ストロークによって高出力が容易になったことから、その出力自体を効率的にスピードに結び付けるための出力制御に取り組んだ。そして、4ストロークV型4気筒RC213Vの現在(2023年)は、今なお高回転・高出力化を追求するのは当然として、そのパフォーマンスを保証する品質や耐久性が技術課題となっている。
 高回転を追求し、2ストロークによって高出力が容易となった
高回転を追求し、2ストロークによって高出力が容易となったNSR500エンジン
特にMotoGPにおいては20年の間に2度の排気量変更・燃料タンク容量の規制・1シーズンにおける使用可能エンジンの基数制限と、順次厳しくなっていったレギュレーションによって、エンジンには以前よりも格段に高いレベルの性能や耐久性が求められている。つまり、かつては性能の「絶対値」が、その後は性能の特性が求められ、そして現代では、さらに「質」が求められているといえる。その意味では、MotoGPにおけるホンダの技術的な取り組みは、「21世紀における4ストロークエンジン開発の歴史」と呼べる内容を体現している。
RC211V

2002年投入され開幕戦優勝 16戦中14勝とライバルを圧倒したRC211V
 4ストロークV型5気筒 Vバンク角75.5°のRC211Vエンジン
4ストロークV型5気筒 Vバンク角75.5°のRC211Vエンジン
 2002年ロードレース世界選手権 バレンティーノ・ロッシ
2002年ロードレース世界選手権 バレンティーノ・ロッシ
MotoGP初年度の2002年に投入されたRC211Vは、まったくの新設計である4ストロークV型5気筒エンジンを採用し2002年に続く2003年でライダーズチャンピオンを獲得している。このエンジンはVバンク角75.5°、クランク位相角104.5°というディメンションにより1次振動を理論上ゼロとしたもので、高出力かつコンパクト、そして独創的であるべきという命題をクリアしたエンジンだった。初代開発責任者(以下、LPL)が「絶対に負けない自信があった」と言う車体も含めたマシン性能は、2002年の開幕戦で優勝すると以降9連勝を記録。最終的に16戦中14勝という戦績でライバルを圧倒。
しかし、その裏側で開発チームは、開幕戦直前から壊れ続け、耐久性が保証できないエンジンの対策に追われていた。開幕直前テストで使ったエンジンが、性能チェックのベンチテストで壊れた。コンロッド小端部の齧りが原因でピストンとバルブが破損したのだ。このため、2,000kmでの管理を予定していたピストンは対策品ができるまで300km管理となり、これにより当初計画のエンジン1基/1レースというエンジンローテーションが、エンジン2基/1レースとなってしまい、レースの開催日程によってはオーバーホールが間に合わなくなる場合も予想され、いわゆる「エンジンの自転車操業」に陥ったのである。
しかも、開幕戦ではフリー走行時での転倒で早速ローテーションに狂いが生じた。加えて燃費が事前に想定したレベルに達していなかったこともあり、用心のためエンジン出力を抑えて参戦した。この、開幕戦での薄氷を踏む思いとは裏腹に、快勝を収めることができたことは大きな自信になったものの、トラブルは収まらず、第2戦ではレースの現場でエンジンを分解することになった。当時のエンジン開発担当(以下、PL)で、ホンダ・レーシング(Honda Racing Corporation〈以下、HRC〉)の元常務取締役・二輪レース部長である若林慎也が振り返る。
「開幕戦に続きピストンのマイレージは300km管理だったが、現場に行ったスタッフから『エンジンが足りないので、ニコイチで組み直してもいいか』と尋ねられ、さすがにそれは止めさせた。急場をしのぐには小端部にブッシュを入れて齧り対策を施すことしかないと考え、全エンジンを日本に戻し、製造メーカーさんにブッシュが付いたままのコンロッドを持ち込んで加工してもらうようお願いするなどして、なんとかエンジンを再生した。そのころはそんな対応を常に繰り返していたし、他にも吸気側バルブスプリングの折損・ステムエンドの欠損・リフターの齧り・バルブやバルブシートの不具合と、課題は山積みで、シーズン序盤は動弁系の精度向上や仕様変更に追われ続けていたのが実態だった」
これらの対策部品が完成し、ようやくひと息ついたのがシーズン中盤だったが、第10戦ではシーズン初のリタイヤを喫し、連勝記録はストップした。リタイヤの直接的な原因はリアタイヤのブローだが、このレースを前にラムエア過給を導入し、5%(約10PS)程度の出力向上を実現した結果、タイヤが持たなかったのだ。このように自らの出力に耐え切れなかったともいえるRC211Vでは、シーズン終盤まで対策が続き、仕様の変更や改良を行った部分は実に87カ所に及んだ。MotoGP初年度の躍進は、必死のフォローで何とか勝ち抜いたというのが実態だった。
「幸いだったのは、実戦でのエンジントラブルはクラッチトラブルが1度のみだったということだろう。とにかく2002年はいろいろな部分が壊れ、ひたすら直し続けることに没頭せざるを得なかった。そのため根本的な性能向上には手が回らず、2003年になってようやく性能向上が実現できた」(若林)
2003年は、新たに参入してきたドゥカティが最高速に優れていたこともあり、2002年に14,750回転でスタートした回転数のリミットを15,500回転まで引き上げて、より高回転・高出力化を図った(最終的には15,750回転)。そして、4チーム・計7台のRC211Vは出場レースすべてで表彰台に上がり、全体では16戦15勝という圧勝ぶりでシリーズランキング上位を独占。ところが2年連続でライダーズチャンピオンとなったエースライダーのバレンティーノ・ロッシ(以下、 V・ロッシ)がヤマハへ移籍してしまったのである。
 2004年に投入されたHITCSの構造図
2004年に投入されたHITCSの構造図
2004年に向けてはボア・ストロークを変更し、さらなる高回転化を図りながら点火間隔も変えるという大幅な変更を施し、回転域は16,000回転以上に拡大。最高出力を2002年当初の226PSから256PSまで向上させ、その駆動力を最適化するHITCS(ホンダ・インテリジェント・スロットル・コントロール・システム)*1も投入し、万全の準備を整えた。
 2004年に投入されたHITCSの構造図
2004年に投入されたHITCSの構造図
しかし、2004年はV・ロッシの9勝に対してホンダ勢は合計7勝に終わり、47ポイント差でV・ロッシに逃げ切られてしまった。シリーズランキングでは2位から6位までをホンダ勢が占め、4年連続のメーカータイトルを獲得したことからも、マシンの仕上がり自体は悪いものではないと思われたが、結果的にライダーのポテンシャルに負けてしまったのである。
「この年は、2レースに1回ぐらいの頻度でマシンをアップデートし、エンジンも10種類くらいの仕様違いを投入していた。不等間隔爆発と同爆もあり、最後は16,750まで回したと思う。当時は2レース後には新規で何を入れようかずっと考えていた。毎日、1日の半分はベンチの前で動力研究PLと話をして大体やることを決めたら、夜に自席に戻って図面に直しを入れておくと、トレーサーが翌日に作図しておいてくれて、翌日夜にまた違う指示を書きこむような感じだった。上役たちには『決めたことに対しては文句言わないから、PLとしてよく考えて自分で決めろ』と言われていたから、とにかくマシンをもっと速くするために、エンジン馬力を出すために、どうすべきか常に考え続けていた」(若林)
2005年のRC211Vはリアサスペンションの変更・フレームの改良など、車体関係を大きく変えた。「V・ロッシに対して減速時の車体安定性に劣り、コーナーでの旋回性や加速も負けている」というライダーからの打ち上げを基に、コーナー進入から立ち上がりまでの一連の動きを向上させるための改良であった。しかし、結果は惨敗に終わる。V・ロッシはリタイヤした1戦以外はすべて表彰台に上がり17戦11勝。これに対しホンダ勢は4勝を挙げたのみだった。
この年は、シーズンを通じてエンジン・車体とも3つの異なるバージョンを投入したが、V・ロッシに太刀打ちできなかったのである。実は打倒V・ロッシの秘策として、それらとはまったく異なる設計のマシンをシーズン中盤で投入する予定があった。それは、2007年の800cc化に向けて開発中だった新型エンジンをベースにしたニューマシンであったが、2005年のマシンとそれを踏襲した次期マシン、そしてそれらと異なる新型という3機種の並行開発は困難を極め、実戦投入に翌2006年まで時間を必要としたのである。
そのニューマシンが2006年のRC211Vニュージェネレーションと呼ばれるものだ。このマシンは、800cc化に向け徹底したダウンサイジングを追求していたV4エンジンをベースに設計されたV5エンジンを搭載しており、そのサイズはそれまでのV5エンジンとは別物の仕上がりであった。しかし、あまりにも急進的にコンパクト化を推進したため、エンジン各部の耐久性が確立できず、約30回のエンジンテストを実施したが、1周の距離も持たずに壊れるほど脆弱だった。それが2005年の投入に間に合わなかった理由である。

右がコンパクト化された
RC211Vニュージェネレーションエンジン

ニュージェネレーションエンジンを搭載したRC211V
 2006年ロードレース世界選手権 N・ヘイデン
2006年ロードレース世界選手権 N・ヘイデン
材料・形状・加工精度、そのすべてを徹底的に精査・改良し、かつてない詳細な項目と時間で部品管理を行い、最終的にはレースごとにエンジンを丸ごと交換するという荒技で、RC211Vニュージェネレーションは実戦投入が可能になった。それでも用意できるエンジンは1台分のみという状況であり、当時のエースライダーであるニッキー・ヘイデン(以下、N・ヘイデン)のみに与えられ、他のライダーは正常進化版のRC211Vで参戦。RC211Vニュージェネレーションは、小型化されたエンジンに合わせて車体関係も完全新設計となり、2005年のRC211Vと同じ開発テーマである減速時の車体安定性・コーナーの旋回性能・立ち上がり加速性能を大幅に向上させたバランスの良いマシンとして仕上げられた。
2006年シーズンは、ホンダとヤマハ、そしてドゥカティの三つどもえの戦いとなった。その中でシーズンを通じて安定感のあったN・ヘイデンがランキングトップを走り続けた。そして、N・ヘイデンが最終戦を前に転倒し、V・ロッシに逆転されるも、最終戦ではV・ロッシが転倒し、再度逆転するというドラマチックなエンディングで、ライダーズチャンピオンに輝いたのである。最終的にはN・ヘイデンの2勝を含むホンダ勢が8勝、ヤマハ(V・ロッシ)5勝、ドゥカティ勢が4勝を記録していることからも拮抗した戦いだったことが分かる。
- :前後輪の回転差を検知してスロットル開度を自動で調整し、ホイールスピンやウイリーを抑制する電子制御スロットル。コーナー立ち上がり時の効率的な加速を実現するだけでなく、減速時にはスロットルを自動で開くことでエンジンをスムーズに回し、エンジンブレーキによるホッピングを抑制する

N・ヘイデンのみに投入された、RC211Vニュージェネレーション