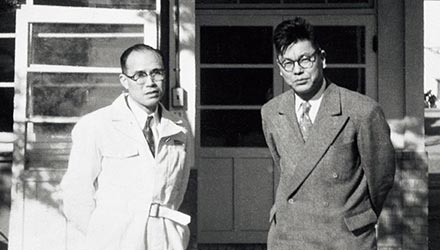スーパーカブという発明
1950年代、国内では新三菱重工業(株)のシルバーピジョン、富士重工業(株)(1952年までは富士産業(株))のラビットといったスクーターが人気だった。ホンダも1954年に当時としては画期的な繊維強化プラスチック(FRP)を多用したボディーや全天候型を目指した装備などが満載のジュノオK型をデビューさせたが、重くパワー不足で、トラブルも多かったため失敗に終わっていた。その直後の1956年12月に当時、社長の本田宗一郎と専務の藤澤武夫はヨーロッパを視察、多くの人がモペッドやスクーターを日常の足にしていることを知り、大衆の足となる二輪車の必要性を再度認識しモデル開発に着手する。コンセプトは「そば屋さんの出前持ちが片手で運転できるバイク」であり「スカートをはいたお客様にも乗ってもらえる二輪車」である。
本田は誰もが乗りやすく経済的な乗り物とするため、またぎやすく快適という要件を満たす構造・デザインを思案。さらに環境にも配慮した結果、燃料タンクをシート下に収めた低いバックボーンフレームに高出力で省燃費、排出ガスもきれいな4ストロークOHVエンジンを水平近くまで前傾させて搭載し、クラッチ操作不要の3速自動遠心クラッチを採用した。
さらに、足元が汚れない樹脂製レッグシールド・オイル飛散を防ぐチェーンケースを採用。また、乗り心地が良く悪路でも安心感のある、スーパーカブC100のためにつくってもらった専用サイズの17インチ大径タイヤも採用し、生活のためのバイクとして完璧ともいえる内容を実現していた。試作車を見た藤澤は「3万台売れる」と言い、その場に居合わせた若手のデザイナーが「年間で?」と思わず聞き返すと、藤澤は「月間で」と言い放ったという。国内二輪業界全体での生産台数が月42,000台程度であった当時ではあり得ない数字だったが、藤澤のビジネスマンとしての直感が判断した。

機能を追求し尽くした美しさを持ったスーパーカブC100
スーパーカブが素晴らしかったのは、その装備や性能だけではなく、機能を追求した本当の機能美を持っていることだった。機能や要求を十分に満たしてまとめていけば、プロダクトデザインは結果的に素晴らしい形になる。当時の本田はこのようなことも言っていた。「バイクの姿が良ければ必ず内容、すなわちエンジンの構造や機能も充実していると思う。私は上品で、端正で、少し色気がある姿が好きだ」
1958年にデビューしたスーパーカブC100は、まさに当時の社是「わが社は世界的視野に立ち、顧客の要請に応えて、性能の優れた、廉価な製品を生産する」を具現化する空前のヒット商品となった。この年の8月発売だったこともあり、同年の生産台数は約24,000台だったが、翌1959年は約167,000台に拡大。1960年には「月産5万台のスーパーカブ。ホンダ新工場建設」とうたった鈴鹿製作所が稼働し約564,000台、1961年は約661,000台、1962年は約79万台と藤澤の予想をはるかに上回る売れ行きを記録し、ホンダが企業として世界へ躍進する原動力となったのである。「良品に国境なし」という本田の言葉通り、その後スーパーカブは生産拠点を世界15カ国に広げていった。
1964年にはスーパーカブシリーズとして初めてOHCエンジンを採用したC65を、2年後にはOHCエンジンを搭載した49ccのC50を発売。このOHCエンジンにより、C100系のOHVエンジンに対し、動力性能・燃費・耐久性のすべてを向上させ、新たに「2年5万km保証」制度を設けたことで、その人気はさらに爆発的となり累計生産台数は500万台を突破。
その後C65をマイナーチェンジし排気量を72ccにアップしたC70と89ccのC90を発売。C65で設計されたOHCエンジンは、2000年代のキャブレター仕様の最終モデルまでベースエンジンとして使われ続けた。また、モンキーやダックスといったレジャーバイクや、ベンリイシリーズ、さらにはビジネスモデルCDなどのベースエンジンとしても搭載され、ホンダの小型二輪車のラインアップ拡充に大きく貢献した。

鈴鹿製作所で出荷を待つスーパーカブ

OHCエンジンを搭載したC50を皮切りにシリーズ化されていったスーパーカブ
アメリカにおける二輪車のイメージを変えたCA100
1959年、ホンダは海外展開の足掛かりとして、初の海外販売会社であるアメリカン・ホンダ・モーター(AH)を設立。1962年には真っ赤なボディーカラー、2人乗りが可能なロングシートを装備した北米向けHONDA50 CA100を発売する。セルスターター付きCA102・55cc版CA105もラインアップした。
1963年には「YOU MEET THE NICEST PEOPLE ON A HONDA」の広告キャンペーンによって、当時のアメリカ人のバイクに対する「ブラック・ジャケット(アウトローの意味)」というネガティブイメージを払拭、若者を中心にそのライフスタイルまでをも一変させた。
3速自動遠心クラッチによるエンジンの軽快な走行感、そしてバイクで移動する爽快な楽しさは、ビーチボーイズやホンデルスの「LITTLE HONDA」という歌唱曲にもなったほどである。また、ロードスター・ラリー・ボス・スチューデントといったスタイルのバリエーションも展開され、スーパーカブは多くの若者たちの心を引きつけた。
さらには狩猟や釣りといったアウトドアを楽しむレジャーモデルを投入し、より幅広いユーザーへの波及を行った。チェーンの掛け替えで2次減速比を変更できるダブルスプロケットやブロックタイヤなど、オフロード走行を考慮したヘビーデューティーな装備を持ったCA100Tトレール50を1961年に発売。さらにアップマフラー仕様のCA105T・90ccのCT200へと進化した。
また、1966年発売のCT90トレールの後期モデルは4速+4速の副変速機能が採用されたモデルへと進化。このノウハウを元に1968年には日本でC50の派生モデルであるCT50ハンターカブが誕生し、これらが後のハンターカブの源流となったのである。

アメリカでのバイクに対するイメージを一新させた
HONDA50 CA100

アップマフラー仕様のレジャータイプ CT200トレール90
アジアの国々でも愛されるスーパーカブシリーズ
北米・欧州に続き、スーパーカブはアジア圏に進出し、1961年に台湾でノックダウン生産を開始した。タイでは、タイ・ホンダ・マニュファクチュアリング(TH)が1967年からスーパーカブを現地生産。1980年代になるとC70とC90という東南アジア専用モデルを生産し、同クラスのモデルと比べ、使い勝手の良さと低燃費・高い耐久性によって支持を獲得。1986年にはスーパーカブタイプのドリームを発売。
1995年にはタイ市場のさらなる活性化に向け、性別や世代を問わずモダンなデザインを採用したスーパーカブタイプのWaveを新開発、新たなヒット商品へと成長させた。スーパーカブの流れを受け継ぐベーシックなデザインのドリームと、モダンでスタイリッシュなデザインのWaveというタイ生産のスーパーカブシリーズが、東南アジア全域のみならず南米などへも展開され、各地域のニーズに合わせて進化していく。
2000年代に入ると、ユーザーのニーズに応えてWaveなどのスポーティーモデルは液晶オドメーターやシャッターキーなどを装備。さらに2003年にはWave125iで世界のスーパーカブシリーズに先駆け、PGM-FI(電子制御燃料噴射装置)を搭載。幅広い走行環境においても快適な始動や力強くスムーズな乗り心地と低燃費を実現した。

タイで生産したアジア専用モデル C70
スーパーカブ天国・ベトナム
ベトナムへスーパーカブを輸出したのは1965年、当時は南ベトナムだった現地のインポーターからの2万台の注文を受けてのことであった。ベトナム戦争の最中にも戦火を逃れるために、スーパーカブに家族と家財を載せて逃げ延びた人々も多く、スーパーカブの信頼性は広くベトナムの人々に認識され、以後スーパーカブシリーズはベトナムの人々の生活必需品として位置付けられ、バイクもスクーターもモペッドも、メーカーを問わず、二輪車のことは「ホンダ」と呼ばれるようになった。

南ベトナムへ輸出されたスーパーカブその信頼性から二輪車のことは「ホンダ」と呼ばれるまでになった
ベトナムにおいて「ホンダ」は、いつの時代も人々の夢であり、家族の大切な共有財産であったが、中でもスーパーカブはステータスとされた。そのようなベトナムで特に普及したのは、主に隣国ラオスから輸入されたタイホンダ製と日本製のスーパーカブシリーズだった。
1996年にはホンダベトナムカンパニー・リミテッド(HVN)が設立され、翌年以降からは現地の人々が夢にまで見た、初のベトナム製二輪車であるスーパーカブタイプのスーパードリームの生産販売をスタート。バイクタクシーとしての需要もあるお国柄により、タンデムライディングを重視した構成となっていた。ベトナムにおいてスーパーカブシリーズは、1965年から半世紀にわたりベトナムの人々の暮らしに寄り添う商品となった。2020年には、HVN全生産数3,000万台の中で約40%の生産台数を誇った。

ベトナムで生産されたスーパードリーム
中国内需から世界へ拡大したスーパーカブシリーズWave
1980年代から社会と産業の多様化が始まった中国において、ホンダは1981年の嘉陵工業(後の本田動力〈中国〉有限公司)との技術提携で市場進出の足掛かりを築き、中国政府が開放政策を本格化させた1990年代初頭には、五羊-本田摩托(広州)有限公司(五羊ホンダ)・天津本田摩托有限公司(以下、天津ホンダ)・嘉陵-本田発動機有限公司(嘉陵ホンダ)という3つの合弁会社を設立。100ccのスーパーカブや100ccから125ccクラスのモーターサイクル、125ccクラスのスクーターなどの生産を行い、日本からの輸入車と同じ製品を中国のお客様に値ごろ感を与えられるレベルまでコストダウンを図った製品づくりをしている。日本メーカーの二輪車は中国ユーザーにとって憧れの的で、とりわけホンダ製の二輪車のブランドイメージは高い。しかし、皮肉にもその人気を反映してコピー商品が大量に製造され、それらが東南アジアに輸出されるまでになってしまった。その数は200社以上ともいわれていた。
そこで、天津ホンダはまさにホンダのコピー製品を製造していた中国の有力二輪メーカーである海南新大洲摩托車股份有限公司の二輪事業部門と合弁し、新大洲本田摩托有限公司(以下、新大洲ホンダ)を設立することで、当時世界で最も多くの二輪車を生産していた中国での覇権を確立しようとしたのである。敵の敵は味方という逆転の発想だったともいえよう。
新大洲ホンダは2002年にはWaveを生産・販売。たちまちベストセラーモデルとなった。WaveはASEAN*1モデルと同様の先鋭的フォルムに、4速ミッションと97.1ccエンジンを搭載し、寒冷地での使用を考慮したキャブレターヒーターなども設定。特に男性が出稼ぎで不在となる農村部の女性や高齢者にとって、乗りやすく壊れにくい日常の足として支持されたのである。Waveは世界各国へも輸出された。また、2012年に日本向けにフルモデルチェンジしたスーパーカブ50・110を生産して輸出を開始し、2017年10月まで日本に輸出された。
- :Association of South-East Asian Nations 東南アジア諸国連合

中国から世界各国へも輸出された、新大洲ホンダ生産・販売のWave