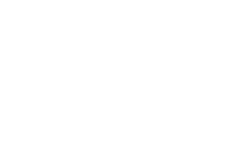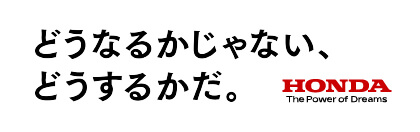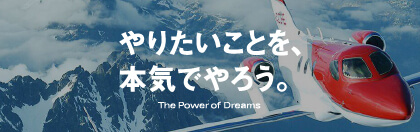Innovation 2024/06/10
松明は自分の手で──新事業開発は、未知なる領域を突き進む冒険
「すべての人に、『生活の可能性が拡がる喜び』を提供する」という2030年ビジョンを掲げているHonda。これまで培ってきた技術力とさまざまなプロダクトを持つ強みを活かし、次々と新たな事業に挑戦しています。ゼロから新事業を生み出すべく奮闘する3人に、Hondaで事業開発に挑むやりがいを聞きました。

石岡 康平Kohei Ishioka
コーポレート事業本部 コーポレート事業開発統括部 新事業開発部 先行企画ドメイン
大手航空会社で経営企画、グループ会社再編、新規事業開発などに従事した後、大手通信会社でスマートシティの事業開発に携わる。2022年8月にHondaへキャリア入社。オンデマンド配車サービスの事業開発に携わった後、EVバッテリーを活用した新たな循環型ビジネス構築に取り組んでいる。

大石 俊介Shunsuke Oishi
コーポレート事業本部 コーポレート事業開発統括部 新事業開発部 先行企画ドメイン
大手飲料メーカーで営業を担当後、マーケティング部に異動し、健康分野における新規事業を担当。2022年8月にHondaへキャリア入社。HondaJetシェアリングサービスの事業立上げプロジェクトと並行して、原付バイクの体験価値に着目したモビリティーサービスの新規事業に取り組んでいる。

伊藤 ジュリアン海Julien Kai Ito
コーポレート事業本部 コーポレート事業開発統括部 新事業開発部 先行企画ドメイン
金融領域、エンターテインメント領域の企業で、既存サービスをローカライゼーションする海外展開、海外営業を担当。新規事業開発の知見を広げるため通信制の大学に通った後、2020年6月にHondaへキャリア入社。入社以来、電動垂直離着陸機「eVTOL」の事業開発に携わっている。
自分で掲げた目標はやりきる。チャレンジを続けるHondaイズムに惹かれて入社

石岡、大石、伊藤が所属するコーポレート戦略本部 新事業開発部は、社会課題やお客様のニーズにHondaが持つ幅広いプロダクトと技術力を掛け合わせることで、新たな事業のタネを作り出し、育てていく部署。
四輪、二輪、パワープロダクツといった既存領域にこだわらず、次のHondaを担う事業領域を探し出して形にしていくことをミッションとしているため、メンバーのバックグラウンドも多彩です。
 石岡
石岡
「私は新卒で大手航空会社に入社しました。そこで新規事業開発に従事したことをきっかけに、『もっと人びとの生活に密着した領域で事業開発に挑戦してみたい』と考えて通信会社に転職。スマートシティやMaaSといった領域で事業開発に取り組んでいました。
そのなかで人びとの生活を考えていると、最終的に行き着くのは『移動』なんです。そこで、移動を日常的に支えているクルマやバイクをはじめとした幅広いモビリティを開発しているHondaに転職しました」
 大石
大石
「私の前職は大手飲料メーカーです。営業やマーケティングに携わった後、健康分野で新規事業に挑戦し、社内外から評価していただきました。
Hondaに転職したのは、大好きなF1がきっかけです。2021年、レッドブル・レーシング・ホンダが優勝しました。Hondaにとっては30年ぶりの栄冠。さまざまなメディアでHondaの技術者たちの想いが紹介されていたのを見て、心を動かされました。
もともとHondaという会社に憧れはあったものの、私のキャリアとは業界が異なるため、自分が働くというイメージはありませんでした。しかし、Hondaが変革期を迎えていて、新規事業を生み出せる人材を求めていると知り、私も貢献できるかもしれないと飛び込みました」
 伊藤
伊藤
「私は、ずっと海外で仕事をしていました。既存事業を海外展開するためのローカライゼーションに取り組んでいたのですが、だんだんと新規事業に興味を持つようになったのです。そこで、イノベーションマネジメントを勉強するために通信制の大学に3年間通い、転職しました。
転職活動で応募したのはHondaだけ。理由は2つあります。1つめは、Hondaは常にイノベーティブな会社であること。これまでの歴史を見ても、いつでもチャレンジして新しいものを生み出してきている。その精神は入社した今も感じます。
2つめは、私の生活には常にHondaの製品があったこと。最初の記憶は、父が乗っていた黄色のCITYです。身近にある製品を作っている会社で、イノベーションを起こしたいと思ったのです」
伊藤が惹かれたイノベーティブな風土、世のため人のために情熱を燃やし続ける「Hondaイズム」は、石岡と大石が入社を決めた理由でもあります。
 石岡
石岡
「Hondaに受け継がれる『松明は自分の手で』という言葉が好きなんです。未開の地を自ら切り拓いていこうという意味なのですが、これは事業開発にもつながりますよね」
 大石
大石
「私もその言葉が好きですね。自分で掲げたことをやりきるのは苦しいことですが、新しく何かを立ち上げて突き進むことが好きなので、フィロソフィーに共感してHondaへ入社したことは良かったなと今も思います」
空飛ぶクルマ、エネルギー、電動バイク。多彩な領域でHondaの技術を市場に届ける

新たな事業のタネを生み、育てる新事業開発部は、宇宙、航空、エネルギーなど扱う領域も多種多様で「百貨店のようだ」と石岡は話します。無限に広がる領域で、Hondaの技術をマーケットに照らし合わせて事業にしていくのが3人の仕事です。
 伊藤
伊藤
「私は入社以来、Hondaの研究・開発をリードする本田技術研究所と連携して、電動垂直離着陸機『eVTOL(イーブイトール)』の事業化に向けた事業開発に取り組んでいます。
事業戦略を練り、事業化した際にどんなニーズや使い方があるかという仮説を立てた上で、お客様となる人たちにヒアリングしながら検証していくというサイクルを繰り返しています」
空飛ぶクルマと言われるeVTOL。世の中にまだない事業を作っていくからこそ、その難しさに直面していると伊藤は言います。
 伊藤
伊藤
「検証を繰り返していくことで、仮説の解像度を徐々に上げていくことが大切です。お客様の層やニーズをブラッシュアップして、事業の方向性を見定め、可能性や真価を見出すことが、今やるべきことだと考えています」
石岡が取り組んでいるのは、新たなエネルギー事業の構築。電気自動車(EV)のバッテリーという希少な資源を車載用から定置型蓄電池にリパーパスして活用する仕組みを構築しようとしています。
 石岡
石岡
「カーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーの普及が必要となりますが、発電可能な時間と電気を使用する時間との間にギャップがあり、再生可能エネルギーを十分に活用しきれていない状況があります。蓄電池を活用し、そのギャップを解消する電力事業の構築に挑戦しています」
事業として成り立たせるためには、すべてを自社で行うのではなく、同じ目的を共有できるパートナーと共創することで、Hondaが持つ強みを最大限に発揮させることもポイントです。
 石岡
石岡
「Hondaには優れた技術がありますが、技術があるだけでは『新たな事業』を起こすのは難しい。そこで、ターゲットとなる市場のノウハウを持つパートナー企業と共に、事業化をめざしています。
仕事をする上で私がよく行うのは、『自社のあるもの探しとないもの探し』。Hondaのなかには本当にさまざまな技術や知見がありますが、異なるバックグラウンドをもってHondaにキャリア入社した目線で見ると、十分に活用されていない技術や知見もあります。
そのため、まずは自社のなかでできることを徹底的に探す。それでも見つからなければ、それを持っている企業とシナジーを生める方法を考えます」
大石が企画したのは、既存領域である二輪の価値を高める事業。企画のタネは、自身の体験でした。
 大石
大石
「新事業開発部ではHondaのさまざまなアセットを活用し、自由に企画を提案できる良さがあります。私自身、HondaJETのシェアサービスの事業化メンバーとして活動する傍ら、入社後初めて乗車したバイクの魅力に感動し、自ら企画を立ち上げました。
バイクに乗ると、自然や地域の風を肌で感じて『この街って、こんなに魅力的なんだ!』と知ることができる。私の原体験から、同じように共感してくれるお客様がいるのではないかと考え、多くの方が運転できる原付一種クラスの電動バイク『EM1 e:』を活用したモビリティサービスを企画。ホンダモーターサイクルジャパンや全国の販売店、さらには地域のプロスポーツクラブなどと協力しながら進めています」
この事業は、二輪のトップメーカーというHondaの強みを活かせるものだと大石は続けます。
 大石
大石
「具体的にサービス設計を始めると、全国各地にさまざまなアセットがあり、とてもスピード感をもって実証検証を重ねられています。これは、Hondaが蓄積してきた資産やブランドがあるからできることだと思います。バイクの楽しさを多くの方たちに広められるサービスとなるよう、日々多くのステークホルダーと共に考えをめぐらせています」
関連記事はこちら▶
空飛ぶクルマをつくる!Honda eVTOL用パワーユニット開発に挑戦する技術者一人ひとりの想い
「エネルギー発展の歴史の一部になりたい」EVを活用した新たなバリューチェーンを構築
挑戦を後押しする風土があるから、胸を張って“出る杭”になれる

Hondaのなかにあるプロダクト、先進的な技術、社会ニーズ、自身の体験など、さまざまなところに眠っている事業のタネを見つけ、育てていくことが楽しいと語る3人。事業化するまでに長い期間がかかることもありますが、未開の地を進むことがモチベーションになっていると話します。
 伊藤
伊藤
「探検家になった気分になれるんです。自分で課題を設定して、解決策を模索し、周りの人たちと力を合わせながら解いていく。誰かが教えてくれるわけではないので、自分で考えながら答えに近づいていくことがおもしろいですね」
 大石
大石
「よくわかります。私も答えが見えないことに挑戦するのが好きなんです。少人数で始めても、成果が出るにつれて仲間が増えていく。だんだん一体感が生まれてくるのが醍醐味ですよね。
今回の事業も、最盛期に比べて大きく販売台数が減少している原付一種のカテゴリーということで、お客様がいるのか懐疑的な目もありました。けれど、利用した方に想像以上に感動してもらえた結果から、社内だけではなく、地域の企業や飲食店などが事業の可能性を信じて集まってくれています」
 石岡
石岡
「伊藤さんは探検に例えていましたが、私はスポーツにも近いと思っています。練習のように過程は楽しいことばかりではないけれど、続けていくうちに『昨日よりは今日』と日々新たな発見が生まれる。
最終的な結果の良し悪しはありますが、やった分だけ達成感が得られ、自分の成長につながる実感があるから頑張れるんですよね」
新たな事業は、うまくいくことばかりではありません。それでもチャレンジングな事業に挑戦できるのは、Hondaならではの風土があるから。
 大石
大石
「チャレンジした経験のある人が多いんですよね。意見や考えに賛同するかどうかは別として、チャレンジする気持ちを受け入れてくれる。だから、堂々と“出る杭”になれるのだと思います」
 石岡
石岡
「キャリア入社だからという垣根もなく、自由に発言できる雰囲気もありますよね。新しいことを始める時に、『あなたはどうしたいの?』と必ず聞かれます。経営的な判断のポイントはありつつも、社員の意志を尊重する文化を感じます。それは、これまでも数々の新規事業に取り組んできた会社だからこそ根付いている風土かもしれません」
 伊藤
伊藤
「あとは、パッションが強い人が多いと思います。一人ひとり、自分の信じていることを持っていて、太い芯があるんです。だから、本質的な議論が求められます。年齢や職位にとらわれずに議論しあうワイガヤなど、話しやすい環境があることも大きいと思います」
アイデアを具現化できる技術力を活かし、Hondaの可能性を広げる

イノベーションを起こし続ける姿勢のほか、キャリア入社した3人が感じるHondaの魅力は、その技術力。アイデアが生まれた時に、それを具現化する力が会社にあることは、大きな強みだと話します。
 大石
大石
「私はF1の技術者の姿に感動して入社したので、彼ら彼女らが作ったものを広めて、一緒に世の中を変えていきたいんです。Hondaには、まだ知られていない素晴らしい技術がありますから、これまでの私のキャリアを活かして世の中に少しでも影響を与えるサービスを生み出したい。実は、すでに構想しているプロジェクトがいくつかあります」
技術力を活かし、「移動」と「暮らし」の進化をリードすることがHondaのミッション。「移動」が転職のキーワードだった石岡は、その価値を広げる事業にも挑戦したいと意気込みます。
 石岡
石岡
「移動することは、人間の本質的な欲求だと思っています。超高齢社会となった日本で、移動を持続的に便利にしていくサービス、移動に関する制限を解放していくサービスを、Hondaを通じて世の中に出し続けていきたいと考えています」
空飛ぶクルマの事業化に挑んでいる伊藤は、自分のような「Hondaファン」を増やしていきたいという夢を抱いています。
 伊藤
伊藤
「新規事業というのは、新たな課題を解決することによって今までになかったお客様を見つけることだと考えています。自分が携わる新事業を通じて、一人でも多くのHondaファンを作りたい。そのために、私は新たな価値の提供にチャレンジし続けたいと思います」
Hondaに受け継がれてきたイノベーティブな精神とチャレンジする土壌。その環境に多様なキャリアを融合させ、Hondaに眠る無限の可能性を広げていきます。
※ 記載内容は2024年5月時点のものです