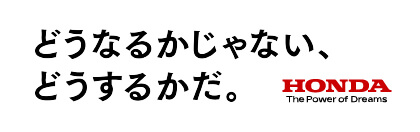Innovation2020/08/03
“楽しさ”を希求し、自由に駆ける。Hondaが示す発想力の可能性
最先端技術の最果てを見た男が真に求めたもの——それは、心を躍らせる“楽しさ”でした。Hondaの荒木 真は、バイク自身が自立するというHonda Riding Assistの開発責任者。彼のキャリアや仕事観から、Hondaらしさをご紹介します。

荒木 真Makoto Araki
二輪事業本部ものづくりセンター 将来技術開発部 将来戦略課
Honda Riding Assist(自立するバイク)の開発責任者として、コンセプトの企画から開発までを推進。
Hondaマンらしい熱い想いと、こうなったらいいなという夢を持つ。
一風変わった少年が、世界レベルの研究競争を経て行き着いた場所

スーパーファミコンの全盛期に、プログラミング雑誌を見ながらゲームを自作していた。
バイオリン演奏の音の探究にのめり込み、最終的には楽器を自ら製作してしまった。
正直、相当変な子どもだったと思う。
荒木 真は、少年時代をそのように振り返ります。
荒木 「父親もかなり変わった人でしたね。大学教授だったんですが、地球物理学者だったはずがいつの間にか電子情報工学科にいたりして。興味のあることにまっすぐ突き進む性質は、私も受け継いでしまったようです(笑)。
前職はナノテクノロジーの研究者でした。端的に言うと、ICチップの性能を上げるために、シリコンウエハ上に“いかに細い線を書くか“という一点を追求する仕事です。技術革新の隆盛期で、自分の研究が世界のスタンダードになるかもしれないという可能性が情熱のすべてでした」
最先端の技術研究に励む日々を送っていた荒木。
ところが、その挑戦は思いがけないかたちで終焉を迎えることになります。
荒木 「電子回路の性能を高めるために線の細さを追求する研究を続けていたわけですが、ある発見を機に文字通り桁違いに細い線が書けるようになり、線幅が細くなり過ぎて電子が常温では通過できないレベルに到達してしまったんです。
つまり、それ以上の研究を進めても製品としての電子回路には応用できないわけで、『一体なんのために研究するんだ?』と、目指すべき指標が失われてしまいました。ハイレベルな“すごさ“を競うことは、技術研究を加速させるアクセルになります。
とはいえ、それは一過性のものでいつか必ず別の人、別の技術に超えられてしまう。あるいは、まったく別物の技術に置き換えられて必要とされなくなってしまう。私のように突如行き詰まることもあります。それってむなしいな……と」
そして荒木は“すごさ“の対義語は“楽しさ“だ、と考えるようになりました。
荒木 「たとえばいわゆる趣味って、必ずしも新しさやレベルの高さを競うものではありませんよね。本人が楽しければ、優劣とは無関係に続いていく。“すごさ“を競う研究者として走り続けてきましたが、自分は一過性の研究ではなく、誰かの喜びや楽しさに役立つ技術に携わりたい。そんな想いが芽生えたんです」
誰かの楽しさに貢献する仕事に就こう。そこで、あらためて自分の進むべき道を見つけよう。
そう考えた荒木が選んだ次なるフィールドがHondaでした。
8割の反対が成功の入口?クセの強い猛者がそろうHondaとは。
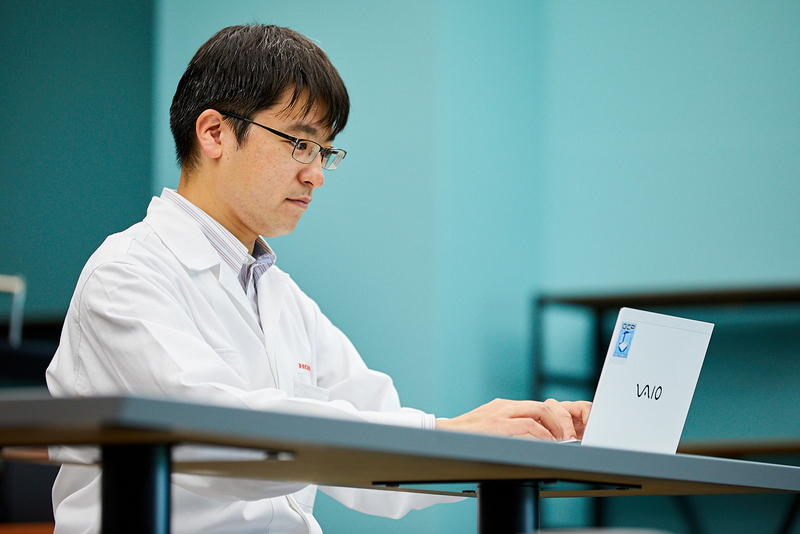
バイクや自動車、耕うん機や芝刈り機といった生活に根差した製品から、航空機や最先端のロボティクスまで。
いわずと知れたHondaブランドのもと、多様な事業を展開するものづくりの会社です。
入社した当初、荒木には当時の上司から幾度となく言われた言葉がありました。
荒木 「それは『先行開発は8割に反対されるくらいのネタがちょうどいい』。私は、これこそがHondaを表し、かたちづくる言葉だと考えています。やるからには普通じゃないことをやりたい、というHondaの志向性を絶妙に言い表しているというか。
大多数が賛成することはきっと誰かがやっているから、あえてHondaでやる必要はない。一方、全員が反対することは、本質的に間違っている可能性が高い。この“8割が反対”は、Hondaとして挑戦する価値があるかどうかを判断する重要な思想だと思います」
また、反対には意見がある、というのも重要な考え方です。
あえて反対するからには、必ず理由がある。興味もある。明確な意志がなければ、人は意志表示さえしないものですから。
「反対する人こそ仲間に引き込め。そして、反対できなくなるまで前進できたとき、その取り組みはすでに成功している」というのが、荒木がたたきこまれた上司の教えでした。
このスタンスからは、Hondaの社風も垣間見えてきます。
荒木 「反対する人を仲間に取り込むくらいですから、良くも悪くも自由な会社だと感じています。誰かが本気で『やりたい!』と声をあげたら、それを頭ごなしにやめさせる人はいません。
前のめりで突き進めばやりたいことができる会社というか、逆に言うと、受け身でいたら何も始まらない。主体性や行動力が求められるのが特徴的ですね。社員レベルでいえば、自分自身の行動に信念と誇りを持っている人が多いと感じます。
反対意見の話にも通じますが、それは自分の知識やノウハウに基づいて論理的に判断した上での反対ですから。いうなれば、きちんと向き合ってヒントをくれているのだとも受け止められますよね」
技術も実績もある猛者が集う会社だからこそ、想いを語るときには歯車がかみ合わないことも起こります。
だけどそのぶつかり合いの中でこそ、Hondaらしい開発やイノベーションが生まれているのもまた事実。
その一例が、荒木が開発責任者を務めている Honda Riding Assistです。
バイクの固定概念を覆すまったく新しい挑戦にも、“楽しさ“を追求する技術者たちの本気が息づいていました。
バイクの可能性を本質から追求するHonda Riding Assist

Honda Riding Assistは、ひと言で表すと自立するバイクです。
これはバイクの前提を根底から覆す斬新な発想なのですが、その技術開発の根底にあったのも、楽しさを追求するHondaらしいスタンスでした。
荒木 「始まりは『もっと気軽に大型バイクに乗ってほしい』のひと言に尽きます。『自立するすごいバイクをつくろうぜ!』ではなく。自立は、あくまでも結果的に生まれてきた副産物なんです。
私自身、バイクに乗るのが好きなんですが、大型車って楽しいけど気を使うんですよね。それはいわゆるお年寄りや女性には重たいといった角度の話ではなく、誰しもが感じることだと思います。
たとえば、行き先が100メートル先のコンビニなら、わざわざ大型バイクを引っ張り出すより自転車で行っちゃいますよね。このとき必要とされる気楽さを、バイクで実現したかった」
バイクがもっと気楽な乗り物だったら、人間はもっと自由になれる。
そのためには、どんな解決策があるのだろう?
この発想こそが、Honda Riding Assistが生まれるきっかけだったのです。
もちろん、抽象的な問いはそれだけ難易度が高いということ。
固定概念のせいで、自分たちはバイクの可能性をあきらめていないか?
バイクはまだまだ進化できるはず、でも、バイクの進化って何だ?
技術開発のずっとずっと前段階のレベルから、議論が重ねられていきました。
荒木 「今なおその議論は続いているのですが、業界の常識の壁を壊すために事業部横断的なチームを立ち上げました。私はその開発責任者を務めたわけですが、とにかく最初は会話が全然成り立たなかった(笑)。
同じHondaの技術者とはいえ、『乗り味っていうのは……』とライダーの感性を主体に語る人たちもいれば、『ライダーの動きで自立制御が……』と車体を主語に語る人たちもいる。Honda Riding Assistの開発チームはそういった人たちの集合体なので、議論がうまくかみ合って回りだすまでは大変でしたね」
荒木の役割は、分野の異なるプロフェッショナルの想いをぶつけ合わせ、歯車を回すための調整役。
決断すること、最後の責任をとることというふたつの肝を担った他は、自由な議論や試行錯誤をチームメンバーに推奨しました。
「戦隊ものでいうところの、強気なレッドとロジカルなブルーばっかりのチームで、私はもめたときに間に立つグリーンの役回り(笑)」と、荒木は言います。
強烈な個性が出会い、かみ合った中で生まれたHonda Riding Assist。
そこには、究極まで楽しさを追求するHondaの姿勢や、深遠な命題にも果敢に挑むプロ気質が爆発的な推進力として存在していたのです。
新たな知識と挑戦と共に生きる。限りない自由さの先を見つめて

知識の海を泳いでいるマグロ。
荒木は、周囲からそんな人物だと評されます。
荒木 「マグロって、寝ている間も泳いでいないと呼吸できなくて死んじゃうらしいんですよね。酸素を取り込むために泳ぎ続けないといけない、難儀な生き物。
でも、私は周りから見ると、新しい知識を取り込み続けていないと死んじゃう人に見えているらしくて(笑)。確かに、落ち着きがないのは昔からだし、型の決まったルーティンワークを粛々とこなすといった仕事は苦手で……。
目の前にある問題や課題の内容を把握して、それを解決する手立てを見つけて、また次の新しい挑戦に移っていくという今の仕事は、自分の性に合っているんだと感じています」
飽きるとか飽きないとか考えている間に、どんどん別の挑戦をはじめてしまえばいいんじゃないの?
シンプルで、だけど破天荒なスタンスにも、Hondaらしさはあまさずにじみ出ています。
荒木 「強い想いを持った人がいて、その人がなんとしても実現したい!と思って行動して、誰にも止められなくなって実現してしまう……ということが起こりえる自由さこそ、Hondaの強みだと感じます。
そのモチベーションが、私の場合は楽しさの追求だった、ということ。表現がちがったとしても、製品を通じてお客様の喜びを追い求めることが開発のモチベーションという点は、Hondaに集う誰しもの共通項じゃないでしょうか」
Honda Riding Assistは、まだまだ基礎研究を進めていく段階。
しかし、その先に広がるバイクの新たな可能性を思い描けば、おのずと前進し続けるための原動力が生まれ、進むべき道筋も見えてきます。
荒木 「もとより“すごさ“を狙っている会社ではないので、アウトプットとしての製品の裏にある研究開発力やがんばりをアピールする人が少ないんですよね。
しかも、自由な分だけしくみが全然システマチックじゃないし、なかなかそのがんばりを発信できない不器用さも含めて、Hondaらしさなんじゃないかと(笑)」
「Hondaは、バイクを立たせちゃうようなアホがたくさんいる会社」と言って笑う荒木の表情からは、自由な社風の中で楽しさを追求し続けるHondaの技術開発者としての誇りと喜びがあふれていました。