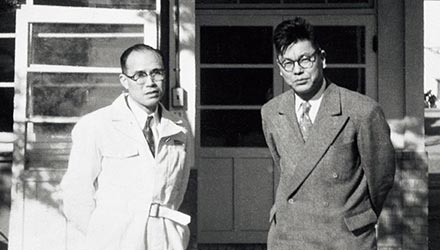終戦後、人の役に立つ乗り物づくりのために創業
終戦後、本田宗一郎は旧陸軍の無線機発電用エンジンを自転車の補助動力に使うというアイデアを思い付き、本田技術研究所を設立し、自転車用補助エンジンの製作と販売を始めた。払い下げのエンジンの在庫が底をつくのは時間の問題であり、オリジナルのエンジン開発に着手。試作を重ねて初の自社製エンジンA型が完成し、1948年の本田技研工業株式会社創業に至った。道路事情も悪く、一般の人々は移動手段を人力に頼らざるを得ない時代に、ホンダはエンジン動力を使った乗り物をつくるメーカーとして創業した。そこには「困っている人の役に立ちたい」という強い想いがあった。
1949年、ホンダはフレームから全て自社製のモーターサイクルを開発。その名も、「ドリーム」と名付けられたドリームD型である。本田宗一郎の「世界一になる」という夢の実現に向けて歩み始める、記念すべき二輪完成車となった。続いて1951年に発売された4ストロークエンジン搭載のドリームE型のヒットで事業は成長軌道に乗り、本格的な二輪車を製造する完成車メーカーへの足掛かりを固めていく。
スーパーカブC100の誕生
1952年、自転車用補助エンジン・カブ号F型を発売する。全国の自転車販売店にダイレクトメールを送って直販する販売店を募り、ホンダは一気に自前の販売網を構築した。
海外から高額な工作機械を輸入し、先進国レベルの工作精度による高性能な製品を生産する体制を整えたホンダは、これまでにない全く新しい二輪車を生み出した。1958年に登場したスーパーカブC100である。軽量・コンパクトで高出力、商用から通勤・通学・レジャーまで、あらゆる生活シーンを豊かにする乗り物として世の中に提案された。月間販売目標は、当時としては桁外れの3万台が設定され、広告展開にも力を入れた。また、販路を拡大すべく、自転車やモーターサイクルの販売店だけでなく、地域に密着した異業種にも働きかけ、全国に独自の販売網を構築した。
スーパーカブは商用に幅広く活用され、1965年には郵政省に配達業務用に採用された。郵便のみならず牛乳・そば・新聞などの配達や、個人のさまざまな生活シーンでスーパーカブは大活躍することとなり、ホンダは日本の交通インフラとして、新しい価値を創造したと言える。

巨大な販売網により、カブ号F型は日本全国に普及した

スーパーカブC100
憧れの「ナナハン」や身近なレジャーバイクで若者の心をつかむ
1959年マン島TTレース参戦を皮切りに、ホンダは世界の二輪レースに果敢に挑戦した。1966年にはロードレース世界選手権(以下、世界GP)史上初の5クラス完全制覇でメーカーチャンピオン獲得を果たすなど、高い技術力を国内外に証明した。
レースマシン開発で培った高出力・多気筒エンジン技術は市販バイクにも生かされ、1969年、ドリーム CB750 FOURを発売。「ナナハン」のニックネームで若者の憧れの的となり、ホンダは大型高性能スポーツバイクをつくるメーカーというイメージを確立する。
一方でスーパーカブやベンリイなど小型実用バイクで定評がある中、本格的スポーツバイクとの中間を埋めるべく60年代後半から70年代にかけて、カラフルなキャンディーカラーを採用した小型・中型のスポーツバイクCB・CL・SLシリーズを展開。これまでのストイックで武骨なイメージが主流のモーターサイクルから一変、若者のファッションの一部として受け入れられ、ホンダは躍進を続ける。
また、当時のホンダは、エンジン付きの乗り物に子供のうちから親しんでもらおうと、多摩テックなど「自ら操り楽しむ遊園地」を展開していた。その遊具をきっかけに、レジャーバイクの原点ともいえるモンキーが誕生した。モンキーやダックスなどは、商用や通勤用とも本格ツーリングとも違う、日常に身近なレジャーバイクという新しいジャンルを創り出した。

ドリーム CB750 FOUR

モンキー Z50M
モータースポーツと安全運転の普及に取り組む
1970年代、急激にモータリゼーションが進み、負の側面として交通事故が急増し、「交通戦争」という言葉も生まれた。また、若者が集団で暴走行為をする暴走族も現れて非行とバイクが結び付けられ、学校が高校生に「免許を取らせない」「買わせない」「運転させない」という「三ない運動」が展開された。これまで自動二輪免許に排気量の区別はなかったが、1975年からは排気量別の免許が導入され、高速道路だけだったヘルメット着用義務が、一般道にも適用されるなど、交通事故抑止のための法整備も進められた。
高性能なモーターサイクルで若者から支持を得て大きく事業を成長させてきたホンダは、モーターサイクル文化の健全な発展と安全運転知識・技術の普及こそが交通事故を防ぐという信念でこの問題に取り組み、1970年に安全運転普及本部を設立。さらに、より安全に、より楽しく二輪車に乗っていただくため、1973年には、楽しく健全な遊び方の普及とユーザーサービスの充実を図り、モーターレクリエーション推進本部を設立した。そこには二輪車トップメーカーとしての社会的責任があった。
また、同年に日本初の本格トライアルモデル、バイアルスTL125を発売。スピードではなく運転テクニックを競うモータースポーツの普及に取り組み、トライアル競技ができるバイアルスパークを全国20カ所以上に用意した。また、モトクロスを楽しむ場所としてセーフティーパークも全国各地に展開。暴走行為とは無縁の健全なモーターサイクル文化の裾野を広げようとしたのである。
1975年、二輪車販売店では「セーフティスポーツショップ(SSS)店制度」を開始した。SSS店では、ユーザーの運転経験・技量を測定する基準を設けて、ユーザーに見合う車種を選定するサービスを提供した。また、各地で安全運転講習会を開催し、販売の最前線での安全運転普及活動を通じて、お客様を守ることに取り組んだ。また、販売店を中心に結成されたクラブは全国に多くあり、年に1回鈴鹿サーキットに集って交流を図り、安全運転の重要性を再確認できる場の提供を行った。
さらに、1978年からは「ホンダモーターサイクリストスクール(HMS)」を開催した。これは、中・大型バイクのユーザーを対象に、セーフティーテクニックやマナーを学ぶ講習会で、鈴鹿・桶川・福岡の交通教育センターで実施された。その後、ワンデースクールが全国展開され、スクーターやファミリーバイクにこれから乗る人を対象に代理店を含め、販売店、ホンダ営業所主催で実施された。

安全運転普及の一環で開催されたホンダモーターサイクリストスクール
新たな需要から生まれたスクーターブーム
1976年、スーパーカブに代わる第2世代のコミューターとして画期的なモデル、ロードパル・シリーズが誕生する。女性ユーザーの使いやすさを徹底的に考えたコンセプトに基づき、操作が簡便で軽量な「自転車イメージのバイク」として開発された。ロードパルは、CMでソフィア・ローレンが口ずさむ「ラッタッタ」が車名の代名詞になるほどの爆発的ヒットとなり、ファミリーバイクという新ジャンルを生み出した。
市場の反響は大きく、新たな市場として他社も参入してきた。ファミリーバイクは学生や主婦層、さらにはライダーのセカンドバイクとしても需要は広がった。「三ない運動」の影響などで逆風下にあった二輪車市場は再び活況を呈し、1980年代のスクーターブームへと発展していく。
この市場拡大を好機と捉えたヤマハ発動機(株)(以下、ヤマハ)は、新製品を次々に投入し、国内市場掌握へと動いた。激しい競合車の攻勢により、ホンダはヤマハと激しいシェア争いを繰り広げることになる。

ロードパル
過激なシェア争い、HY戦争。その反省と学び
1977年、ヤマハは、ロードパルの対抗機種として、フラットなステップが特徴のパッソルを発売すると、ロードパルの販売台数を上回るほどのヒット商品となっていく。
1979年、ヤマハは業界トップを目指すと表明。激しいシェア争いの幕が切って落とされた。いわゆるHY戦争である。
1980年から1981年には、ヤマハのファミリーバイク市場シェアがホンダに肉薄。ホンダはこれまで国内二輪車市場を牽引してきたトップメーカーとして、威信を懸けて迎え撃った。
ホンダは、新たな需要を開拓してシェアを堅持するべく、よりファッショナブルで生活スタイルにマッチする「ザ・スクーター」タクトを1980年9月に発売すると、女性層を中心に爆発的にヒットし、発売後わずか3カ月で11万台を売り上げ、首位の座を守る。
さらに、1981年にはタクト フルマークやタクト フルバック、1982年にはリードやスカイなど、驚異的なペースで新モデルを投入した。互いに一歩も譲らず、販売競争を繰り広げた結果、1982年秋ごろには両社とも大量在庫を抱えることになった。劣勢に立たされたヤマハが1983年1月に販売競争からの撤退を表明し、HY戦争は終結した。
販売の現場は疲弊し、ホンダも痛手を負った。競争が過熱したあまり、創業以来、ホンダが大切にしてきた「三つの喜び」のうち、最も大切なお客様の「買う喜び」を見失い、シェア争いに終始してしまったのだ。結果的に「売る喜び」「つくる喜び」も損なわれたこの経験は、その後のホンダの企業活動における強い戒めとなった。

タクト

タクト フルマーク

リード50 スーパーデラックス

スカイ

日本のお客様と共に。オーナーズミーティング
(株)ホンダモーターサイクルジャパン(HMJ)は「Always the one Honda CB」をキャッチフレーズに、CBオーナーズミーティングを2014年から2019年まで17回開催した。トータルで約1万1,500名の参加があり、参加者の満足度も84%。CBを通してオーナーとの絆を醸成するイベントであった。ほかにも「Hondaオフロード・ミーティング」「ナイスミドルのためのスマートライディングスクール」「Rebel&GBミーティング」などを各拠点で開催。二輪車を楽しむ機会を積極的に提供することで、お客様のロイヤルティー向上に努めている。
若者にバイクで広がる新しい体験を。「HondaGO」
2019年6月にスタートした二輪車市場活性化プロジェクト。その中で、「バイクの乗車体験」として店舗や施設を活用した乗車体験と、SNS、スマートフォンアプリを通した情報発信などのプログラムを実施。

・HondaGO RIDE:全てのライダーのためのバイクライフのサポートアプリ。メンテナンスノート・給油記録による燃費計算・ツーリングプラン作成と記録・バイクレンタル予約・ホンダからの新製品情報やイベント情報などを提供。
・HondaGO BIKE RENTAL:「もっと気軽に、もっと身近に」をキーワードにWEB予約によるバイク貸し出し・ヘルメットやライダースジャケットのレンタル・保険や補償プランなど、準備や費用のハードルを下げ、二輪車に乗るきっかけを提供し、魅力を体感していただくサービス。
・オンライン上の情報発信:ユーザーフォローとして、HondaGO RIDE・HondaGOミュージックビデオ・HondaGO インスタグラム・HondaGO BIKE GEAR・HondaGO バイクラボなど、2023年時点では会員数約7万人で展開。
「ウイング店」で「買う喜び」「乗る喜び」を
かつて自転車販売店を二輪車販売店に育てたホンダは、四輪事業参画にあたり、二輪車販売店が四輪車も併売するという展開で、短期間に四輪事業の基盤を築き上げた。しかし、四輪事業が本格化するにつれ、結果としてそれらの店舗の多くが四輪車専門販売店に移行し、二輪車の販売体制の見直しが必要となった。
1979年、ホンダ二輪車販売で地域のリーダー的な役割を担う専門店「ウイング店制度」が導入された。当時の二輪車販売店は各メーカーの製品を扱う併売店が一般的だった。しかし、多様なニーズに応えて多彩な車種を扱う二輪車販売では、各販売店の拡販活動が販売力を左右するため、ホンダ車だけを扱う店舗が理想である。続いて1982年には、二輪営業所を統廃合して販社を設立。また、代理店は135社から71社体制にすることなどで卸網を強化した。なお、この年に「新ウイング店制度」へと移行した。販売力に加え、整備能力やサービス向上も視野に入れた、お客様の満足度向上が大きな目的だった。当時、他社とのシェア争いが激しさを増して販売の現場も混乱を極めていた中だったが、事業の発展において最も重要な、ホンダの二輪車を「買う喜び」「乗る喜び」を改めて大切にしようという考えに立ち返ったのである。
モータースポーツ人気と技術革新
1967年に世界GPから撤退したホンダは、1979年に再び世界GPへ復帰する。世界GPはテレビでも放映されて人気が高まり、レーシングマシンを模したデザインとスペックのレーサーレプリカというジャンルは一大ブームとなる。レースマシン開発の結果、1980年代に二輪テクノロジーは飛躍的に進化を遂げ、そこで得た最新技術は市販車へもフィードバックされた。
また、モトクロス競技も盛んに開催されて人気を集め、オフロードタイプのモデルも各社から発売された。1990年代にかけてはオンロード・オフロード共にポケバイやミニ・モトクロッサーなどのキッズバイクが盛んになり、それ以降日本人プロライダーも数多く育ち、モータースポーツとしてバイクを健全に楽しむことが浸透していった。
しかしその一方で、1980年代初頭に50cc以下の原動機付自転車が増加した影響から、交通事故が増加したこともあり、1986年に50cc以下の原動機付自転車にもヘルメット着用が義務付けられてスクーターブームに陰りが見え始め、免許取得人口も減少。二輪車を取り巻く環境は厳しくなり、1982年の国内4メーカーの出荷台数328万台をピークに二輪車市場は縮小していく。そんな中、ホンダは、シート下にヘルメットが収納できる機能、メットインを備えたタクトフルマークを1987年に発売。逆風の中にあった原付二輪車市場でヒット商品となった。

メットイン機能を備えたタクト フルマーク