POINTこの記事でわかること
- 普遍的で革新的、親しみやすく特別感のあるクルマとしてCIVICは世界中で愛されている
- 11代目CIVICが、同世代モデルとして「史上初」の2度目、そして同一車種として「史上最多」4度目の北米カー・オブ・ザ・イヤーの受賞を達成
- 開発者の想いが生んだ幻のRSが2024年CIVICのマイナーモデルチェンジに合わせて誕生
グローバルで累計2700万台以上販売され、北米では昨年24万台以上を販売したCIVIC。2025年1月には、11代目CIVICのハイブリッドモデル「CIVIC HYBRID」が、乗用車部門で「2025北米カー・オブ・ザ・イヤー※1」を受賞しました。11代目CIVICは2022年にガソリンモデルで北米カー・オブ・ザ・イヤーを受賞しており、同世代モデルでの2度の受賞は史上初※2です。また、CIVICとしては通算4度目の受賞となり同一車種として史上最多受賞となりました。さらに、日本でも24年9月にマイナーモデルチェンジをし、新グレード「RS」を投入。25年1月には、「CIVIC TYPE R RACING BLACK Package」を発売しています。
今回は、全世界でご好評をいただいている11代目CIVICの開発責任者である明本禧洙 (あきもと・よしあき)の話をもとに、11代目CIVICの魅力に迫ります。
※1 1994年から続く、自動車業界において権威ある賞。前年に北米市場で発売された車種を対象に米国とカナダの選考委員が先進性・デザイン性・安全性・走行性能・顧客満足度などを総合的に評価して選考。
※2 同一車種の同一世代モデルにおける2度の受賞は史上初。2022年以来、2度目の受賞。
史上初・史上最多の快挙! 2025北米カー・オブ・ザイヤー受賞
CIVICは北米においてHondaブランドへの入り口となるモデルであり、Z世代だけでなく、初めて新車を購入する方や、多様な文化的背景を持つお客様に支持されています。
今後は、更にハイブリッドモデルの需要が高まり、2025年にはCIVIC販売台数の約4割をハイブリッドが占めると見込んでいます。
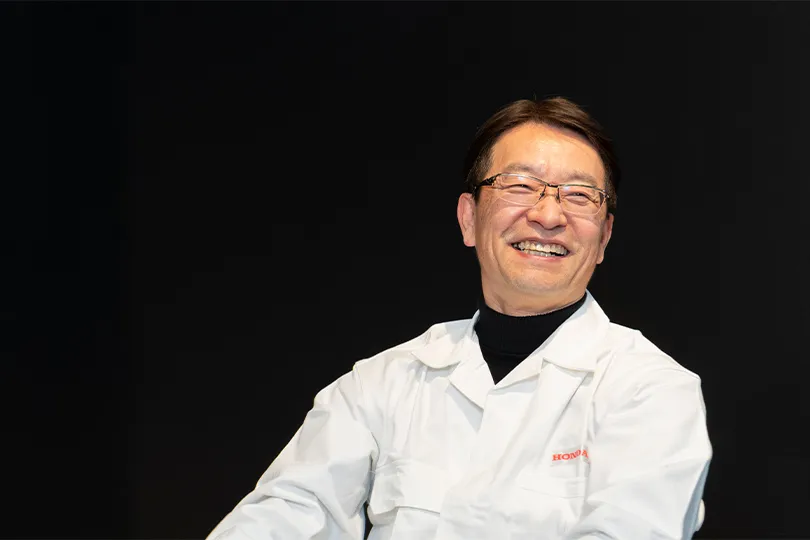 11代CIVICの開発責任者を務める明本禧洙
11代CIVICの開発責任者を務める明本禧洙
昨年11月に北米で発売された「CIVIC HYBRID」が、2025 北米カー・オブ・ザ・イヤーを受賞。同世代モデル(11代目CIVIC)で2度の受賞は史上初、同一車種(CIVIC)で4度の受賞は史上最多の快挙となります。審査に当たったジャーナリストたちから「圧倒的な勝利」というコメントを得た今回の受賞ですが、改めて勝因はどこにあったとお考えになりますか。
 11代目CIVIC開発チーム、北米カー・オブ・ザ・イヤーのトロフィーとともに。
11代目CIVIC開発チーム、北米カー・オブ・ザ・イヤーのトロフィーとともに。
CIVICは1972年に販売を開始して以来、世界170カ国以上で累計2700万台以上を売り上げてきたHondaの主力モデルの一つです。2021年に誕生した現行モデルは11代目に当たり、そのグランドコンセプトは「爽快シビック」でした。改めてこの「爽快シビック」についてお聞かせください。
時代を超えて受け継がれるCIVICの普遍的な“人中心”の価値を継承しながらも、「親しみやすさ」と「特別感」の両立にこだわることで「爽快さ」を表現しています。内にこもるのではなく、外に出て、社会とのつながりを強められるような喜びのパートナーとなるよう開発しました。
「親しみやすさ」と「特別感」は、具体的にはどのような仕様に表れているのでしょうか。
例えば、親しみやすさは大開放の爽快視界。ワイパーがドライバー席から見えないノイズレスで広々とした視界は、乗り込むとすぐにお分かりいただけると思います。
また、同じCIVICのMT(マニュアルトランスミッション)車であるTYPE RやRSといったスポーツグレードでは、伝統的な価値だけでなく、新機能の追加によって快適さも追及しています。停止した際にブレーキペダルから足を離しても自動的に停止状態を維持し、坂道でもラクに発進できるオートブレーキホールド機能、シフトチェンジ時に電子制御で自動的にエンジン回転数を合わせるレブマッチシステムを導入するなど、技術で進化させており、スポーティーな運転が楽しめるだけでなく、快適でスムーズな運転を実現しています。
さらに、2025年1月に発売したTYPE R RACING BLACK Packageでは、爽快な走りに集中できるよう、従来高級車にしか採用されてこなかったスエード素材をインパネとドアの上部に採用するなど、インテリアでも特別感を感じられるようにしています。
 TYPE R RACING BLACK Packageの内装、反射を防ぐ上質なスエード表皮を採用。
TYPE R RACING BLACK Packageの内装、反射を防ぐ上質なスエード表皮を採用。
運転中に光が乱反射するとどうしても気になってしまうので、乱反射する光を極限まで排除してくれるスエード素材をインパネに採用したかったんです。しかし、スエードは伸びない素材であるため、インパネのような複雑な形状に張るには小さくカットした素材を手作業で縫い合わせて形状にフィットさせるなどの手間暇がかかり、大量生産が困難でした。そのため、これまでは一部の高級車でしか使われていませんでした。
今回のモデルでは、Honda独自の機械成型技術を開発し、縫い合わせることなく、1枚のスエード表皮として大量生産することが可能になりました。
実はこの技術、若いエンジニアたちが自ら“やりたい”と手を上げ、開発期間の最速記録をさらに4カ月短縮して実現したものです。強い意志と量産までやり続ける現場力、これを痛感した開発でしたね。
 ノイズレスな視界による走りやすさ、扱いやすさなどで親しみやすさを表現しながらも、インテリアやエクステリアには特別感を施していく。一見相反するように見える「親しみやすさ」と「特別感」を両立し、爽快な走りを実現してきた第11代目CIVIC。写真はシャープなスポーツデザインにこだわったフロント部分。
ノイズレスな視界による走りやすさ、扱いやすさなどで親しみやすさを表現しながらも、インテリアやエクステリアには特別感を施していく。一見相反するように見える「親しみやすさ」と「特別感」を両立し、爽快な走りを実現してきた第11代目CIVIC。写真はシャープなスポーツデザインにこだわったフロント部分。
CIVICは長い歴史を持つHondaの主力モデルの一つです。改めて、CIVICとはどんな特長を持つクルマだとお考えですか?
CIVICの歴史は1972年から始まりました。歴代CIVICの快適な車室空間は、MM(マンマキシマム・メカミニマム)思想という、機械部分は最小に抑え、人間のためのスペースを最大限広くするという考え方をもとに設計されています。このMM思想に加え、キビキビとした走り、扱いやすさ、経済性や環境性といった普遍的な価値を継承しつつも、時代の変化、そして各地域の特性に合わせ、いち早く技術がアップデートされてきたのがCIVICです。
歴史を振り返ると、1950~60年代にクルマが普及したことで大気汚染問題が深刻化し、排気ガスによる光化学スモッグの規制、いわゆるマスキー法が米国で制定されました。この世界一厳しいといわれた規制を、Hondaは画期的なエンジン燃焼技術を搭載したCVCCエンジンで、世界で初めてクリアしました。そのCVCCエンジンを最初に搭載したのがCIVICでした。高い目標に果敢にチャレンジし、先駆けて技術を投入するのはCIVICの普遍性と革新性の両側面を表しているんですよ。
直近でいうと、2024年9月に日本で発売したモデルに搭載したADAS(先進運転支援システム)の渋滞追従モードは、他モデルに先駆けてアップデートしています。 これにより、運転中に先行車との車間距離が詰まりすぎる「ひやひや感」や、逆に走り始めが遅れる「出遅れ感」を大幅に改善しています。
『街乗り最高スポーツ』を作ろう! 開発者の想いが生んだRSモデル

2024年にマイナーモデルチェンジし、日本で発売したCIVICは好評で、中でもMT車のRSモデルは20代のお客様を中心に多くの支持を得ています。軽快かつ意のままに操る喜びの提供を目指したRSは、開発現場からの強い要望で実現したモデルでした。実はこの開発、当初から想定されていたものではなかったと伺いました。改めて開発の経緯についてお聞かせください。
マイナーモデルチェンジの開発が開始された当時、自動車業界では電動化の流れが非常に強く、ガソリン車であるMT車のアップデートをしたいと言い出せる雰囲気では到底ありませんでした。しかし現場の担当者たちは、もっと良いクルマをつくるための改良点やそれを実現できるアイデアを既に思いついていたので、内緒で開発したんですよ。
すべての方に、公道でもご満足いただけるスポーツモデル、つまり“街乗り最高スポーツ”を作りたい。この想いを胸に、チーム一丸となり、走りに重要な部分である、足回り、ステアリング、フライホールの軽さ、ダンパーなどをこだわって改良を施しました。
RS専用として新しい部品や技術を導入するには人的にも金銭的にも多大なコストが必要になります。どのように克服されたのでしょうか。
幸いにしてCIVICは全世界で発売しており、地域ごとに最適な部品を使用し、地域にマッチしたタイプを販売しております。そのような各地域仕様の最も優れた部品を組みあわせることで、開発期間とコストを抑えながらクルマを仕上げることができます。
それを証明するために、密かに開発のエキスパートたちが手塩にかけて磨いたテスト車を1台仕立ててくれました。実際に乗ってみたら、「これはすごいクルマだ」と脊髄反応ですよ。何としてもRSとして実現しよう! そして一刻も早く役員に試乗してもらい賛同を得ようと必死になりました(笑)
役員の反応はいかがでしたか。
「これはすごくいい! 早く市場に出そう」と言っていただけました。そこからは急ピッチで開発を進めて量産体制を構築していきましたね。現場からの声がなかったら実現しなかったはずのクルマを、多くの人々のこだわりと期待を乗せて幻のRSとして生みだせたのは感慨深いです。Hondaに現場の声を聴くボトムアップの文化があるからこそできたことだと思います。
お客さまにはなかなか伝わり切らない、多くのこだわりがRSには詰め込まれていると思います。細かすぎて伝わらない、だけど非常にこだわった!というポイントをお聞かせください。
一つ挙げると、ステアリングシャフト※3の先端にあるトーションバーですね。
電動パワーステアリングを制御するためには、ドライバーがステアリングを回す力=ステアリング荷重をセンシングする必要があります。
この荷重をどうやってセンシングしているかと言うと、トーションバーがねじれて、そのねじれをセンサーで計測することで、ドライバーがどのくらいステアリングを回しているのかをセンシングしています。
トーションバーはねじれないといけないので、他の部分より細くなっています。ただ、トーションバーを細くすると、ステアリング操作のダイレクト感に遅れがでるというネガティブ要素が生じてしまうんです。
TYPE Rでは、研究を重ね、細くてもステアリング荷重をしっかりセンシングできる高剛性のトーションバーを開発していたため、このTYPE RのトーションバーをRSモデルで使用することで操舵の応答性を向上させ機敏でリニアなハンドリングを実現しました。
※3 ステアリングからトーションバーまで連結している棒状の部品
エンジン屋からクルマ屋へ 人気車種を担当する重責と喜び
明本さんはエンジンがご専門です。これまでのキャリアを踏まえて、クルマ一台分を統括する開発責任者を担うということは、明本さんの中でどのような意味を持ちましたか?
私はもともと学生時代にスポーツエンジンに興味があり、エンジン開発に携わりたいと考えてHondaに入社したんです。エンジン部門では、初代VTEC(ブイテック)エンジンの開発、S2000(2シーターのオープンカー)のエンジン担当、そして「エンジンの最高峰を見てみたい」と2000年から第3期F1活動に参加し、2005年にはF1 研究開発責任者を務めました。
しかし、世界最高峰のF1で勝つためには、「エンジンだけ」「1人の力だけ」で世界一になれるものではないということを思い知ったんです。
エンジンの頂点を目指していた私の考えが180度変わった瞬間でした。これからは、世界中のお客様に喜んでもらえるクルマの開発に携わろうと。そこで "ホンダエンジン株式会社(※比喩表現)"をやめて、"ホンダモーター株式会社(※比喩表現)" に再就職したという感じです。
そんな思いを胸に新機種の開発に携わってきましたが、最終的に機種統括である開発責任者を担当することとなり、光栄に感じています。
明本さんはもともとACURAインテグラという北米のモデルを担当していたことから、同じ骨格を使っているCIVICも統括することとなり、今回のマイナーモデルチェンジからLPL(Large Project Leader、開発責任者)として開発現場を率いてこられました。LPLとは現場のプロジェクトリーダーを束ねるリーダーであり、開発コンセプトの決定から、設計、開発、デザイン、コスト、開発日程など、クルマ1台分の開発をとりまとめる総責任者です。実際CIVICのLPLに就任したときは、どのようにお感じになられましたか。
伝統的でHondaを代表する人気モデルを担当する重責はヒシヒシと感じていましたし、CIVICの普遍的な価値・キャラクターは絶対に失わないように守っていくように肝に命じて開発していましたね。
いつどの工程が大変だったかと聞かれれば、いつもどの工程も大変だったと思いますが、もう慣れましたね(笑) それにクルマが出来上がってしまうと、喜びが勝って苦労も苦労じゃなくなるんですよ。
改めて、明本さんの今後の夢についてお聞かせください。
夢というのは、興味が湧いて、憧れになって、それが夢に発展した時に自ら掴みに行きたいと思うものですよね。かつて抱いた「世界一のエンジンをつくりたい」という個人の夢が独り善がりだと気づいた私は、チーム、みんなで築き上げるものをつくりたいと思って改めて車の開発に戻ってきました。
今はお客さんの声もSNSなどを通じてダイレクトに拾うことができる時代です。世界中から上がってくるさまざまな声に気づかされることもたくさんある。喜びの声を目にするたびにこういう車をつくってよかったなと感じます。走る喜びを感じていただけるクルマをこれからもつくっていきたい。それが変わらず私の夢です。







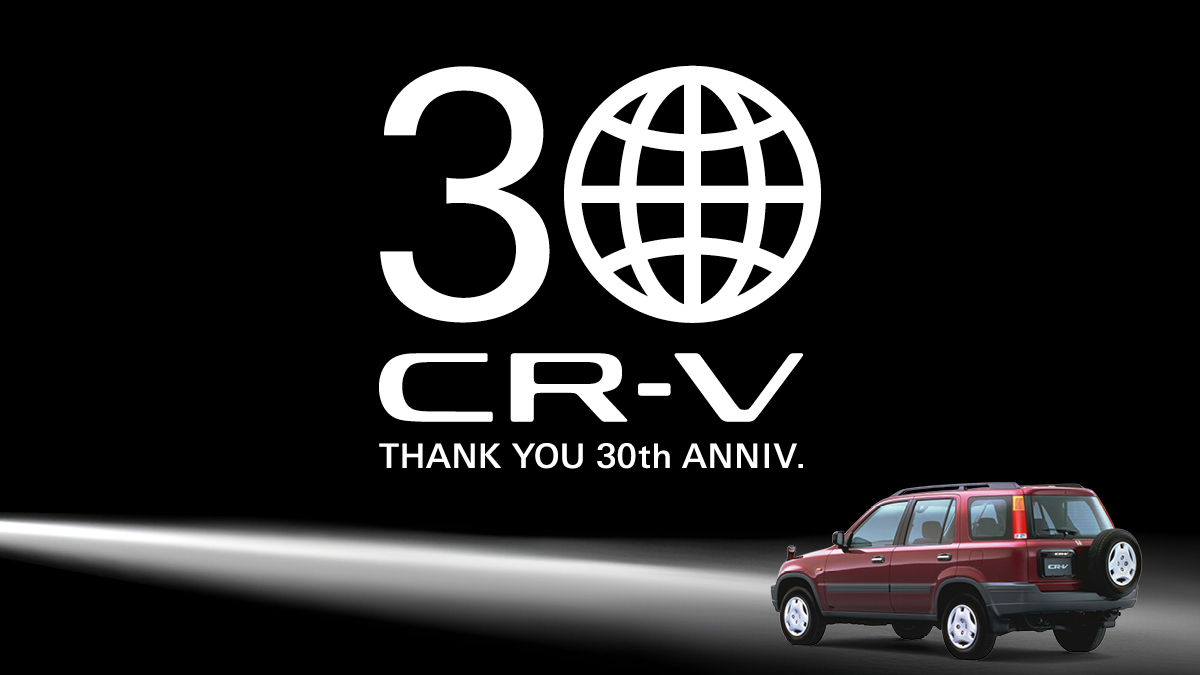


競合他社の燃費性能も上がっている中で、燃費至上主義にせず、あえて多少燃費を落としてでも、CIVICの「爽快感」を象徴するキビキビした走りを追求しました。11代目CIVICとして北米に初めてハイブリッドを導入するにあたり、期待以上の価値をお届けするために乗り心地や静粛性、ADAS(先進運転支援システム)、コネクテッド機能など細やかな進化を行いました。そうしたことが高く評価いただけたのではないかと思います。
乗るとみんなが笑顔になるクルマに仕上がっており、ジャーナリストの皆さんにも高く評価いただきました。
実は11代目シビックは、2021年の発売当初から北米にハイブリッドモデルの導入を検討していましたが、当時はハイブリッドの需要が今ほど高まっておらず、導入を断念しました。そんな背景もあり、今回マイナーモデルチェンジのタイミングで北米にハイブリットモデルを導入し、市場で非常に高い評価を頂いたので喜びもひとしおです。