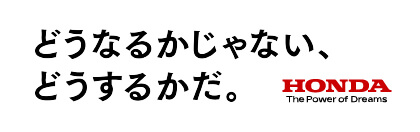Sustainable impacts 2022/05/09
アジャイル開発を推進し生産領域のソフトウェア開発に取り組むエンジニア
入社以来ソフトウェア開発に携わってきた谷野は、現在アジャイル開発の推進に励んでいます。新たな開発手法を取り入れた背景にあるのは、Hondaが抱えている課題の存在です。谷野がこれまでに関わってきたプロジェクト経験を振り返るとともに、Hondaのソフトウェア開発のあるべき姿について語ります。

谷野 伸治Shinji Tanino
四輪事業本部 ものづくりセンター生産技術統括部 車体生産技術部 デジタル技術課
2000年にHondaに入社し、ホンダエンジニアリング(現在は四輪事業本部ものづくりセンター)でソフトウェア開発に携わる。組立支援システムや LET*の開発を進めるとともに、アジャイル開発を推進。
*Hondaが独自に開発した検査診断機。Line End Testerの略称
ホンダエンジニアリングでソフトウェア開発の経験を積む

谷野は大学時代に工学部で学び、エンジニアとしてHondaに入社しました。
谷野 「もともとクルマに興味があったわけではなく、大学では太陽電池の研究をしていました。入社当時はHondaでも太陽電池の事業を進めていたので、携わりたいと思って入社したんです。しかしホンダエンジニアリングの太陽電池を開発している部署へは配属されなかったため、興味のあったソフトウェアやシステムの開発を希望しました」
谷野が2000年にHondaへ入社して最初に取り組んだのは、カーシェアリングに関するシステム開発です。クルマに載せるシステムやサーバー側にある管理ソフトウェアの開発プロジェクトに携わりました。
谷野 「シンガポールの現地メーカーが開発を行っていたため、何度も出張して現地の方と打ち合わせをしていました。サービス自体をシンガポールで行い、システム開発も現地のメーカーに依頼していたので、仕様を決めてテストや検証をするために出張していた形です。
当時カーシェアリングは先進的で、時代に先行しすぎたがゆえに事業はなくなってしまいましたが、挑戦はとてもおもしろかったですね」
現在はデジタル技術課に所属し、これまでの経験を活かして働いています。
谷野 「デジタル技術課は、現場知見とデジタル技術の融合を領域横断で実行し、クルマ1台分の開発・生産の質とスピードを革新するためにできた部署です。私は入社以来、工場の生産設備や生産プロセスの開発や効率向上に取り組んできたので、デジタル技術課でもソフトウェア開発をリードする立場にいます。
過去、組立支援システムの開発など行い、現在は主にLET(Line End Tester)と呼ばれるクルマにつなげて検査する機器の開発と、変化に追従できるソフトウェア開発プロセスの推進を行っています」
現場からの要望を受け、世界初の生産ラインを支援するシステムを開発

谷野は、ハイブリッド車に搭載されるIPUの組立支援システムの開発にも関わってきました。2011年度は東日本大震災やタイの洪水などでHondaも大きな影響を受け、国内外でハイブリッド車の生産台数が急減し、その後急増したのです。このような生産台数の変動への素早い対応が求められることから、多機種少量生産で変動に強く、誰でも作業可能な生産ラインの要望がありました。
谷野 「IPU*(バッテリーと制御装置が一体になったパーツ)を生産するラインでは、最初はセル生産といってひとりが最初から最後まで組立てる工程で行っていました。ただし、部品点数が多く作業手順が複雑だったため、作業者が手順を覚えきれず間違える恐れや、作業者により組立品質がばらつく可能性があったんです。そのため、生産台数が一定になりにくい、という懸念がありました。
そこで、作業のガイドをしてくれてトルクやシリアルナンバーのチェック、手順の確認などができるシステムがほしいと現場から要望があがりました。課題を解決するために、IPU*の組立支援システムを開発し導入したのです」
*ハイブリッド車の重要部品であり、モーターを回す電力を効率よく供給するユニット。Intelligent Power Unitの略
IPU組立支援システムの開発には、ASIMO開発のために作ったソフトウェアを活用しました。実は、このASIMOの組立支援システムをかつて作ったのも谷野だったのです。部品点数と作業手順が多いASIMOの組立支援システムを利用し、IPU組立のニーズに合わせて機能追加しました。
谷野 「開発したIPU組立支援システムは、まず鈴鹿製作所と埼玉製作所の工場に導入しました。埼玉製作所で約3.5倍の増産計画となったとき、約2.5カ月で設備対応が完了し納期短縮に貢献することができました。その後、システムは台湾など海外工場にも導入を拡大していきました」
IPU組立支援システムの機能として、まず作業者への案内が挙げられます。組立情報を視覚的に表示し案内することにより、誰でも組立が可能になったうえに習熟期間の短縮につながったのです。
また、トレーサビリティ機能を付けたのもIPU組立支援システムのポイントです。
谷野 「ワークに対して各種組立データを紐づけることで、何かあってもすぐに履歴を確認できるようにしました。トレーサビリティ機能により、トルクが小さかったり違ったものを組立てたりするようなミスをなくすことができ、品質管理が可能になりました」
IPU組立支援システムを作るうえで谷野が意識したのは、現場の作業員の使いやすさです。
谷野 「システムでは、現場で作業シナリオを育成できるようにしました。作業手順と作業スライドは現場の方が使い慣れているOffice製品で作り、現場でいつでも修正や追加ができるようにしたのです。そうすることで現場の方がより理解しやすいシナリオに育てることができ、組み間違いによるミスを減らせます」
次の手を打てなかった反省を活かし、アジャイル開発を推進

ASIMOやIPUの組立支援システムを経て、谷野はタイの工場に入れる新たなシステムの開発にも携わりました。
谷野 「生産現場では通常1本のコンベア上を流動する車体に、組立作業者が単一工程で部品を組み付けていく方式でした。一方、タイの工場に新たに導入されたARCライン*は、今までの生産ラインとは異なり、組立作業者が広範囲の工程を受け持ち、複数部品の組立を行いながら、コンベア上を流動します。多くの作業を一気に行うことで、人の入れ替わりや無駄を最小化できる効率的なラインでした。
ただし、ひとりが多くの作業をしようとして忘れてしまったり、新人が入ったときに対応できなくなったりするという問題がありました。そこで、作業案内の機能に特化した組立支援システムを導入しました」
*四輪完成車で世界初となる車体組立ライン。Assembly Revolution Cellの略
新たなシステムを展開するなかで大変だったのは、これまで必要とされていなかった仕組みについても考えなければならなかったことです。
谷野 「新たなシステムではタブレットがラインと一緒に流れていくので、無線のネットワークが必要でした。つまり生産現場で無線が切れた場合、不具合になり、ラインが止まって量産できなくなります。そのため、無線ネットワークが切れるリスクをいかに抑えるかがポイントでした。
私たちはインフラの技術者ではないので、無線ネットワークの安定化といっても拠点工場のインフラ設計など対応できないことも多くありました。このARCラインというのは文字通り、環状の生産ラインなので、確実に通信できるエリアを一部に狭め、何か工程に変化があった場合は、確実に通信できる箇所で工程データをダウンロードできるように工夫しました」
しかし、部品の配膳が最初にあるので、多少組立手順を間違えたとしても現場の方はきちんと組立てることができたのです。つまり、人は覚えることができる、ということ。そのため、タイの工場に導入したシステムが別の場所でそのまま展開されるということはなく、最終的に使われなくなってしまいました。しかし、その経験こそ、現在デジタル技術課で実践されているアジャイル開発に役立っているのです。
谷野 「このシステムが使われなくなったあと、本当にまったく必要ないのかをきちんと検証する必要があったんです。アジャイル開発を始めた今となってはよくわかります。ひとつのシステムが使われなくなったとしても、その後に形を変えて支援するシステムを作るというアクションを取れなかった反省こそがこの時の最たる学びです。
この経験がアジャイル開発に役立ちました。開発では変化に対応しなければならず、何が必要かはやってみないとわかりません。最初からいらないと言うのは簡単ですが、やってみること自体に価値があり、使い方が変わったとしても次の手を打ち続けることが大切です」
谷野の所属するチームではお客様が本当に必要としているものを最短日程かつ高品質で提供するため、2019年からアジャイル開発の手法を取り入れたのです。
効率化を求める場合、ソフトウェアはある程度知識のある人が開発を行い、導入して運用することになります。しかし、その導入時の担当者がいなくなると変化に対応できなくなってしまうという問題があります。そこで、アジャイル開発を進めながら携わるメンバーが交代で開発するなど知見を共有し、経験者を増やすことにしたのです。
谷野 「自動車の生産技術領域出身のメンバーが多く、ソフトウェアに精通した人は少ないんです。技術的なバックグラウンドもないため、アジャイル開発の概念はわかってもピンとこないことが多い。
アジャイル開発の考え方自体には、皆しっくりきています。一方で、結果を含めていいものだとわかってもらえなければ開発方法は根付かないと思うので、今はアジャイルの手法を取り入れながら、チーム内で小さな成功体験を積み上げているところですね」
アジャイル開発をデジタル技術課で根付かせるため、外部のコーチを呼んで実践していきました。デジタル技術課では、今後もアジャイル開発を体験できる人材を増やしていく方針です。
「楽しく仕事をする」というモットーのもとチームにノウハウを蓄積する

谷野が20年近くずっとHondaでシステム開発を続けているのは、自身のモチベーションにつながることが明確にあるからです。
谷野 「自分で提案したシステムを作ったこともありますし、根拠を持って提案をすると、『やりたいことをやってみて』と受け入れてもらえますね。また、Hondaでは同じ価値観を持つ仲間と開発を進められます。
たとえばアジャイル開発を推進する場面においても、常に現状を打破しようという課題感を共有することができました。このように変化を主体的に起こすことができる“ずっと一緒に仕事をしたいと思える仲間”がいて、刺激を受けながら仕事ができることは働くモチベーションにつながっていますね。
ソフトウェアは進化が早く、技術が大きく変わるので覚えなければならないことがたくさんあります。技術や知識は、日々インプットし続けなければいけません。だからこそ、アジャイル開発を経験して、組織やチームで課題解決できる環境を作ることが大切です。
自分自身の経験も含めて、ソフトウェア開発は属人化しやすいです。自分が作っている部分しか知らないことも多くありますが、それでは限界があります。チームで動くためには知見を共有し、組織に蓄積する必要があると思います」
アジャイル開発はまだ始めたばかりで、経験者を増やしている段階です。これから成果が形となり、Hondaの課題解決につながると谷野は考えています。
谷野 「Hondaは有事の際に皆の力を結集して解決することが得意です。その経験は個人の積み上げにはなりますが、手法として客観的に振り返りながら経験を組織に蓄積していきたいと考えています。
アジャイル開発では、すべてを自分事としてとらえ日々自分たちが成長していくことを目指しています。そのマインドが定着して、成長していけるような組織やチームを作るのが目標です」
目標達成のために動くなかでも、谷野は自身のモットーである「楽しく仕事をする」を心がけ、チームメンバーにも楽しく働いてもらうために工夫しています。
谷野 「自分も周りも楽しみながら働ける環境が理想ですね。これからも長くHondaで働いていきたいと思っているので、仕事そのものを楽しみたいと思っています。
周りのメンバーにも楽しく働いてもらうためにコミュニケーションを重視することに加え、チャンスを提供するようにしています。自分がこれまで先輩にしてもらったように、提案があったら、まずはやってみてと言うようにしていますね」
Hondaの課題を見据えながら、自身や周りの働きやすさを考えてデジタル技術課のプロジェクトを率いている谷野。
今後アジャイル開発を経験したメンバーが増え、Hondaがさらに成長していくためにこれからも前進していきます。