「守っていたらダメ」──HTF実行委員会が“議論の熱”を絶やさない理由

HTFを「年に一度の社内イベント」で終わらせない。
技術者に光を当て、議論で磨き、次の挑戦へ火を渡す。——その“場の思想”を握っているのが、実行委員会です。
彼らが口を揃えて語る合言葉は、たった一つでした。「守っていたらダメ」。
原点は「技術者に光を当てる」こと
須藤:「元々、HTFは“ひとりひとりの技術者に光を当てる”ことが基本ポリシーなんです。社内に、こんな技術がある、こんな人がいる——それを見える化して、ここで意見交換して、議論して、知識を持ち帰る。技術を交換する。そういう場にしたいと思ってスタートさせた取り組みです」
HTFの価値は、研究成果の“完成度”だけでは決まりません。むしろ、同じ会社の中にあるはずなのに普段は交わらない技術が、同じ空間で向かい合い、言葉を交わし合う。その瞬間に、火がつく。
山本:「今回、特別企画での講演についても、いまの技術トレンド——特にAIの流れを踏まえたときに、『AIをしっかり語れる人は誰か』という議論をしました。そこで候補として挙がったのがGoogleのVice Presidentを務められたアルフレッド・Z・スペクターさんでした。
そもそもアルフレッドさんは、Googleの中で“エンジニアに光を当てる仕組み”をつくってきた方。その原点のモチベーションが、私たちのフォーラムや論文委員会が大切にしている考え方とも合致している。だから、今回のテーマでお呼びすれば、技術者に光を当てる話をしていただけるだろうと考えました」
発表する側だけでなく、聴く側にも熱が入る。
“自分の現場へ持ち帰れる何か”が確かにある。だから、また来る人が増えていく。
「守っていたらダメ」──変わり続ける設計思想
整った成果だけじゃない——HTFは「未完成」も扱える場所でいたい
ここが、HTFのいちばんHondaらしいところかもしれません。
外には出せない話、まだ答えが出ていない話、失敗から拾った学び。
そういう“生々しい技術”ほど、本当は現場を前に進める。
北村:「もともとHTFは外に出せないような失敗事例とか、まだ未完成の内容とか。そういうものも含めて、課題を整理して共有できる場だったと聞いています。いわゆる“揺り戻し”っていうほどじゃないですけど、そういう場所に少し戻していきたいなって。」
完成されたスライドの裏側にある、迷い、判断、試行錯誤。
HTFがそれを受け止められる場所であれば、技術者は次の挑戦を“怖がらずに”持ってこられる。
須藤:「もっと荒削りでいい。“助けてください”でもいい。学会ではできない発表ができる場にしたい。」
“きれいな結論”より、“いま詰まっている問い”。
その問いに誰かが反応し、次の打ち手が生まれる。
HTFを、そういう循環の中に置きたい——実行委員会の本音がそこにあります。
育てたいのは、「場がなくても自ら動ける技術者」
HTFは、強い技術を見せる場であると同時に、強い技術者を育てる場でもある。
ここで出会い、議論し、発表し、フィードバックを浴びる。その経験が、外でも通用する“自走力”になる。
鈴木:「答えが出るまで時間が掛かるとは思うんですけど……。ここでの発表でみんなが慣れて、外でも自分ひとりでやっていけるようになるといいなと思っています。」
“HTFがあるから集まる”ではない。“HTFで得た熱とつながりで、次は自分から動く”。その状態までいけたとき、HTFはイベントではなく文化になります。
議論が生まれる場を設計する。議論が起きる。技術者の心に火が付く
HTFの運営は、裏方で終わりません。
技術者に光を当て、議論を起こし、未完成さえも前進へ変える。そのために実行委員会は、毎年フォーマットを“攻める”。
「守っていたらダメ」——この言葉がある限り、HTFの熱はまだ上がっていきます。




 技術者に光を当て、議論で磨く──
技術者に光を当て、議論で磨く──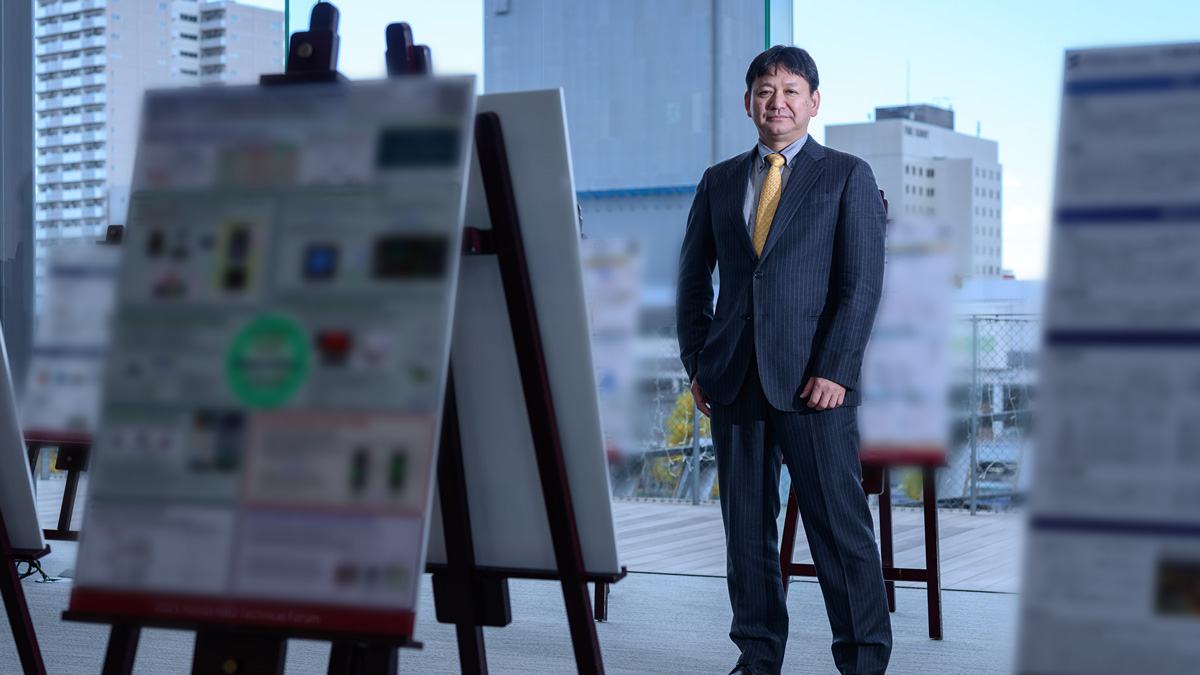 オープンフォーラムインタビュー
オープンフォーラムインタビュー Research Insights
Research Insights Research Field
Research Field