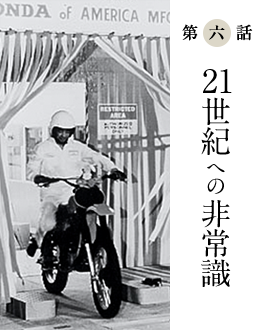ノンフィクション小説本田技研

- 第一話 安全への創造
- 第二話 完全燃焼への夢
- 第三話 自立航法の旅
- 第四話 安全は、こころ
- 第五話 未来へのコース
- 第六話 21世紀への非常識
- 第七話 砂に埋まった夢
- 第八話 夢見るハイブリッド
- ノンフィクション小説本田技研TOPへ


「ええっ、安全対策の研究?それが私の配属ですかあ」
小林三郎は、思わず自分の声が高くなったのに気づかなかった。
「そうだ。新設の第6研究ブロック。メンバー46人。今、ウチの研究所は700人ほどだから、結構大所帯だぜ」
小林は半ば茫然とした。
スポーツカーを作りたくて(株)本田技術研究所に入社したのだ。
それが・・若い夢が急にしぼんだ。
研究所の大食堂でコーヒーを飲んだ。苦い味がした。
テレビは小柳ルミ子の「わたしの城下町」を流している。ニュースに変わり米国のベトナム反戦運動が出た。1971年とはそんな年だった。
前年には大阪万博が開催されている。自動車の安全には関心さえ払われない頃だった。突然、小林から離れた席で笑い声が弾んだ。
エンジンや車体の連中のようだ。───来年出る初代シビックのチームかなあ。ああいう所には・・俺は行けないんだ。
安全の"6研"か。
──小林はコーヒーを飲みほした。やはり苦かった。
この6研はやがて数々の独創的な安全デバイスを生みだすことになる。
4WS(4輪操舵システム)、4輪ABS(アンチロックブレーキシステム)
──だが、それはずっと後のことでスタート以来10年は何も出てこなかったのだ。
見向きもされないがため、いつしか"猫またぎの6研"と呼ばれた。
小林の担当は、猫もまたいでゆく地味な6研の、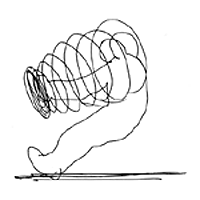 なかでも難関のエアバッグシステムの開発だった。
なかでも難関のエアバッグシステムの開発だった。
小林たちは議論を重ねた。
人間は神様じゃない。時にはミスをする。
事故を未然に防ぐためのブレーキ等の研究は一次安全だ。
不幸にも衝突が発生した際の二次安全をも達成するんだ。そのひとつがエアバッグだ。
ぶつかった瞬間、車と人間の間に袋を膨らませ衝撃を緩和するという発想を現実にするんだ。──しかしそこには山ほど未踏の問題があった。
世にないものを初めてつくるのだ。
こうした装置を「ワンショットデバイス」という。
つまり、「一回使ったら、おしまいだぞ」なのだ。「必要時は必ず、あっというまもなく開かなくてはダメだ」
──それだけではなかった。
「お客さんは勿論だが整備中、車は時に振動する。それで誤作動じゃダメだ。扱う人にも安全でなくては」
概念、理論、技術を手さぐりで這うように追いながら、
超のつくかつてない信頼性の実現が巨大な壁となって立ちふさがった。
初めある段階までゆくと思った3年は矢のように流れ
思い通りではなかった。
さらに数年が無情に過ぎ去った。月日は重なるばかりだった。
日本の首相は5人、米国大統領は3人代わっていた。
生命にかかわる研究の宿命なのであろうか。困難を極めた。
国内でも米国でも他社は撤退したと風の噂が流れた。
「まだやってるのか」──そんな声が社内外で飛びかう。
小林は孤独だった。
技術開発には予測というものがある。その先の見通しが立たない。
やってきたことが全てむだに終わるかもしれない。
辞めたい。毎夜そう思った。だが、もう部下のいる身だった。
10数人のチームは4人に減り、その責任者なのだ。
ある日、計画説明に上司を訪れた。「小林君、これ中止だ」「えっ!」
小林は、ハッとした。そうだ、今止めたら部下の希望が消える。ひきさがるものか。「やります」「中止にしよう」「いえ、絶対やります!」───
押し問答が1時間続いたろうか、遂に上司は折れた。
「そこまで言うならやろう。が、必ず完成させるんだ」
──その夜、小林は結局自分の情熱が計られていたのだと気づいた。
そう、社内でも効率最悪、10年何も生まずの"猫またぎの6研" を未だ閉じもしない。先の見えない開発を
自由? 何て辛い自由なんだ。それが俺のホンダか。
(今に見ていろ、バカヤロー!)小林は、星が瞬く夜空に向かって吠えた。
部下は僅か3人、研究は長期戦、回りは批判の海。ともすれば意気消沈に襲われる。小林は明るく話そうと努めた。声の音程を高めた。早く話した。
元気を出すことが仕事の一部になった。
ボクシングのビデオを見て、役員に会いに行った。
亀の歩みでもエアバッグ基本システム研究は進んだ。
車両試験を始めた。衝突時安全の開発だから、車をつぶさざるをえない。
新部品の型代もテスト車も高額を極める。
(一台で俺が一生かかって家一軒建てられる金だな)
それを10台、20台とつぶしていった。が、完成はなお先だった。
「参ったな」小林たちは副所長川本信彦(現社長)につ
「金つかうだけです、こんなこといつまで・・」
「お前が使う金位で会社がつぶれるか、ジャンジャン使え!絶対止めるな!」
4人の眼の色が一変した。
───「信頼性技術が最後の山だ」
「故障確率ゼロか」
「そうだが、ゼロは工学的に意味がない、設計できない」
「神様でないから、どんな機械もある確率で故障しう
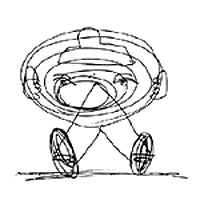
「それを極限まで少なくする」
「どこまで?」
「99.9999%だ!」
「100万回に1回の故障率か、ほぼゼロ!」
「宝くじ一等の確率の方が高いや」
──が、そんな技術経験は日本にはない。小林たちはロサンゼルスへ飛んだ。
NASAが宇宙開発で実践する技法に学ぼうというのだ。
様々な解析手法があった。が、ある程度は知っていた。神髄が知りたいのだ。
と、設計はシンプルに、決定事は出席者と根拠を記録せよ、目標への全員の思考の整合を確認しろ等と宇宙のプロたちは答えた。
何だ、何教わった、当たり前のことばかり・・日付変更線を越えた。
当たり前・・成田まで1時間と機内アナウンスが告げた。
膨大なメモをまた見た。
当たり前・・そうか! 天啓のように、小林は気づいた。
そうか、人間、当たり前のことを完璧に徹底的にやる
1987年2月運転席用ホンダSRSエアバッグシステム技術発表(国産初)、9月レジェンドに搭載発売。
12月10日、会議中の小林に衝突第一報が飛びこんだ。
0.1秒で作動完了したエアバッグは運転者を無傷で守っていた。
興奮が歓喜が激情が体中をめぐる。
「あなたが・・そうか。ありがとう」熱い握手だった。
帰り道の風景が滲んでいた。
(霙か)自分の涙に気づくのは時間がかかった。
(終)

 テクノロジー図鑑 エアバッグ
テクノロジー図鑑 エアバッグ