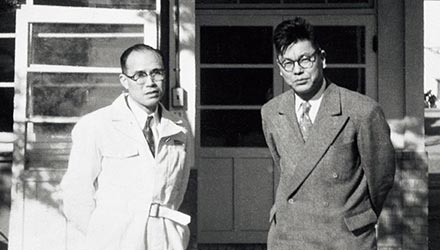いよいよF1へ
1980年代に入ると、ホンダエンジンがヨーロッパF2選手権シリーズで圧倒的な強さを発揮する。一方、国内F2選手権シリーズにもF1を目指した気鋭の外国人ドライバーが多数参戦し、星野一義や中嶋悟らの日本人選手と激しいレースを繰り広げていた。国内のフォーミュラ熱は日増しに高くなっていった。
そうした中、「世界最高峰のF1を鈴鹿で開催したい」という(株)ホンダランド*4の夢と「F1を鈴鹿で見たい」というファンや関係者の気運の高まりが1つになった。ホンダランドはF1開催に向けて動き出す。世界基準に合わせた国際レーシングコースの改修工事を重ねる一方、F2選手権を国際格式のF3000選手権とし、レース運営力の強化に努めた。同時に、F1開催権を持つFOCA*5(Formula One Constructor’s Association〈当時〉)との度重なる交渉を続け、バーニー・エクレストン会長(当時)が1986年11月23日に鈴鹿を視察することが決定した。そして、視察の翌日には開催契約を締結。ついに夢がカタチになった。
- :1968年4月、(株)テクニランドから社名変更。後のホンダモビリティランド(株)
- :F1コンストラクター(製造者)協会
F1日本グランプリ、ついに開催
F1は、世界最高峰のレースであり、特別な存在ともいえた。開催にあたっては、会場設営・看板の設置・オフィシャルのトレーニング・チームの入国ビザの手配から宿泊先の手配に至るまで、準備は膨大な実務を伴った。すべてが初めての経験であり、期日は厳守である。(株)鈴鹿サーキットランド*6では全社員を挙げて準備に奔走した。
1987年11月の開催を前にした6月、前売り観戦券の公開抽選会が行われた。5月1日からわずか1カ月間の短い募集期間だったが、一般販売チケット9万枚の販売に対して、応募は約40万枚。当選倍率4.4倍以上となり、世界最高峰レースに対するモータースポーツファンの関心の高さを証明した。11月、待望の「F1世界選手権シリーズ フジテレビ日本グランプリ」決勝。世界のトップドライバー26人が奏でる最高峰マシンのエキゾーストノートに、スタンドを埋め尽くした112,000人は熱い声援を送った。ホンダは2チーム4台にエンジン供給し、自国での優勝が期待されたが、勝ったのはゲルハルト・ベルガーが操るフェラーリだった。鈴鹿サーキットで初のF1が開催されたその年は、ホンダ第2期F1参戦5年目。ホンダエンジンを搭載したウイリアムズ・ホンダのネルソン・ピケがドライバーズチャンピオンを獲得、この年ホンダは2年連続コンストラクターズタイトルを得た。その後の1988年にマクラーレン・ホンダが16戦中15勝を挙げる快挙を成し遂げるなど、注目が集まりF1ブームが到来した。
- :1987年6月、(株)ホンダランドから社名変更。後のホンダモビリティランド(株)

「世界最高峰のF1を鈴鹿で」 1987年11月、その夢をカタチにした
モビリティワールドもてぎ構想
1980年代の半ば、ホンダの二輪営業部には1つの構想が立ち上がっていた。全国各地の販売代理店との協力で、オートバイを使い、楽しく遊べる場を全国につくる「モーターゲレンデ構想」である。1960年代に取り組んだ「テック」と同様の考え方だった。構想を推進するためにホンダは、「モータースポーツの世界と安全運転を普及するべく、モビリティーを取り巻くソフトウエアを活用したフィールドスポーツや、広大な自然を体験できる施設などを通して、世界のモビリティー文化の発信地となる」ことを目的とした「モビリティワールドもてぎ(仮称)構想」を1988年に発表。山に囲まれたすり鉢状の地形により、音が外部に漏れにくい特徴を持った栃木県芳賀郡茂木町を最終候補地とした。そして1991年2月、施設運営を行う会社として鈴鹿サーキットランドとの共同出資により、(株)ホンダモビリティワールドが設立された。
ツインリンクもてぎ誕生

モビリティー文化の情報発信基地を目指し、1997年オープンした「ツインリンクもてぎ」
モビリティワールドもてぎのプロジェクトメンバーは21世紀に向けた新しいモータースポーツの姿を模索し、モータースポーツがエンターテインメントとして定着しているアメリカに注目した。NASCAR(National Association for Stock Car Auto Racing, Inc.)レースを視察したメンバーは、観客が熱狂する状況に圧倒された。色鮮やかなスポンサーカラーのストックカー(市販形状の車両を使用したマシン)が繰り広げる、オーバルコースでのレース。観客はスタンドに居ながらにして目前でマシンの走りとレースの全容を楽しめる。ヨーロッパのフォーミュラカーレースと異なった観客参加型のモータースポーツがエンターテインメントとして成立していた。
これこそ日本にないものだ、と強く感じたメンバーは、日本初の本格的なオーバルコースの導入を強力に推進。「ただ単に、国内9つめのロードコースをつくるだけではダメだ。参加型モータースポーツの選択肢を豊富にそろえた施設こそが、21世紀には求められているはずだ」。こうした考え方に基づき、安全運転トレーニングのためのコースや設備、および交通文化についての学習施設からなる交通教育ゾーン、ロード・トライアル・モトクロス・トレッキングなど用途別のゲレンデ的なコースで初心者から上級者までスポーツ走行を楽しめるモータースポーツゾーン、多目的スポーツグラウンドやエアスポーツが楽しめるスポーツゾーン・オートキャンプ場・自然の村・イベント広場などを配し人造湖を利用したレクリエーションゾーンと、その他付帯設備として宿泊施設・レストラン・ホール・駐車場などを設置。さらに、必要に応じて本田技術研究所のテストコースなどの補助施設としても使用されるユニークな施設の建設が決定した。
施設名は「ツインリンクもてぎ」に決定。会社名も同様に(株)ツインリンクもてぎに改称された。ツインリンクとは、英語のTWINとドイツ語のRINGをつなぎ合わせた造語で、2つのレーシングコースを表し、ツインには融合という意味合いがあり、「人と自然」の触れ合いや調和、そして「人と人」との出会いや結びつきに通じる想いが込められていた。
全長1.5マイル(約2.4km)のスーパースピードウェイと全長4.8kmのロードコース・ショートコース・ダートオーバルトラック・カートランド・交通教育施設など13の施設が完成し、1997年8月から営業を開始した。1998年3月にはホンダの足跡をしるした「Honda Collection Hall」がオープン、さらに2000年7月、人が自然と楽しく関わり合う中で、あふれる生命を自ら体験し発見する場となる「ハローウッズ」がオープン。ツインリンクもてぎは、21世紀に贈るモビリティー文化の情報発信基地を目指した。


1998年10月にはホンダ創立50周年イベント「ありがとうフェスタ in もてぎ」 がツインリンクもてぎで開催された


Honda Collection Hallには二輪車・四輪車・パワープロダクツ・レーシングマシンを展示
アメリカンモータースポーツを日本に
日本のファンに初めてツインリンクもてぎが提供したアメリカンビッグレースは、1998年3月に行われた「CART(Championship Auto Racing Teams)チャンピオンシップ・シリーズ*7」であった。シリーズ公式戦として行われたこのレースには、CARTにシリーズ参戦するドライバーたちがすべて顔をそろえ、決勝では55,000人の観客が日本初のアメリカンレースを堪能した。最高時速300km超にも達するCARTマシンのバトル以上に新鮮だったのは、ドライバーたちのファンサービスだった。パドックでファンに声を掛けられると気軽に立ち止まり、求められれば写真撮影やサインに応じる。それまでの日本のレース場ではあまり見られない光景だった。アメリカンモータースポーツを開催していく中で、ツインリンクもてぎや日本のモータースポーツ界に「ファンに楽しんでもらうことが、なによりも大切」という考えが根付いていった。

日本で初めてツインリンクもてぎで開催された、アメリカンモータースポーツ「CARTチャンピオンシップ」(1998年)
1998年のCARTチャンピオンシップ・シリーズ開始以来、ツインリンクもてぎはインディカーシリーズを開催し続け、アメリカンモータースポーツを多くの人々に楽しんでいただき、地域とも関係を深めることができた。
2006年、(株)ツインリンクもてぎと(株)鈴鹿サーキットランドを合併、(株)モビリティランドとした。
2011年3月、ツインリンクもてぎは、東日本大震災によりロードコースとオーバルコースであるスーパースピードウェイの一部にうねりや亀裂が発生する被害を受けた。グランドスタンドの建物なども広い範囲で被害を受け、震災後はすべての営業を休止。停電・断水による不自由が続く中、従業員は早期の営業再開を目指して懸命な復旧作業を続けた。
その年に開催するインディカーレースはスーパースピードウェイの改修を検討したが、震災後の大掛かりな土木工事による社会的影響などを考慮して、インディカーシリーズを統括するIRL(インディ・レーシング・リーグ)と協議の結果、急きょロードコースに変更してINDY JAPAN THE FINALの開催となった。13年の歴史を締めくくる記念イベントとして、震災を乗り越え、従業員全員が心を1つにしてつくり上げた最後のインディカーレースであった。以来10年あまりが経過し、オーバルコースは、当初のアメリカンモータースポーツ振興に向けた役目を終えた。インディカーシリーズで培ったアメリカンモータースポーツスピリットは、ツインリンクもてぎや鈴鹿サーキットでの開催レース・イベントに引き継がれていく。
- :オープンホイールマシンを用いたチャンピオンシップ・シリーズ
鈴鹿サーキット開業60周年
ツインリンクもてぎ開業25周年
高速道路がない時代に誕生し、日本の自動車産業とモータースポーツ文化を支え続けてきた鈴鹿サーキットが、2022年、開業60周年を迎えた。21世紀に向けた新しいモータースポーツの姿を模索して誕生したツインリンクもてぎも、同じく2022年に25周年を数えた。
長い年月を経た今も、2つのサーキットは、さまざまなイベントの開催で人気を博し、隣接するパークは人々の笑顔と歓声であふれている。交通教育センターでは、白バイ警察官や企業ドライバーの講習のニーズが高く、一般の方もクルマとバイクのスクールを楽しんでいる。高齢者も安全運転を学んだり、運転復帰プログラムに取り組むなど、個の自由な移動を安全に楽しむためにモビリティランドはチャレンジを行っている。
これまでモビリティランドは、「操る喜び」「チャレンジして成長する」という、ホンダ創業者の意志を原点にモビリティー文化の醸成とモータースポーツの振興・人材育成の実践フィールドとして歩んできた。2022年創業60周年を機に、ホンダグループ総合ブランド強化と企業の社会的信頼性向上を目指して、ホンダモビリティランド(株)と社名を変更。原点を再認識し、ホンダとの相互一体感を高め、さらなる飛躍を目指している。
鈴鹿サーキットは、「世界のSUZUKA」のプレゼンスイメージをさらに強化すべく、VI(ビジュアルアイデンティティー)を一新。ツインリンクもてぎは、モビリティーと人と自然が共生するテーマをより色濃く表す、モビリティリゾートもてぎへと名称を変更した。
モビリティー文化の醸成とモータースポーツ振興、カーボンニュートラルや交通事故死者ゼロに向けたホンダの取り組みとともに、商品・サービス両面で新たな価値の「モノ」「コト」を提供していく。それにより次世代ファンを増やし、さらに存在が期待される鈴鹿、もてぎならではのモビリティパークへの進化をこれからも目指して、ホンダモビリティランドは歩みを続ける。

2022年9月 モビリティリゾートもてぎで開催された
MotoGP 第16戦 日本GP 決勝

2022年10月 鈴鹿サーキットで開催された
F1 第18戦 日本GP 決勝